みなさま、カリメーラ(こんにちは)!
二ヶ月前エッセイ第十二回をお送りしたとき、世界がこんなに激しく変わってしまうとは想像もできませんでした。被害に遭われた方々、苦難と戦っておられる方々にお見舞い申し上げます。
ギリシャはヨーロッパの中では比較的被害を小規模にくい止めた方で、二ヶ月続いたロックダウンの解除が五月後半から徐々に始まりました。
 【ギリシャ厚生省(Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Υγείας)の標語「家にいよう(ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ、メヌメ スピティ)」】 |
この期間中、「
■「現代ミステリ作家クラブ」HP(「閲覧室」コーナー)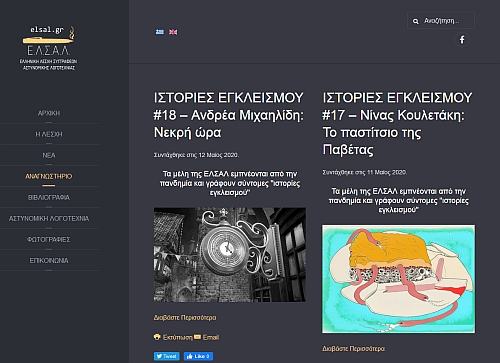 |
500語程度という制限があるようで、文字通りの《掌編》です。自主隔離をめぐるエッセイ風作品から長編を超圧縮したようなものまで様々ですが、何をどう削るかが腕の見せ所です。短いだけに各作家の特質がよく現れています。《リアリズムの極北》アポストリディス【エッセイ4回】は軍事政権下で監禁され拷問を受けた男の手記、「おばあちゃん」のクレタキ【エッセイ5回】は自宅にこもってパスタを作る孤独な女性の心に去来する切ない過去。ミステリ的風味が利いていると感じたのは、十年間復讐の準備と遂行にかける主人公の執念をこの短さに収めたアーナ・ダルダ・ヨルダニドゥ【エッセイ6回】「鏡の中に」でした。
◆《旬》の作家三人目アザリアディス
さて今回は三人目の《旬》の作家グリゴリス・アザリアディスをご紹介します。と言っても1951年生まれなので、エヴィア島警察が舞台のシモスやスウェーデン移民警官のヤニシスという他の《旬》の作家よりも一世代上です。
2010年の経済危機のあおりで失業し随分と苦労したそうですが、そんな中かつて執筆し引き出しに眠っていた原稿に手を入れ(もともとミステリ小説マニア)、2012年デビュー長編作『かつての借り』として上梓しました。翌年『マリナ・フィリプの最後の公演』が続きます。私が読んだのは批評家になかなか評判のいい第三作『殺人者のモチーフ』(2015年)です。
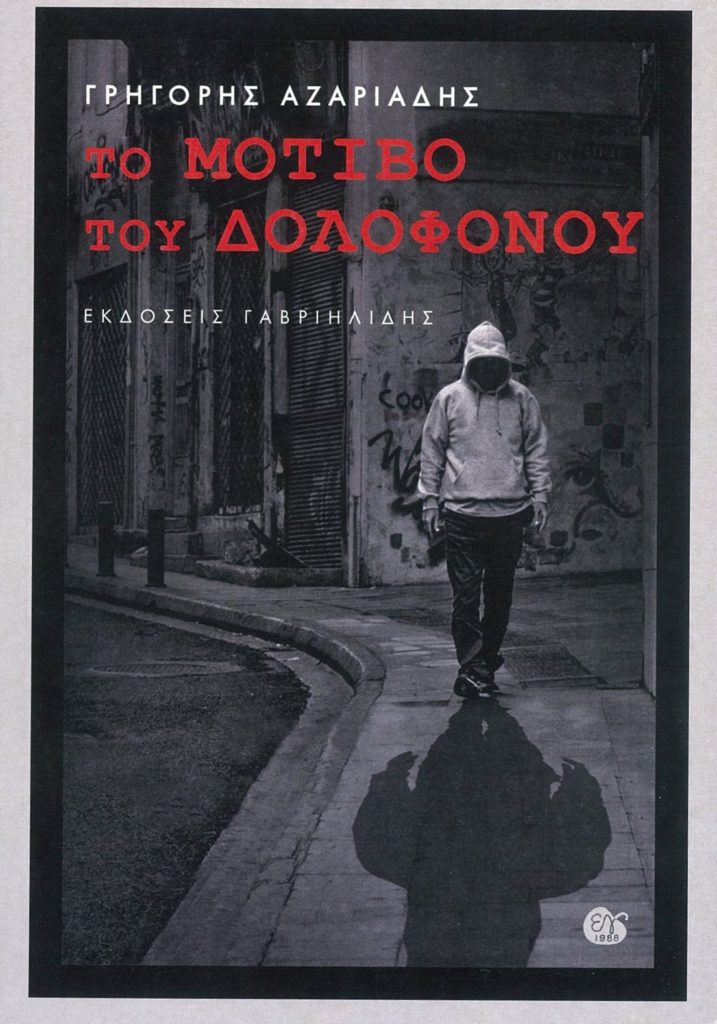 グリゴリス・アザリアディス『殺人者のモチーフ』 グリゴリス・アザリアディス『殺人者のモチーフ』ガヴリイディス社、2015。 |
地中海ノワールの傑作と聞いていたのですが、意外にもロッテルダムの大学風景で幕を開けます。心理学の大学院ゼミで論文をこっぴどく罵倒され傷ついた人物が相手の教授に殺意を抱き、復讐を想像しながら拳銃を手に部屋を出ます。珍しやオランダが舞台の事件かと思ったら、実はここまではある原稿の一部で、その後ストーリーはギリシャに飛びます。
アテネの街角で犠牲者の腿に三発の銃弾、間を置いて腹部に二発、さらに胸に二発、最後に眉間に一発のとどめ、という実に残虐な射殺事件が起こります。アッティカ警察本部の殺人課チームが事件を追いますが、犯人は警察をあざ笑うかのように陰惨な犯行を続け、あと一歩のところで捕まりません。毎回の犯罪で犯人が儀式のようにこだわる八発の銃弾という《モチーフ》の意味は一体何なのか? 次の犯行はいつどこで? 何か法則があるのか?……
捜査チームを率いるのは殺人課トリピ女警部。前作から登場しているようです。白いTシャツの上に灰色のカレッジパーカーをはおり、ジョーマローンのグレープフルーツ・コロンを愛用、タバコの輪をプカプカ吹き上げながらフラッペ(アイスコーヒー)のカップを手から離さない、という風になかなかキマってます。シングルマザーとして女の子を育てながら、屈強な部下たちを指揮します。元夫はチラッと登場するのですが、離婚の情況などは全然語られません(たぶん前作で説明済み?)。
周囲も個性的な役者がそろっています。女たらしで絶えずへらず口をたたきながら抜群の行動力のある巨漢ブリニス巡査長、謎の理由で退職した父の意志を継ぎシリアルキラー逮捕に執念を燃やすモラリス警部補、よき家庭人で奥さんの手作りホウレンソウパイの差し入れを持ってくるドナス巡査長、警察組織改革を進めてきた頭脳派ヴェルギニス准将、その良き後輩で現在の殺人課を仕切る慎重派スタヴリディス大佐といった面々。
作者がスウェーデンの集団警察官もの《マルティン・ベック・シリーズ》に強い影響を受けたというのも頷けます。あのシリーズでも主人公ベック警部の周囲は皮肉屋の相棒コルベリ、戦闘・破壊力随一のラーソン、歩くコンピュータ・メランデルなど個性派ぞろいでした。
実は犯人は最初から登場します。街角の陰湿な虐めや悲惨なニュースを目にすると何やら心のスイッチが入り、念入りに殺しの装いを整えては凶器を手に街にくり出す様が繰り返されます。長身で、灰色のパーカーに頭を覆うフード(本の表紙デザインのような感じ)、と常に同じ衣装で現れ被害者に近づいていく姿は鬼気迫るものがあり、狙う者・狙われる者という多人称視点の切り替えの多用によって、読者は犯行へと引き摺られていきます。このへんのスリラーの書きっぷりは作者の持ち味の一つのようです。
他方で、ギリシャ警察のリアルな捜査ぶりもまたこの作家の狙いでしょう。取材・準備に二年かけたという精密な描写には恐れ入ります。
伝統的な聞き込み捜査の上に、検屍・遺留品蒐集分析・DNA鑑定・弾道解析と細分化された科学捜査が、少しずつシリアルキラーを追い詰めていきます。ただ、そう簡単に進捗するわけではありません。そもそもただ一人の犯人を相手にしているのかどうかさえ特定するのに困難を極めます(もちろん読者はそう期待しますが)。
じわじわと直線的に物語が進みますが、冒頭の原稿がオランダ警察から送られてくるあたりから話がうねり始めます。十数年前にロッテルダムで類似のモチーフの連続殺人が十件あり、その犯人はなんとギリシャ人だというのです。しかもこの男は告白の原稿を残しながらも警察との銃撃戦の最中にすでに死んでいるらしい。さらに、トリピ警部たちがアテネの未解決事件を調査するうちに、これまた似通ったモチーフの殺人事件四件が明らかになります。犯人が実は生きているのか? あるいは模倣犯? 米クワンティコのFBIアカデミーで研修を受けたというトリピ警部やヴェルギニス准将はシリアルキラーを巡り議論を戦わせます。政府は「ギリシャは神の統べる慈愛の国なり」の建前から、凶悪犯罪者の存在など公式に認めようとしません。記者たちがテサロニキを震撼させた「セイフ・スーの竜」や「アテネの切り裂き魔」(いずれも実在のシリアルキラー)のことを持ち出しても無視されてしまいます。
黄金期ミステリ作品で繰り返し用いられてきた連続殺人事件は、遺産狙いや復讐のように動機がはっきりしたものから、隠されたミッシングリンク発見がテーマのものまで実に多彩です。1950年代のヤニス・マリス作品にも調査していくと実はアメリカの大富豪の遺言が発端で……というのがあります。あるいは《賢い人は小石をどこに隠す》式に、狙った人物以外は目眩まし、というのもありますね(クリスティーの某有名作品)。いずれにしても、犯罪者は自分の行為を完全に自覚しており、その動機も常人が理解できるものでした。なので、結末で犯人が逮捕されると読者は溜飲を下げられました。
ところが時代が変わると、犯人自身にも行為の意味が分かっているのかどうか怪しい場合とか、犯人本人にしか通用しない不可解な動機とかの事件が現れてきます。かつてのマザーグースの歌詞通りに犯罪を続ける犯人などはすでに片足をそちらにかけています。
さて、『殺人者のモチーフ』の長身パーカー男は一体どんな原理で動いているのでしょうか? 読者は最後にカタルシスをもらえるのか?
◆リアリズムと社会風俗の描写
アザリアディスの持ち味として、ハラハラするスリラーの盛り上げとリアルで地道な警察捜査と書きましたが、考えてみるとこの両者は少し矛盾しています。矛盾と言うか、両立させるのが容易ではありません。犯人は先に場面に登場し、陰惨な犯行が描かれます。その後に緻密な警察捜査が延々と続きます。犯人の顔や名は隠れているので、倒叙ものというわけではありません。が、犯行の様子など予め読者に提示されているので、捜査では後追いでその確認をしているだけのように感じてしまいます。被害者の人間関係の聞き込みや捜査会議での仮説なども細かく語られますが、シリアルキラーは無差別に相手を選んでいるように見えるので、最後に大どんでん返しがない限り、少々じれったく感じてしまいます。
この点はそもそも捜査側と犯人側の多人称視点を取る以上避けられない、構造的な難点のようにも思えるのですが、作家は二つ目の持ち味、つまりリアルな警察捜査に重きを置いており、敢えてこの構成にしているように思います。インタビューでも「私はリアリズムの信奉者」と明言しています。
実際に複数の犯罪が起きた場合、同一犯がどうかの同定は大問題になるはずです。動機を被害者の周辺に求めるのか、無差別犯罪なのかもまた、地味な捜査を通してようやくたどり着ける答えでしょう。そのへんの粘り強い警察捜査を作家自身もまた粘っこく描き続けます。
さらに、小説をフーダニットに特化するなら、直接関係のない人物の暮らしぶりなどは、事件が解決すれば、あれは何だったのか?と余計な情報に思えてしまいます。しかし、アザリアディスは同時代(2010年代半ば)のギリシャ社会の風俗の情報を盛り込んだ作品を目指しているようです。経済危機にもかかわらず抜け目なく立ち回って事業を拡張する建築家。裕福なわけではないのにホームレス支援に奔走する気のいい男。覇気に欠け世の中の変化について行けず没落する雑貨屋。勤務時間が減らされ、ピザのデリバリでこっそり小金を稼ぐ巡査。こういった群像は「犯人は誰か?」を超えて現実の世情を写し取ろうとする作家のこだわりなのでしょう。
ただし、このことがミステリとしての骨格を損ねてはいません。事件の伏線は周到に埋め込まれており、ロシア最大のシリアルキラーの隠れ家巡礼ツアーとか、トリピ警部愛用のコロンなど、冗長に思われた情報が最後に意味を帯びてきて、見事に結末へと流れ込みます。
◆ジェンダーの壁
トリピ警部は娘や新しい恋人との場面もあれば、自ら囮捜査に参加し命を落としかける壮絶アクションもあって主役に違いないのですが、心中の独白が少なく、欠点も弱みもたいして見られないので、人物像がちょっとつかみにくいです。
正直言うと周辺の男刑事たちの方がキャラが立っています。拳銃の出所を求めて暗黒街をうろつき回る行動派ブリニス巡査長や犯行パターンを予測するため犯人の心理と同化しようとするちょっと危ないモラリス警部補など、忘れられないキャラです。
作者が敬愛するシューヴァル&ヴァールー風の警官群像劇を目指すため、脇役の浮き彫りも疎かにしないということもあるかも知れませんが、これに関連してちょっと気になっていることがあります。それは男性作家によるヒロイン造形ということ。これ、けっこう難しいのではないでしょうか。もちろん作家は想像力を総動員して登場人物を造り上げるのでしょうが。アザリアディスはインタビューで「女性警官を主人公にした理由を多くの読者から訊かれるけど、答えは単純。女性(の強さ、能力)への敬意だよ」と答えています。ただし、この遠慮は時に主人公の心奥の弱さ・いやらしさをえぐり出す障害になってしまうのでは、と(読者として)勝手に心配しています……
こう思うのは、もう一人女性刑事をシリーズ主役に据えたギリシャ人作家がいるからです。数学ミステリのテフクロス・ミハイリディス描くオルガ警部補のことです。ボルヘスを愛好する繊細で理知的なこの女性警官が、権力や物質欲にまみれた警察の上司・同僚の中で一人奮闘する姿は読者の共感を呼ぶのは間違いないのですが、長所ばかりでどうも少し理想化されているような印象を受けます(ただし、ミハイリディス作品は目前の事件が解決しても背後の巨大悪は残る、という社会派志向なので、個人の無力さを痛感しながらも正義への純真さを失わないという役回りでこの女性警官が登場しているようにも思いますが)。
逆に女性作家が男性探偵を主役に据える際もそういう理想化の感じを受けることがあります。同じ作者でもポアロよりミス・マープル、ダルグリッシュ警視よりコーデリア・グレイの方が血肉を備えたような感じ、ベイジル・ウィリング博士はなんだか優等生過ぎる感じということです(私だけ?)。コリン・デクスター『死者たちの礼拝』を読んだときモース主任警部が謎を解きながら中年男のいやらしさを垣間見せていて男性作家らしいなと笑ってしまいました。あ、もちろん作品の出来とは関係なく、あくまでキャラのイメージの問題です。『ナイチンゲールの屍衣』『女には向かない職業』『あなたは誰?』『ささやく真実』いずれもホントに楽しませてもらいました(にしても、『女には向かない職業』『あなたは誰?』のラスト、名探偵だから何でも赦される、といわんばかりの行動はちょっとね……)。
トリピ警部ですが、証人たちの外貌や行動に対するひじょうに辛辣な揶揄が時折挿入されることがあります。いちおうキャラに対する作者自身のコメントだと思うのですが、しかし、もしかして彼女の抱える偏見をえぐり出して見せようとしているのかも知れません。そうであれば、作家はジェンダーの壁を越えてけっこう女主人公の心の内奥に飛び込んでいます。
三年後に発表された第四作『暗闇の迷宮』では壮絶なアクションの連続で、前作ではけっこう押さえていたのか思われるほどです。
ハメットとチャンドラー、ギリシャ人作家ではペトロス・マルカリス【エッセイ2回】の影響を作家自身公言していますが、他にお気に入りの作家としてジャン=パトリック・ マンシェットを挙げています。『暗闇の迷宮』はマンシェット『
 グリゴリス・アザリアディス『闇の迷宮』 グリゴリス・アザリアディス『闇の迷宮』メテフミオ社、2018。 |
マラトンの片田舎に隠遁した裕福なワイン商一家が中庭で朝食を楽しんでいます。ところへ二人組の男が現れいきなり小銃乱射、幼い孫を含め五人を惨殺します。まがまがしい犯行は何か過去の因縁を思わせます。長らく外国暮らしだった娘ソフィアが帰国、父の墓前で復讐を誓っているところへ、父親の友人だったパンダレオンなる男が現われ援助を申し出ます。
この光景、どこかで見たような……そう、古代ギリシャ悲劇での一シーンです。トロイア戦争から帰還後、暗殺された父王アガメムノンの墓前でエレクトラとオレステスの姉弟が再会を果たし、父の復讐を誓う場面があります。そのオマージュに違いありません。ノワール版「エレクトラ」ですね。いえ、私のこじつけではなく、実際、アイスキュロスの古代悲劇「供養する女たち」が言及されており、明らかに『闇の迷宮』のモチーフになっています。
◆ギリシャ悲劇のモチーフ
アイスキュロスの作品では、父王を惨殺した母クリュタイムネストラと愛人に対し、姉弟が復讐を決行します。が、『闇の迷宮』の実業家パンダレオンは若々しいオレステスっぽくはなく、ソフィアより二十歳以上年上。しかも、途中から彼に代わってソフィアに協力するのは、なんと一家殺害に関わったはずの若い男《のっぽ》です。マンシェットのヒーローのように殺し屋の技術を持つこの《のっぽ》はなぜかマフィアに狙われることになり、激しい銃撃戦をかいくぐると北ギリシャへ向かって逃亡、その後をソフィアが追います。やがて二人は共闘を約束。この辺は「エレクトラ」をずいぶんひねってあります。
前作に続きトリピ殺人課チームが再登場。「殺人者のモチーフ」事件で自らを囮にして間一髪殺されかけたトリピ警部はようやく後遺症から脱したようです。新しいメンバーとしてマンダス巡査部長が麻薬課から転属してきます。小柄ながら頑強なこの男、あぶれ者でチームを引っかき回しています。群像劇を面白くするにはこういうはねっかえりのメンバーがやはり必要ですね。(マルティン・ベック組も一匹狼グンバルト・ラーソン刑事が登場してから面白さを増しました。)
地道な聞き込み調査を進めるうちに、殺されたワイン商人はどうも薄暗い過去を持っており、かつて強盗団のメンバーだった可能性が出てきます。他のメンバーを裏切り大金を一人占めにしたのはこの商人なのか? 一家惨殺はその復讐? 闇に蠢く仲介者を何人も介して殺しを依頼した黒幕が少しずつ浮かび上がり……にしても、その動機は?
この強大な黒幕を追って、復讐に突き進むソフィアと《のっぽ》、さらにこれを追跡するトリピ警部チーム、という三つどもえの争いになります。疾走感はハンパではありません。ホンダやカワサキのバイクが首都アテネから北の山村まで雨の夜道を駆け抜けます。
古典作品では首尾よく復讐を遂げたものの狂気に囚われてしまったオレステスが流浪しアテネで神々の赦しを受けるまで悲劇は続きますが、ソフィアと《のっぽ》は最後にどこへ向かうのか? ソフィアとトリピ警部の対決は、つまりは私的復讐と法の正義のぶつかり合い。二人が直接対話を交わすシームもあり、この決着がどうつけられるのか、という興味もあります
そもそもアガメムノン王の暗殺は、直接的にはクリュタイムネストラ妃とその情夫が図ったことですが、男女の愛憎関係を超えてアガメムノンを恨む理由が実は王妃にも情夫にもあります。さらに、それらの悲劇は全てかつて祖先が受けたアトレウス家の呪いに覆われている、という壮大な神話物語です。そう考えると、『暗闇の迷宮』はそれらしい(コナン君風の)タイトルをつけたというのではなく、ストーリーを流れる底無しの呪いをなかなか的確に暗示しています。物語が閉じられるとき、登場人物たちは無限の迷宮を脱することができるのでしょうか?
『殺人者のモチーフ』で見られたマルティン・ベック風警察チーム捜査とマルカリス風社会犯罪のスタイルに、さらにマンシェット風の暴走アクションが加わり、様々な要素が混在します。ギリシャ名物B級グルメのスブラキ(ケバブ)のデリバリ車が道を行き交い、闇の殺し屋といえばジョージアかアルバニアが連想されるなど、ギリシャ社会の風俗スケッチもあちこちに盛られています。
ただ、その分ちょっと盛り込みすぎ感も。復讐へ、そして破滅へとひた走るソフィア&《のっぽ》の姿には読者もグイグイひっぱられて行くのですが、その後を丹念に辿るトリピ・チーム(こちらも主役です)のリアルな捜査がどうにもモタモタしています。その間にソフィアは、時に手荒な手段で黒幕の正体を突き止めていくので、「警察を侮るな。影のように追ってくる」などと言われても、ソフィア=エレクトラ姫の方がよほど有能に見えます。
リアリティーに富む警察捜査の描写が持ち味であるのは分かりますが、相反する二組の主役の多人称視点が逆方向に反発し合うこともあるようです。「両雄並び立つ」のはなかなか難しい。
最後にトリピ警部へひと言アドバイス。「タバコ吸いすぎ」。朝起きて一服、出勤して一服。捜査会議の議題が変わる度に一本、火をつけています。彼女だけではなく周りの登場人物も同じ。このヘビースモーカーの伝統はベカス警部、ゲラキス警部ら先輩以来の伝統ですが……【エッセイ3回】。
そもそもギリシャは喫煙率で世界の上位にいます。2016年の統計で男性の喫煙率は世界12位、女性はなんと世界5位。(ちなみに第1位はあのネロ・ウルフのモンテネグロです。バルカン諸国は全般的に高い。)
■トリピ警部のギリシャ語講座■Άναψε τσιγάρο.(アナプセ ツィガーロ)「タバコに火をつけた」 |
次作『眩惑――トリピ警部の冒険』がすでに予告されており、トリピ警部が堂々と表紙カバーを飾っています。
 グリゴリス・アザリアディス『眩惑――トリピ警部の冒険』 グリゴリス・アザリアディス『眩惑――トリピ警部の冒険』メテフミオ社、近刊。 |
ギリシャ悲劇つながりということで、2019年9月にハヤカワ・ポケミスで出たばかりの作品をご紹介しましょう。映画脚本家アレックス・マイクリーディーズの長編デビュー作『サイコセラピスト』です。原著が出たのが同じ年の7月ですから、出版社の力の入れようが分かるというもの。原題は『沈黙の患者 The Silent Patient』で、ギリシャ語訳もそのまま直訳しています。
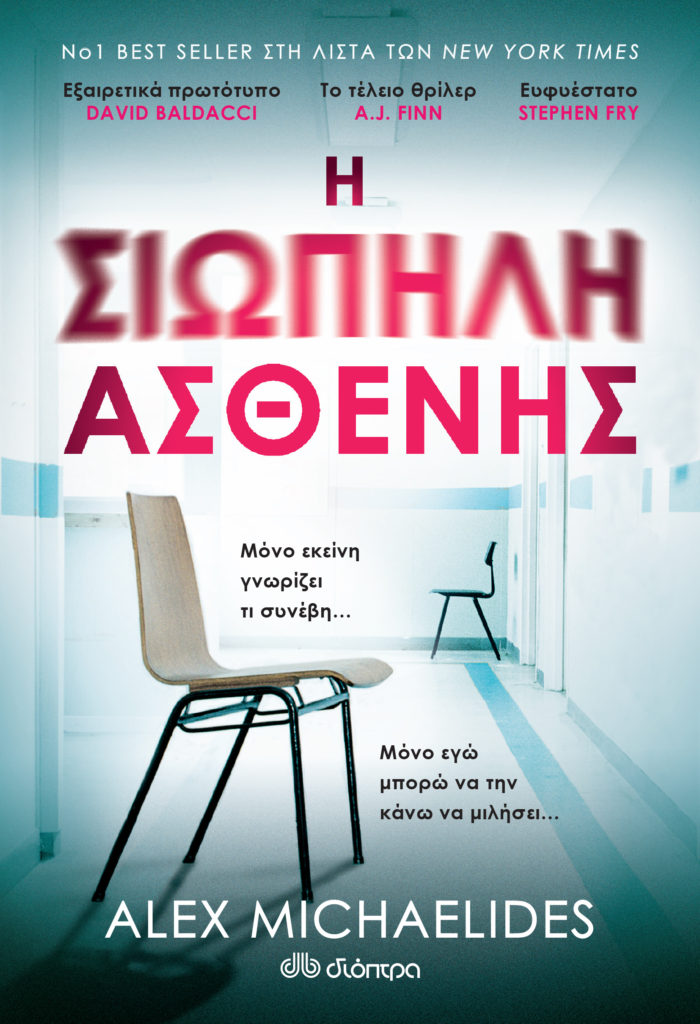 アレックス・マイクリーディーズ『サイコセラピスト』ギリシャ語訳 アレックス・マイクリーディーズ『サイコセラピスト』ギリシャ語訳*訳題名は原題と同じく『沈黙の患者』。 ディオプトラ社、2019。 |
作者の名はギリシャ語読みならミハイリディス。キプロス出身で父親がギリシャ人、母親が英国人。幼い頃から英国育ちだそうです。あの数学ミステリ テフクロス・ミハイリディスと同じ姓ですが、たぶん親戚ではないと思います。
画家アリシアは、夫の殺害現場で発見されて以来ショックからか言葉を発さず、ロンドン郊外の精神治療クリニックに収容されています。手がかりは犯行後に描いた自画像だけ。「アルケスティス」という不可思議な題が付けられています。
彼女はなぜ夫に弾丸を撃ち込んだのか? 真実を語り始めるとき、彼女に何かが起きるのか? この謎と恐怖がストーリーを推し進めます。サイコセラピストの《僕》が志願して治療にあたりますが、自身も父親から虐待された過去があって精神が安定しておらず、アリシアの事件は他人ごとではありません。相手を癒すことで自らの癒しも得ようとするうちに、セラピストと「沈黙の患者」の立場が逆転し同化していきます。心に傷を持つ者同士の再生という骨太の物語かと思っていたらどうしてどうして。アリシアが《僕》に日記を手渡すあたりから話が錯綜。ついにアリシアが言葉を発し始めるとストーリーはグラグラと崩壊、破綻。《僕》がある人物の行為を目撃する際、顔がよく見えず自分が幽体離脱しているような気がした、ってホラー? 「ウイリアム・ウイルソン」? それぞれの人物の妄想の集積なのか?という、このどっちつかずの感じは最後に至ってメビウスの輪のように見事に着地します。
破綻していたのは私のほうでした。
◆ギリシャ古典劇のモチーフ
作品では古代ギリシャの悲劇作家エウリピデスの「アルケスティス」がモチーフとして使われますが、利用の仕方が実に巧みです。
画題の謎を解こうと、《僕》はクリニックの診療部長のギリシャ人教授に質問します。教授は「ギリシャ人ならギリシャ悲劇すべてに精通していると思ってるのかね」と苦笑しますが、この「すべて」がポイントです。「エレクトラ」や「オイディプス王」などの超有名作を知らないギリシャ人はいないでしょうが、問題の「アルケスティス」は微妙です。ヘタするとそんなのあったっけ?と思われてしまいそうなマイナー作。そもそも結末がハッピーエンドっぽいので悲劇と言えるのかどうかもあやしい。
あらすじは小説中で説明してくれるので、知らなくても問題ありません。
死を目前にしたアドメトス王は、身代わりを探せば運命を逃れられると知りますが、周囲は誰もそんな役を引き受けようとしません。唯一献身的なアルケスティス王妃が自ら犠牲なるのを受け入れます。折から客人となっていた英雄ヘラクレスが憤激して死神と戦い、王妃を連れ戻すという、人間のエゴを描いた、神話というより民話的な趣きの劇です。
マイクリーディーズは悲劇全体のストーリーを小説に持ち込むのではなく、そのある一点(しかし本質的)を利用しています(インタビューによると、このことは昔から疑問だったとか)。
その点というのは劇の結末にあります。アドメトス王は自分のわがままな行為をコロッと忘れ、歓喜の中でヘラクレスに礼を繰り返し、二人の男のとぼけたやりとりで劇は終わります。犠牲にされた王妃としてはたまったものではないはずですが、王は「なぜ家内は突っ立ったままものを言わないんだ」のひとことで片づけてしまいます。ヘラクレスはただ「地下の神々の禁断が解けるまでは声を聞くのは許されない」と答えるのですが……。
アルケスティス妃のこの沈黙が「サイコセラピスト」の謎の核心になっています。
このモチーフを除くと、舞台は英国のクリニックで、ギリシャが出てくるわけではありません。ただ例外的に、ギリシャ人の診療部長ラザルス・ダイオミーディーズ教授が登場します。六十代でかすかなギリシャ語訛りがありますが、すでに三十年も英国滞在。スーツとネクタイでビシッと決め、しかも青年のような茶目っ気があり、すっかり英国紳士です。アリシアの診療でたびたび暴走気味の《僕》を慈父のような寛大さで支える一方、患者優先で経済効果を挙げられないクリニックの閉鎖危機を前に、その対処に奔走する姿がひじょうに好意的に描かれています。
しかし、ダイオミーディーズ、ギリシャ語風に言えばディオメデスはトロイア戦争でアキレウスに次ぐ英雄として敵方の神々にまで傷を負わせ、トロイアの守護神像を盗み出して都を滅ぼした男。そのまま信用してよいものか……?
マイクリーディーズはやはりギリシャ神話をテーマにした次回作をすでに準備中とか。期待しましょう。
| 橘 孝司(たちばな たかし) |
|---|
|
台湾在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっと紹介するのがライフワーク。現代ギリシャの幻想文学・一般小説も好きです。 図書館が古い文庫本を処分するというので、もらってきた中に大量のルパンものがありました。ルパンの自称が「わし」の堀口大學訳とか、(「お・それ・みお」の)水谷準訳『ルパンの奇巌城』(角川文庫版のこれ知りませんでした)とか。真っ先に読んだのは、謎のサインに導かれて島へ渡るヒロインといにしえの地下墓所だけが記憶に残る『三十棺桶島』。冒頭のまるで「八つ墓村」かというような海の殺戮シーンなどは完全に忘却……。第一次大戦末期が舞台の暗いホラー風作品でした。書名には長すぎるという理由で「三十」が削られてしまったのが残念。続けて読んだ『オルヌカン城の謎』もベルギー戦の陰惨な戦闘描写が続き、飛来する砲弾の唸りが耳に残ります。華麗なる冒険ロマンスではない、ルブランの別の一面が見られます。 |
| 【「供養する女たち」所収。トロイア遠征から帰還した王が暗殺される「アガメムノン」、狂えるオレステスが神々の赦しを求める「慈しみの女神」とともに三部作を構成】 |
|
■マイケル・カコヤニス監督、イレーネ・パパス主演「エレクトラ」(1962年)。 【残念ながら日本版DVDは出ていませんが、YouTubeで見られます。ただし、下敷きになっているのは、『暗闇の迷宮』に復讐の連鎖のモチーフを提供したアイスキュロス「供養する女たち」ではなく、(同じテーマを扱いながら)女性の心理に深く分け入るエウリピデス「エレクトラ」です。イレーネ・パパスの不屈の面構えがすばらしい。「ナバロンの要塞」ではグレゴリー・ペックたち潜入部隊を助ける島のレジスタンスでしたね。】 |
| 【「アルケスティス」所収。王妃の犠牲が決まり悲嘆にくれる館で、空気を読めない野人ヘラクレスの牛飲馬食っぷりが笑いを誘います】 |