みなさま、カリメーラ(こんにちは)!
今回ご紹介するのはちょっと毛色の変わった二作です。
どちらも2021年の「パブリック書籍賞」の「長編小説部門」候補作になっています。
この賞のことはエッセイ第17回でご紹介しておきました。2020年には《家族の絆》エフティヒア・ヤナキ『後ろの座席で』が受賞していますが、特にミステリ小説が対象というわけではなく、とにかく読者に評価された面白い作品に与えられます。
 【2021年「パブリック書籍賞」の各部門受賞作。残念ながら「長編小説部門」は別の作品が受賞。「翻訳小説部門」はマーガレット・アトウッド『誓願』、「特別賞」(毎年テーマが変わるようで、今回は「北欧諸国作品」が対象)はジョー・ネスボの新作『王国』が受賞しています。】 |
そういうことなので、今回の二作が息もつかせぬジェットコースター型エンタメ作なのか、ずっしりと重い問題提起作なのか、実はわかりません。同じく候補に挙がっている《スウェーデンの移民ギリシャ人警官》ヴァンゲリス・ヤニシス(エッセイ第12回)の『アマロック』は明らかに警察ミステリですが、今回の二人は私には初めての作家なので、いったいどこへ連れて行かれるのか。ドキドキしながらページをめくることになります。
◆ どこに向かうのか行き先不明――ミノス・エフスタシアディス『クワディ』
なかなか魅惑的なカバー絵に、とにかく不思議な題名。ギリシャ文字は一つ(または二つ)の文字がただ一つの発音に対応していてわかりやすいのですが、外来語だとちょっと曖昧になります。この「ΚΒΑΝΤΙ」はいったい /kwadi/ なのか、/kvanti/ なのかよくわかりません(他にも可能性があります)。何にしても辞書に載るような普通の語ではありません。
 ミノス・エフスタシアディス『クワディ』 ミノス・エフスタシアディス『クワディ』
イカロス社、2016。 |
霧雨に煙る夜のパリ。街角を急ぐ男の前に突如《影》が飛び出し、ナイフが煌めきます。刺殺されたのは南仏在住のドイツ人老画商で、息子とバーで飲んで別れた直後のことでした。
パリ警察の腕利きトゥリエール警視が担当することになり、近隣住民の目撃証言やら、息子テオドールのアリバイやらを丹念に辿ります。ウォッカに目がないというこの人間臭い警視は、ユーゴ紛争でフランスに亡命したセルビア系検死官と組んで、真相を追っていくようです。これはつまり、ギリシャ人作家によるメグレ・テイストのミステリなのでしょうか?
ところが次の章で、いきなり舞台はペロポネソス半島の小さな町エギオに飛び、私立探偵《おれ》の一人称語りに変わります。クリス・パパスなるこの探偵は作家のシリーズキャラのようです。前作ではハンブルグで探偵稼業でしたが、ある事件でしくじり免停となって帰国、故郷でくすぶっています。あれれ、実はギリシャのハードボイルドなのか? にしても、ゴミ箱で拾った子犬と広場の滑り台で遊ぶこの探偵、不思議な造形です。
さて、冒頭の息子テオドールがさるつてをたどって、ギリシャの《おれ》を訪れ、亡くなった父親の埋葬を依頼します。葬儀屋じゃないぞと不満を漏らしながらも、ろくに仕事のない田舎探偵は引き受けますが、旅行で一度立ち寄っただけの、縁もないこの町に父親は葬られることを切望していた、などとテオドールは奇妙な話をします。
注文通り葬式が執り行われますが、列なったのはテオドールと葬儀屋と《おれ》だけ。ところが、ここからまたおかしな展開になります。墓穴の上でテオドールは不可思議な呪文を唱え始めるのです。外国経験の長い《おれ》にも全く理解できない言語です。
翌日テオドールは風貌も声も変容してしまい、フランスに帰った後精神を病んだ挙句、なんと病院のベランダから飛び降り自殺してしまいます。その直前にも謎の呪文をつぶやいたらしい。呪文て、まさかラヴクラフトの「フングルイ・ムグルウナフー・クトゥルフ……」のたぐいなのでしょうか? それともギリシャの幽霊狩人カーナッキなのか? 題名の意味はいまだ説明されず、「ウェンディゴ」だか「ヴィイ」もどきの正体不明の怪異に読者は引きずられていきます。ギリシャ・ミステリでこんなのは初めてです。
 H・P・ラヴクラフト『クトゥルフの呼び声』ギリシャ語訳(11巻シリーズ) H・P・ラヴクラフト『クトゥルフの呼び声』ギリシャ語訳(11巻シリーズ)LOCUS-7社、2002。 【クトゥルフ教信者の群れはギリシャでも増殖中。複数の出版社からラヴクラフトの訳書が出ています。おなじみの触手がちゃんと描かれててうれしい。】 |
とりあえず仕事が片付いたと思っていた《おれ》ですが、オフィスにロシア人画商が現れ、なぜかパリの刺殺事件の捜査を依頼。実は事件当日に被害者と約束しており、買い取るはずだった絵をどうしても入手したいのだが、と打ち明けます。
かくしてギリシャ人探偵《おれ》はパリへ向かい、テオドールからあずかっていた写真を手掛かりに絵の在りか、ひいては殺害事件を調べることになります。事件がはかどらず苛立つトゥリエール警視も《おれ》に接触してきます。
続いて、パリ郊外の豪邸に住む高齢の絵画コレクターが殺されます。167カ所に刺し傷を受け出血多量で死亡、という残忍でいかにもいわくありげな手口でした。絵画つながりの怨恨が疑われます。
さらに、調査で深夜のパリをうろつきまわる《おれ》はアフリカの某国出身者たちの集まる幻想的なクラブに誘い込まれ、べろんべろんになるのですが、おかげで件の絵を持つ女にたどり着き、ついには警察も加わってセーヌ川沿いの家々の屋根上で追うもの追われるものの大アクションとなります。
パリのメグレ風ストーリーで幕を開け、ギリシャのマーロウにラヴクラフト、いったいどこに連れていかれるのだろうと読者の期待と不安が止まらない中、第二部ではそれをはるかに超えたとんでもない大冒険が始まります。
第一部には出て来もしなかったオランダ人ザイブルなる富豪が、バーで出会ったいかにも怪しげな巨漢と意気投合し、世界の深奥を見せてやろうなどという胡乱な誘いに乗って、南アフリカまで出かけていくのです。
二人はケープタウンに入港し、現地の道案内人とともに車で北へ向かいます。猛暑と砂嵐に苦しみながら摩訶不思議な村にたどり着き、現実だか夢だか定かならぬ奇怪な事件に巻き込まれていきます。
最終部では、この異常な冒険譚が力業によって、第一部のパリの刺殺事件やエギオの奇妙な埋葬に繋がっていきます。ドイル長編風の過去にさかのぼる因縁話なのですが、とにかくスケールが大きすぎます。殺人の舞台パリ、被害者の葬られるギリシャの町、謎の男二人が出会うオランダの港町、異様な冒険の待ちうける南アフリカ奥地の村、さらに事件の根はクアラルンプールまで拡がっていく奇想天外の壮大な大風呂敷の物語(もちろん誉め言葉)が堪能できます。
最後のシーンになって《クワディ》が姿を現し、ようやく題名の意味が明かされることになります。
この満腹の内容が、最近の長編ミステリではごく普通の500頁超えの分厚い本ではなく、250頁ほどにどっさり盛り込まれているのには驚かされます。
作者ミノス・エフスタシアディスはアテネとハノーファーで法学を学び弁護士として働いているそうです。2001年に『脱出』でデビューし、『言語なしで』(2004年)が続きますが、どちらもミステリではないようです。パパス探偵が登場するのは第三作『夜の第二部』(2014年)からで、この作品はドイツ語訳も出ています。
|
【ミノス・エフスタシアディス『絶滅危惧種』。『夜の第二部』のドイツ語訳。】 |
続く『ダイバー』(2018年)は《アテネ文学賞Athens Prize for Literature》の候補作となり、さらにフランス語訳されて、《オクシタニ・
後のほうは南仏オクシタニ地方を拠点とする《トゥールーズ南ノワール協会l’association Toulouse Polars du Sud》が2011年に創設した賞で、南方の諸言語で書かれた翻訳ミステリに毎年授与されるそうです。南方の言語une langue du Sudというのは、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語、ギリシャ語に加えて、アラビア語、トルコ語等も含まれており、南欧のインド・ヨーロッパ系言語だけではなく、地中海の諸言語作品を広く取り込もうという目論見のようです。実際の候補作はイタリア語やスペイン語のものが多く挙がっていますが。
| 【ミノス・エフスタシアディス『ダイバー』フランス語訳、ACTES SUD、2020年。】 |
 Prix Violeta Negra Occitanie – Toulouse Polars du Sud (toulouse-polars-du-sud.com) 【2021年の《黒スミレ文学賞》はイタリアのアレッサンドロ・ロベッキ『これは恋歌じゃない』Ceci n’est pas une chanson d’amour(原著はイタリア語)に決まったようです。】 |
◆アイデンティティーの揺らぎ――カテリナ・マラカテ『失った顔』
もう一作ご紹介します。題名からどうしても安部公房『他人の顔』を連想してしまいますが、シュールな世界が展開するのでしょうか。
 カテリナ・マラカテ『失った顔』 カテリナ・マラカテ『失った顔』
メテフミオ社、2020。 |
島に暮す青年ディオニシスはある時母親と激しい口論になり、激高した挙句、猟銃を持ち出しますが、これが暴発してしまいます。四十日後病院のベッドで意識を取り戻したとき、とんでもない結果になったことを知ります。全身の神経や運動器官は無事でしたが、弾丸は顔面を突き抜け、鼻口頬の顔半分が失われていました。嗅覚や言語能力も失くし、コミュニケーションは筆談に頼るしかない有様です。何よりも容貌が変わり果ててしまったことの自信喪失から、自身の殻にとじ籠るようになります。しかし精神科医の忍耐強い協力と勧めで、事故の事情や自身の感情を手記に綴り始めます。
手記の内容を通じて、寡黙で放任主義の父、心配性で過保護の母、故郷を捨てアテネで俳優をやっている奔放な弟の姿が浮かび上がっていきます。都会住まいの美貌の従妹が島を訪れ魅惑された甘い回想も出て来ますが、ほかならぬ彼女との恋愛関係が母親との喧嘩、ひいては事故につながったようです。
この後話は十五年ほど飛びます。ディオニシスは四十前になっており、母親の世話を受けながら部屋に籠る生活を続けています。いまも声は出せず、周囲の世界とはただSNSを通じて関わるだけ。
そんな時ディオニシスの事情をフェイスブックで知ったある女医が、アメリカで実践されているという皮膚移植を勧めてきます。母親は他人の顔をつけて生きていくなんて、と猛反対。ディオニシス自身は先の精神科医や信頼する神父とアイデンティティーにかかわる討論を続けます。
結局両親も周囲も本人の願いを受け入れることになります。高額な手術代や治療費はクラウド・ファンディングで賄おうと、ディオニシスはテレビ番組で素顔を晒すのも厭いません。
その後渡米して、長時間の苦しい手術を受けてからリハビリ、やがてオデュッセウスのようにギリシャに帰国します。
「断片的にして複眼的」と書いているレビューがありましたが、他人との接点である《顔》を失うことで人間関係がどう変わっていくのかが、様々な視点から描かれます。
冷淡に去っていく人もいれば、同じ態度で付き合い続ける気のいい友人もいます。SNSのフォロワーたちも激励賞賛から、手術への非難や嫉妬まで実に様々なコメントを寄せます。
語りの点でもまた多面的です。
主人公はいちおうディオニシスで、彼が一人称で語るのですが、それに劣らぬほどの分量を母親カリオピが語ります。さらにもう一人、手術を勧めた女医のマニアも後半から語り手になり、この三人が目まぐるしく語りを交代します。(父親、女医の夫、顔面皮膚のドナーなどディオニシス以外の男性は語り手にならず、影が薄いのがちょっと気になりました。ただ、父親がそもそも寡黙なのは狙った設定でしょう。その分最後に、父親が森で息子にある教えを授けるシーンは効いてます。)
第一部はディオニシスがどのようして絶望から前向きになれるのか、ストーリーは直線的に進みますが、第二部のアメリカ編では、手術は成功するのかということに加えて、顔のドナーの家庭が描かれ、話が動き始めます。ドナーの妻は亡き夫の顔を持つディオニシスを目の前にして、どう反応するのか? (個人的には特にこの部分に関心を惹かれました。ここだけ発展させてもドラマになりそうです。)
第三部で故郷に帰り、ディオニシスの身体的状況は回復していきますが、その内面はむしろねじれていきます。連絡を絶っていた弟スタシスが突然再会を求めてきますが、レイシストと化した弟の人間憎悪も兄をどす黒い思いへと押しやっていきます。最後に、ディオニシスの憤怒はある人物に向かうのですが、どんな結末に至るのか、ここはハラハラしてしまいました(ミステリとは言えませんが)。
もうひとつ、ストーリー展開として読ませるのは、女医マニアとディオニシスとの関係です。SNSのやり取りだけだったにもかかわらず、熱心に手術を勧めたマニアが後半、主要人物としてたち現れ、帰国したディオニシスと初顔合わせするあたりからその心情が繊細に語られていきます。家族がありながら年下の青年に惹かれていく女医(決して美貌で凄腕のドクターXではなくて、ごく普通の目立たない中年女性)と、リアルな世界のやりとりに向き合うことになったディオニシスの心の揺れも読みどころです。(このへんもギリシャの読者に受けたのでしょう。)
安部公房『他人の顔』のような不条理劇とかシュールな物語ではなく、あくまでリアリズムが基調のお話です。
『他人の顔』では、事故で顔を失った化学者が終始一人称で、顔とはなにか?素顔と仮面の違いは?仮面と覆面の違いは?などと哲学談義を饒舌に続けるのに対し、この『失った顔』は主人公、母、女医の三人が交互に語る重層的な声の構造から成っています。さらには、主人公の内心の語りと並んで、彼のブログの文章も挿入されていき、これによって、同一人物の表裏のずれ、本音と建前の断層もまた明らかにされます。
もう一つ違いを言うと、『他人の顔』は着脱可能の新しい仮面を作ろうとする(なぜか元の顔を復元する気はさらさらない)のに対し、マラカテ『失った顔』は、あくまで自分の顔を取り戻したいのだけれど、皮膚が失われたためやむを得ず他人の顔を移植しようとする点が大きく異なります。一方が変身願望ならば、他方はあくまで原型の復元希望、と真逆の方向に向かっています。この、意に反して他人の顔を生涯付けざるを得なくなったことが、ディオニシスに数々の不幸を生むことになります。
もちろんジョン・ウー『フェイス/オフ』みたいなアクション大作ではありません。あるレビュアーは『ジョニーは戦場へ行った』を連想したといいます。が、反戦厭戦といった骨太の思想が一本貫いているというより、ひとつの事故を通じて医学倫理、薬害、SNSの功罪、家族の信頼、移民問題など、現代社会の抱える問題が次々に浮き彫りにされます。
さすがにミステリには分類できないでしょうが、人のアイデンティティーなるものが他人との関係の上に構築されているように見えて、実は大事な点が忘れがちだと気づかせてくれる、読み甲斐のある作品でした。
著者カテリナ・マラカテはアテネ生まれ。もともと薬剤師で、本作には日頃向き合っている薬害のような問題が込められているのでしょう。これまでに『誰も死にたくない』(2013)、『計画』(2016)の二作を発表しています。短編がいくつかあり、アンソロジー『王の陰で』(2017)にも作品を寄せているようです(ギリシャ人作家16名がスティーヴン・キングに捧げるオマージュ集)。
 キリアコス・アサナシアディス編『王の陰で』 キリアコス・アサナシアディス編『王の陰で』クリダリスモス社、2017。 【書名はもちろん「キング」をもじっているのでしょう。マラカテは「白い家」を寄せています。編者アサナシアディスはリレーミステリ『黙示録』(エッセイ第10回)でオドロドロしい血まみれパートを担当した作家です。《家族の絆》ヤナキや《一匹狼のイタリア派》ママルカスも書いてます。これはおもしろそう。】 |
◆欧米ミステリ中のギリシャ人(15)――パトリシア・ハイスミスのギリシャ人――
パトリシア・ハイスミスの作品を読んだのはギリシャ人作家の作品がきっかけでした。
エッセイ第4回に書きましたが、《リアリズムの極北》アンドレアス・アポストリディス(《六歌仙》No. 5)はハイスミスが大のお気に入りで、交換殺人を扱った自身の短編「ライヴ、または《立ち去る者たち》」(2007年)には『見知らぬ乗客』をギリシャ語訳した映像作家(つまりはアポストリディス本人がモデル)を登場させています。作品名の後半も『ヴェネツィアで消えた男』の原題Those Who Walk Away の借用です。ほかにも「イロディオ劇場のトム・リプリー」(2009年)という贋作も書いているし、なによりもリプリー・シリーズ五作をすべて翻訳しています。
 P. ハイスミス著、A. アポストリディス訳『見知らぬ乗客』 P. ハイスミス著、A. アポストリディス訳『見知らぬ乗客』ロエス社、2002。 |
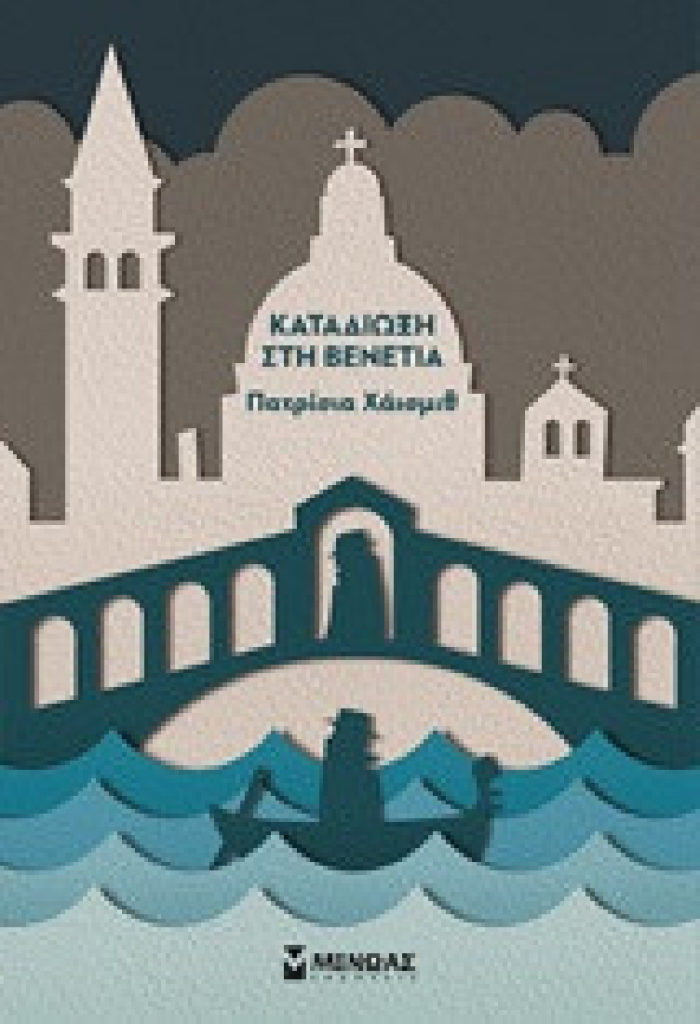 P. ハイスミス著、A. アポストリディス訳『ヴェネツィアで消えた男』 P. ハイスミス著、A. アポストリディス訳『ヴェネツィアで消えた男』ミノアス社、2017。 |
そんなわけで『見知らぬ乗客』『ヴェネツィアで消えた男』がおもしろかったので、勢いに乗って有名な『リプリー/太陽がいっぱい』(1955年)も読んでみました。
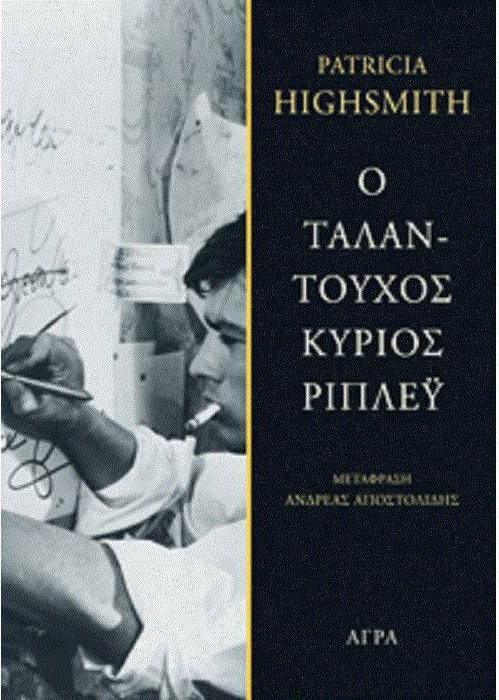 P. ハイスミス著、A. アポストリディス訳『才子リプリー』 P. ハイスミス著、A. アポストリディス訳『才子リプリー』アグラ社、2021。 |
アメリカ人青年トム・リプリーがさる金持ちに依頼され、ヨーロッパで遊び惚ける息子ディッキーを連れ戻しに行きます。優雅に暮らすドラ息子に嫉妬し、殺害してなり替わろうとするのですが……。なんとなく南仏のお話かと思っていたので(アラン・ドロンの影響?)、リプリーが折りに触れてはギリシャ旅行の夢を語るのが意外でした。「冬にはディッキーとヨットでギリシャの島めぐりをしよう」「ギリシャはどうしても見たい」「ガイドブックを買ってすでに日程も立て」「天井を見あげ船旅を想像した。ヴェニスからアドリア海をくだって
最後は念願叶って「蜃気楼などではない」アテネのピレウス港に船が入ります。腕組みで仁王立ちの警官隊を突破してリプリーは目指すクレタへ渡れるのか?(
リプリーがクレタでどう過ごしたのか、どうしても気になります。クノッソス宮殿は絶対訪れてますね。しかし、リプリーもの第二作『贋作』が発表されるのは何と15年後(作品内では5年後の設定ですが、そもそもシリーズ化を考えてたわけじゃないんでしょう)。
 P. ハイスミス著、A. アポストリディス訳『土の下のリプリー(贋作)』 P. ハイスミス著、A. アポストリディス訳『土の下のリプリー(贋作)』アグラ社、2006。 |
あんなに憧れていたギリシャへの言及もこの作品ではごくわずかです。伝説の画家が亡くなったというイカリア島(むかし翼を蝋で固めたイカロスが落ちた島)を訪れますが、数日滞在するだけ。アテネはというと、以前より近代化され綺麗になっており、リプリーが泊まるのはもちろん「一番高い」《グランド・ブルターニュ》です。ただし、ちょうど軍事独裁政権下で市民生活が締めつけられ、街角じゃブズキの音色も聞かれないんだ、と不満顔です(作品は1970年刊。軍事政権4年目のまさにリアルタイム)。奥さんのエロイーズの方がよほどギリシャ旅行を楽しんでおり、「船主ゼッポがよろしくって」などと手紙を送ってきます(このギリシャ人船長ゼッポは数行引用されるだけのチョイ役ですが、上記アポストリディスの贋作では強大な敵となってリプリーの前に立ちはだかります)。
なので、実質的な続編は(リプリーは出てないけど)1964年の『殺意の迷宮』(CWAシルバーダガー賞受賞作)だと私は勝手に思っています(それでも9年経ってますが)。嬉しいことにほぼ全編ギリシャが舞台です。
 P. ハイスミス著、A・アポストリディス訳『一月の二つの顔(殺意の迷宮)』 P. ハイスミス著、A・アポストリディス訳『一月の二つの顔(殺意の迷宮)』アグラ社、2013 |
ニューヨークで荒稼ぎしている詐欺師チェスターと妻コレットが身の危険を感じてアメリカを脱出、「いよいよギリシャね」「そう、ギリシャだ」と
ケチな夫妻は《グランド・ブルターニュ》ではなく、向かいの安ホテルに投宿。アクロポリス、スニオン岬のポセイドン神殿、と定番を回って、次はペロポネソス、クレタ島、ロドス島と繰り出す予定だったのですが、米捜査機関から依頼を受けたギリシャ人刑事ジョージ・M・パパノプロス(黒い顔に黒々とした濃い眉。半月刀を思わせる大ぶりな鼻に白髪混じりの黒い髪)にホテルへ押しかけられ、争いとなって殴り殺してしまいます。そこへ偶然来合わせた(!)米人青年ライダルが死体隠匿を手助けすることに(!?)。ライダルは法律一家の落ちこぼれで、一種の遊民ですが、
ライダル青年とチェスターの関係がなかなかに複雑です。ライダルは詐欺師オヤジが薄っぺらい犯罪者であることを見抜いているのですが、同時に亡き父に対する思慕めいた気持ちを抱いています。実は街角で偶然見かけたチェスターが父親にそっくりなので、のこのこ後をついて来たのでした。
かくして三人は一緒にクレタへ。
イラクリオン考古学博物館を見学(有名な牛跳び儀式の壁画とか蛇の女神像とか見たはず)した後、西の町ハニアへと逃亡を続けます。ただ、このハニアの描写が何とも残念で、沈滞の気が漂い、住民がどうやって生計を立てているのか訝しく思えるほどうら淋しく、町は美しさとは無縁……などと続き、引用するのも気が滅入りそうです。コレットと喧嘩したチェスターのむしゃくしゃした心情投影もあるのですが、そもそも天候が悪く波の高い冬にエーゲ海を楽しもうなんてのがよくない。春か夏に訪れれば、燦燦と注ぐ太陽の下でヴェネチアやトルコの歴史を刻む建物が堪能できたでしょうに。この十年後にはハニア国際空港も建設され、美しく活力に富む街になっています。マルカリス『筆頭株主』で大掛かりなシージャック事件が起きたのもここの沖合でした(エッセイ第14回)。
とはいえ、ハイスミスもハニアの港(ヴェネチアン・ポート)には惹かれたらしく、「カーブを描いて長々と続き、幅広い埠頭が海に向かって突き出している」などと記しています。町を抜けて港に出ると、ユニークなこの光景がいきなり目に入るのですが、長い腕で湾を抱え込むような堤防とその突端に立つ灯台の姿はちょっと忘れられません(映画化作品『ギリシャに消えた嘘』では一瞬映るだけ。残念)。
  |
ところで何がすごいと言って、ライダル青年の語学力です。二か月滞在しただけで
イラクリオンに引き返した後、三人はいよいよ昔々獣人ミノタウロスが閉じ込められた《迷宮》クノッソスへ向かいますが、ここでストーリーが大きく動きます。ライダルたちは無事アテネへ帰れるのか? そして肝心の刑事殺しの決着は?
鄙びたクレタのほかにも喧騒のアテネの雰囲気がたっぷり楽しめます。ライダルが頼りにする青年ニコス・カルフロスは街角でよく見かけるスポンジと宝くじ売りが生業(裏では偽造パスポートなんかも調達してますが)。このニコスと気さくな妻アンナ(大の英国びいき)とはかなり好意的に描かれています。
食事のシーンはあまり出てきませんが、厚切りパンにのせた熱々のヤギ肉とレツィーナ酒はおいしそう。ウーゾ酒を飲むシーンはやたらと登場します。
ストーリーの構図としては、あいかわらず強迫観念にとらわれた男たちの戦いです。ヒロインを交えた三角関係に見えますが、コレットの心理はろくに描写されません。というか、自分が男たちの不和の原因になることを知ってか知らずか、無邪気に如才なくふるまい引っ掻き回すだけの存在です。二人の男たちが憎み合いながら同時に惹かれ合い、互いに取り込まれていくドロドロが、『見知らぬ乗客』や『ヴェネツィアに消えた男』同様に、やっぱりハイスミス節です。相手の中に自分と同質の部分を見て嫌悪感を抱きながらも、逃れられずあがき続ける男たち。年齢差を考えるとオイディプスと父ライオス王の関係を思わせる部分もありそうです(『見知らぬ乗客』では主人公ガイが宿敵ブルーノについて「ふたりはどっちも、相手から見ればそうなりたくないような人間なのだ。つまり放棄した自分自身なのだ。だから憎らしいと思っているはずなのに、実際は愛しているのかも知れない」と心中を明かします)。
ところで、チェスターはアテネで時間つぶしに日本映画(ギリシャ語字幕つき)を観ています。題名も内容も書かれていませんが、1964年頃と言えば、黒澤明「天国と地獄」でしょうかね?
■パトリシア・ハイスミスのギリシャ語講座■ ギリシャ語が話せるのか? と港の検問で訊かれたライダルが、 |
| 橘 孝司(たちばな たかし) |
|---|
|
台湾在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっと紹介するのがライフワーク。現代ギリシャの幻想文学・一般小説も好きです。 昔買ったまま読みもせず本棚の一部と化していた文庫本を、五十年後に《大人読み》。エレベーターに閉じ込められた男の時限サスペンスだとずっと思ってたのに、一触即発の火種を抱えたあぶないカップルが次々に出てくるノワール群像劇でした。映画のようなカメラアイの切替えがスタイリッシュ。思いもよらぬところから主役が告発される皮肉も効いてます。映画は見てないけどマイルス・デイビスのクールなメロディが頭の中を巡るノエル・カレフ『死刑台のエレベーター』。最近新装版が出ました。 【子供の頃は全く気になりませんでしたが(カタカナ名はみんな外国人)、この姓はスラブ系ですね。ブルガリア生まれだそうです。】 |
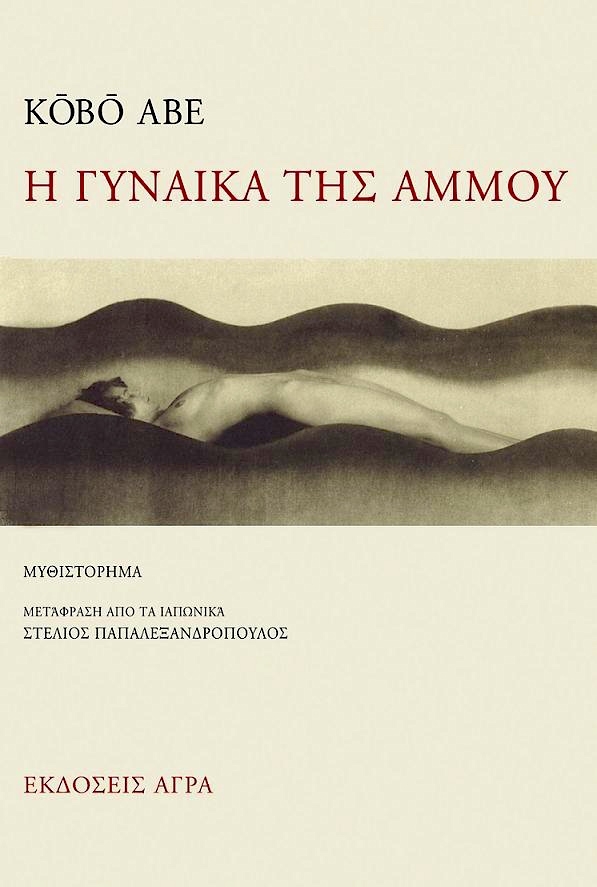 安部公房著、ステリオス・パパレクサンドロプロス訳『砂の女』 安部公房著、ステリオス・パパレクサンドロプロス訳『砂の女』アグラ社、2004。 【『他人の顔』はギリシャ語訳されていないようですが、『砂の女』は日本語からの直接訳(こういう試みはまだまだ少ない)があります。アテネ大学神学部で、日本を含め東洋の宗教を研究するステリオス・パパレクサンドロプロス教授の労作です。】 |
|
■ヴィゴ・モーテンセン、キルステン・ダンスト、オスカー・アイザック共演!映画『ギリシャに消えた嘘』予告編■ 【『殺意の迷宮』を映画化した『ギリシャに消えた嘘』。2014年の作品ですが、小説同様1960年代初めの設定になっています。クレタの田舎道を走るバスがいかにも時代っぽい。アクロポリスにはじまり、ほとんどギリシャ国内で話が展開しますが、最後はイスタンブールでのアクションになります(ここは映画オリジナル)。 製作が始まった2010年当時はギリシャ経済危機で、イスタンブールとイギリスでのみ撮影を計画していましたが、結局クレタ島で三週間、アテネで四日という強硬ロケを行ったそうです。ただし、危機のおかげというか、全国ストのためクノッソス宮殿が閉鎖されており、参観者なしでゆっくり撮影ができたとか。パルテノン神殿も本来は立ち入り禁止なのに、主役二人は堂々と入っています。 ハイスミスが陰鬱に描いたハニアですが、ライダル役のオスカー・アイザックはこの町の雰囲気に惚れてしまい、ロケ期間中母親を招くほどだった、という話を聞くと嬉しいです。】 |
■「ギリシャに消えた嘘」のギリシャ語講座■Μπορείτε να μου δώσετε τα γυαλάκια σας;(ボリーテ・ナ・ム・ドーセテ・タ・ヤラーキャ・サス?) |