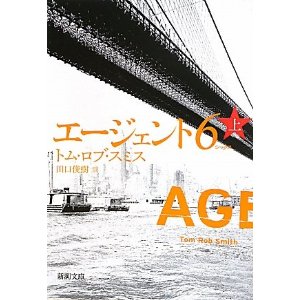 田口俊樹
田口俊樹
「古いジョークが最高のジョークなんだよ。だから残るんだよ」
今訳している本で、ある男がそんなことを言います。なるほどと思い、自分が覚えている一番古いジョークを思い出しました。
もう半世紀近くもまえの話。中学校にはいった頃でしょうか、早世した父親から聞いたジョークです。
アメリカのサラリーをもらい、イギリスの家に住み、日本人の奥さんと結婚して中華料理を食べるのが男の夢。中国のサラリーをもらい、日本の家に住み、アメリカ人の奥さんをもらい、イギリスの料理を食べるのが男の悪夢……
いわゆるエスニックジョークというやつですね。そんな古いことを覚えていたのは、その後二十年ほどくだって高校で英語の教員をしていた頃、親しくしていたオーストラリア人講師に同じジョークを言われて、どこかで聞いたことがあるな……ってな感じで思い出したからです。父親に最初に聞いたときには、実のところ、よくわからないなりに笑ったほうがいいのだろうと思い、オーストラリア人に言われたときには、なんか馬鹿笑いした記憶があります。どちらかと言えば、にやりとする類いのジョークだと思うけど、英語で言われると、ちゃんと理解できたことを示したくて、過剰に反応したんですね。われわれの世代の悲しい性です。
ともあれ、このジョーク。今のご時勢に鑑みてどんなもんでしょう? 基本的なお国柄はそう大きく変わっていなくても、つまり、パンチラインはわからなくはなくとも、今の私には笑えるほど可笑しくはない。やっぱりジョークにも賞味期限というものがある? 古いジョークが最高のジョークとは言えない?
いやいや、ちがいますね。そういうことじゃなくて、やはり肝心なのはそこに発見すべきものがあるかないかということですよね。まあ、笑いだけじゃなくて、人生のたいていのことがそうですが。
ヘミングウェイの短篇に「何を見ても何かを思い出す」というのがありますが、近頃、そういうことが多くて、冒頭の台詞に接し、最初に書いたことを思い出したわけです。でも、このふたつの思い出、ともにとても懐かしかったです。思わず頬がゆるんでしまうようなノスタルジーのやさしさ。これまた歳をとってようやく発見できることのひとつかもしれません。
(たぐちとしき:ローレンス・ブロックのマット・スカダー・シリーズ、バーニイ・ローデンバー・シリーズを手がける。趣味は競馬とパチンコ)
 横山啓明
横山啓明
機会があって、ン十年前に読んでさっぱり意味のわからなかった
文章を再読することになった。あの時は、おれは頭が悪くて
理解できないんだと悲しい思いをした。
さて、今読んでみると……。
なんだ翻訳がひどいだけじゃん。
昔つまずいた冒頭の文章、原文に当たってみると、
関係代名詞以下が長々と続いている。
これをひっくり返して訳しているので、いきなり「彼ら」とか「それら」
などという代名詞が出てくる。「彼ら」って誰? 「それら」ってなに?
これじゃあ、理解できないのも当たり前。
しかも代名詞を全部訳しちゃっている。
「したがってこれらは……彼に対して……それらが実際に彼にとって……
それらは彼に払い戻し……」
これは別のところからとった一文。一文でこれ。
おれの頭が悪かったんじゃないんですね。
(よこやまひろあき:AB型のふたご座。音楽を聴きながらのジョギングが日課。主な訳書:ペレケーノス『夜は終わらない』、ダニング『愛書家の死』ゾウハー『ベルリン・コンスピラシー』アントニィ『ベヴァリー・クラブ』ラフ『バッド・モンキーズ』など。ツイッターアカウント@maddisco)
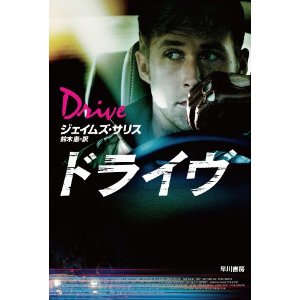 鈴木恵
鈴木恵
今回は旅先からお送りしています(この原稿のことをすっかり忘れて旅に出てしまい、あわてて車中からケータイ送稿してる、なんてことは決してありません)。翻訳者仲間4人と宮城県で温泉プラス山登りののち、これから気仙沼に向かうところ。旅のお供は缶ビールと魚肉ソーセージ、それにアラン・ブラッドリー『パイは小さな秘密を運ぶ』。では、失礼して続きをば。
(すずきめぐみ:文芸翻訳者・馬券研究家。最近の主な訳書:サリス『ドライヴ』 ウェイト『生、なお恐るべし』など。 最近の主な馬券:なし orz。ツイッターアカウント@FukigenM)
 白石朗
白石朗
調べ物のかなりの部分をウェブに頼るようになって久しいが、それでも新しい紙の辞書が出ると気になる。最近ではなんといっても三省堂の『犯罪・捜査の英語辞典』。編著者の山田政美・田中芳文両氏は、『英和ブランド名辞典』(研究社)でもおなじみ。序文にはエド・マクベインやパトリシア・コーンウェル、ジェイムズ・マクルーアにジョゼフ・ウォンボー、メグ・キャボットといった作家の名前があるほか、編著者両氏が過去に研究助成費出版(ってなに?)で『エド・マクベイン英語表現辞典』『パトリシア・コーンウェル英語表現辞典』を出版していたことがわかって驚かされた(どちらも市販されていないようで残念)。
収録語数は3000と少なく感じられる方もおられようが、言葉の由来の説明もおりおりにちりばめられていて読むと楽しいし、日本語索引がついているのもありがたく、思わぬところでミステリ作家に出会えもする。たとえば hugger-mugger の項目では、ロバート・B・パーカー『ハガー・マガーを守れ』の題名がある。本書での語義は、『ランダムハウス英語辞典[第二版]』の同項目の3「《米俗》女を抱きかかえるようにして金を奪う泥棒」とほぼ同様ながら、微妙にちがう。なぜそうなったのか興味もわきますが、どんなふうに微妙かは各自確かめてください。
(しらいしろう:1959年の亥年生まれ。進行する老眼に鞭打って、いまなおワープロソフト「松」でキング、グリシャム、デミル等の作品を翻訳。最新訳書はヒル『ホーンズ—角—』、デミル『ゲートハウス』、キング『アンダー・ザ・ドーム』。ツイッターアカウント@R_SRIS)
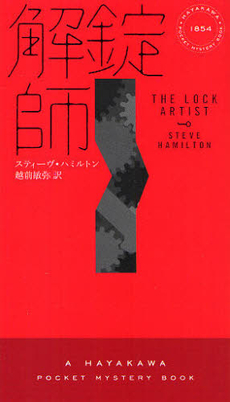 越前敏弥
越前敏弥
シナリオライターの中島丈博の自伝的作品である映画〈祭りの準備〉で、主人公の江藤潤(若き日の中島)が「新藤さんっちゅう、ものすごくえらいシナリオライターの先生が……と言っとるんじゃ」と言う台詞がある。この作品の舞台は1960年代だから、いまから半世紀前に新藤兼人はすでにそういう存在だったわけだ。まさに巨星墜つ。
その新藤兼人の代表作をあげるとき、〈裸の島〉とか〈午後の遺言状〉とか、監督作品がまず出てくるのは当然かもしれないが、シナリオライターとしての功績も同等かそれ以上に称えたい。自分にとっては、何よりも大岡昇平の原作を映画化した〈事件〉の印象が最も強く残っている。このシナリオはペラ600枚以上に及び、そのまま映画にしたら5〜6時間になるはずだったが、野村芳太郎監督はほぼすべてのシーンを撮った上で、半分以下の長さに編集したものを最終バージョンとした。事件にかかわるひとりひとりのディテールが熱く息づいていた長大なシナリオも、大胆な編集を経て切れ味鋭く人間の業に迫った完成版の映画も、どちらも完璧な作品で(矛盾するようだが、そうとしか言いようがない)、まったく甲乙つけがたかったと記憶している。近くおこなわれるであろう回顧企画では、ぜひその両方を公開してもらいたいものだ。
(えちぜんとしや:1961年生。おもな訳書に『解錠師』『夜の真義を』『Yの悲劇』『ダ・ヴィンチ・コード』など。趣味は映画館めぐり、ラーメン屋めぐり、マッサージ屋めぐり、スカートめくり[冗談、冗談]。ツイッターアカウント@t_echizen。公式ブログ「翻訳百景」 )
 加賀山卓朗
加賀山卓朗
自宅療養していた高齢のおじが亡くなったので、田舎にとんぼ返りしてきた。たとえ穏やかな老衰でも、家で人が亡くなるとたいへんなんですね。峠の向こうから警察がやってきて、検死はもちろん、その日の家族全員の行動とか、預金残高とか、何から何まで調べたのだとか。部屋のゴミ箱のなかもあらため、故人に食べさせたナスの大きさまで訊いていったそうです。立場はわからなくもないけれど、なんだかね……。
ぜったい家で死んだらいけんで、というのが地元の意見集約でした。
(かがやまたくろう:ロバート・B・パーカー、デニス・ルヘイン、ジェイムズ・カルロス・ブレイク、ジョン・ル・カレなどを翻訳。運動は山歩きとテニス)
 上條ひろみ
上條ひろみ
『古書の来歴』で第二回翻訳ミステリー大賞に輝いたジェラルディン・ブルックスのデビュー作『灰色の季節をこえて』は、十七世紀のイギリスで黒死病という理不尽な災いに襲われた小さな村の人びとが、自分を失いかけ、さまざまなものに救いを求めながら苦悩する物語。死と暴力がふんだんに出てくる暗い話なのにとても読みやすく、つらい現実に立ち向かう若きヒロインの葛藤がリアルというか、現代人に近い感覚なので、すんなり感情移入できる。読みながら、ああ、ここに「JIN−仁—」の南方先生がタイムスリップしてきてくれたら、と何度思ったことか。けなげで芯の強いヒロインのアンナが「JIN」の咲さんに思えてくる。
当時の生活の様子が仔細に描かれているのも興味深く、厳しい環境で必死に生きる人びとの姿は臨場感たっぷり。デビュー作でもやっぱりブルックスはうまいなあ。ミステリーの範疇にはいるかどうかわからないけど、閉ざされた環境のなかで、人びとがどうにもならない運命に翻弄されるという設定は、小野不由美の『屍鬼』やスティーヴン・キングの『アンダー・ザ・ドーム』を思わせる。
(かみじょうひろみ:神奈川県生まれ。ジョアン・フルークの〈お菓子探偵ハンナ・シリーズ〉(ヴィレッジブックス)、カレン・マキナニーの〈朝食のおいしいB&Bシリーズ〉(武田ランダムハウスジャパン)などを翻訳。趣味は読書とお菓子作り)