みなさんこんばんは。第37回のミステリアス・シネマ・クラブです。このコラムではいわゆる「探偵映画」「犯罪映画」だけではなく「秘密」や「謎」の要素があるすべての映画をミステリ(アスな)映画と位置付けてご案内しております。
通常通りとはいかずとも、ある程度コンスタントに映画館での新作上映が続く状況にだいぶ戻ってきましたね。諸々の状況を考えると手放しに喜べずとも、まあ嬉しいことではあるんですが、なんだか以前のようには劇場に通えなくなっている私がいます。やっぱりマスクかけて長時間はしんどいし……メガネ曇ってくるし……どうしても自宅での鑑賞メインになってしまうのは、この1年余の諸々で身体的にも変化しちゃったからなあ、などと思う今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、そんな私が今「劇場公開になろうが配信オンリーのリリースになろうが、とにかく早く見たい!」と騒いでいるのが、先日HBO Maxでリリースされたスティーヴン・ソダーバーグの新作『No Sudden Move』(タイトルからして素敵)。
私は2009年以降のソダーバーグ監督作品のほぼすべてが大好きなのでかなり贔屓目に見ているところもあるのですが、この人ほど「映画館ではない場所で新作映画がかかる状況」を10年以上前から考えてきて、既存の配給システムと戦ってきた人はいないといってもよいでしょう。ありとあらゆる失敗と時々の成功を重ねつつ、いつもと同じように見えても常に新しいことをやり続けるそのスタイルには毎回感動。普通のクリエイターとは見ているレイヤーが全然違う監督だよなあ、と思っています。
ということで今回は、2019年のベスト映画の1本として強く心に刻まれているソダーバーグ監督×Netflixの『ハイ・フライング・バード-目指せバスケの頂点-』のご紹介を。とにかく語りがなめらかで省略が極まりすぎていて、一見しただけだと凄さがわかりにくいレベルにまで達してしまってるのですが、個人的にこれ、2010年代を代表する傑作だと思っています。
■『ハイ・フライング・バード-目指せバスケの頂点-』(High Flying Bird)
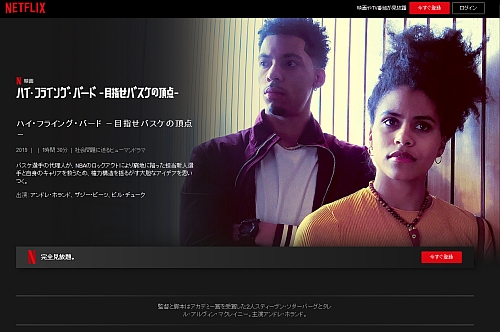
あらすじ:長年、バスケットボールプレイヤーのエージェントを続けているレイ・バーク(アンドレ・ホランド)。しかし、彼と彼のクライアントを取り巻く現状はなかなか厳しい。今、資本主義構造のトップに君臨するNBAという組織は、ロックアウト(労使交渉が決裂して、オーナー側がストライキを強行、選手はアリーナからも練習場からも締め出され「何もできない状態」になる)によって彼らを潰そうとしている。担当の新人選手も、レイのキャリアも崖っぷち。しかし冷静なレイには権力構造を揺るがす大胆なアイデアがあった……
(※今回は、あまりにも私の好みのど真ん中の作品すぎて冷静さに欠けること甚だしいと思いますので、その前提でお読みください!)
「意味のないものが一切存在してない映画」という言葉が思い浮かんだ作品です。何しろ劇場公開なしのNetflixオリジナル作品であることにまで意味がある!最初から最後まで、ひとときたりとも停滞しない物語のなかに「資本主義(≒アメリカ)というシステム」への膨大なコメンタリーが収められた、実に理知的で美しいストラクチャーを持った一作です。
先にいっておくと、この映画に「スポーツのドラマ性」あるいは「痛快な逆転劇」の要素を求めると肩透かしなことこのうえないでしょう。あくまでもこれはスポーツビジネスを「一瞬だけでも(むしろそこが前提)」動かせるのか?動かせる可能性が生まれたら、何がどうなるのか?というところだけをただただ冷静に見つめる話なのです。
通常のスポーツものであれば「試合」や「人間模様」における感動を中心に置くことは避けられないわけですが(それが求められているわけですし、私自身そういう映画も好きですよ!)、そもそもこの映画には「スポーツが呼び起こす感動」や心地よい「連帯」を見せるシーンが一切ありません。唯一の試合シーンでさえタブレット(スマホ)内で処理してしまう潔さ。ガチガチに固められたスポーツビジネス、資本家のためのシステムをクールな主人公の一手で破壊できるかもしれない……なんて感動的な幻想も、もはやここにはありません。
それでも決して露悪的にならない清潔さと人間への信頼を保っているのがこの作品の凄いところ。映画の底に「壊せないシステムが存在する現実」の重さとほぼ同じ比重で、人間は変えることをやめないし、人間自身も変わるのだ、ということへの信頼が感じられるのが、私はとても好きでした。
盤上の駒が、ゲームを一瞬でもスナッチすることは可能なのか? という問いを通じて、現代に生きるものとしての拳の固め方を静かに熱く教唆する物語以外にも、編集や撮影や俳優陣など好きなところを語り始めたらキリがありませんが……最後にもうひとつだけ、この作品の素敵なところを。当たり前のように多様かつ多面的な人物が描かれているのですが、セクシュアリティ/ジェンダー/人種に関する部分がいちいち素晴らしいんですよ!あらゆるフィクションでセクシュアリティの扱いや言葉の選び方、性別や人種の表現がこれくらいの温度であってほしいと願っています。
■よろしければ、こちらも/『ホワイト・ボイス』
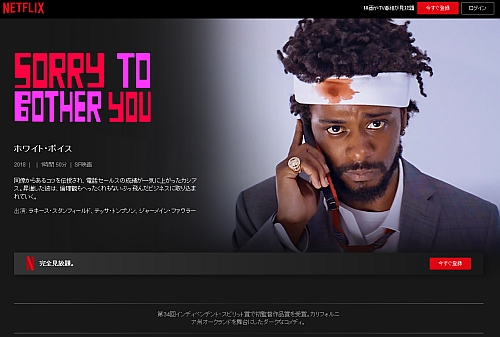
今回併せておすすめしたいのはブーツ・ライリー監督の『ホワイト・ボイス(原題:Sorry to Bother You)』(一時期Amazon Prime Videoのみで配信されていたのですが、現在はNetflixのみでの配信に移行しました)。こちらは傑作というよりも怪作にして快作……?といった印象の作品なのですが、凄い方向から攻め込む労働争議映画として私はかなり気に入っています。
叔父の家の車庫で暮らす黒人の若者がなんとかかんとか滑り込んだのがテレアポの仕事、「そのアクセントじゃ売れないぞ」と仲間に指摘されて白人特有のアクセントを完璧にコピーしたとたん、瞬く間に営業成績はトップに……という途中までのあらすじから、話は予想もつかない方向へと振り切れていきます。トンデモミステリ愛好家の人をときめかせる種類の変な映画、かもしれません。
しかしよく見ると、無限に再生産される搾取構造で笑わせながらも「現代の資本主義ヤバいとこまできてるぞ?本当にこれを望んでる連中はいるぞ?」とゾッとさせる、いたってまっとうな風刺映画なんですよね、これ。実は変な映画としても非常にクレバーな作り方で「んな無茶な」の方向にいきなり吹っ飛ぶのでなく現実と非現実、複数の次元を同一次元に描くある種のマジックリアリズム的な話法が最初から採られていて「寓話としての真実味」が終始担保されているところも、なかなか巧みです。
そして私は、アンドレ・ホランドと並んで大好きな俳優の一人がこの映画の主人公カシアス役、ラキース・スタンフィールドなんですね。いつも訝しげに目を細めて首を傾げては「なんか変な気がするが…」と「まあこんなもんか…」を往復しているラキースの浮遊感が絶妙な形でハマったダークコメディになっています。とんでもないサタイアを成立させるためのミュージックビデオ的なアプローチも効果的で、監督自身がフロントマンを務めるThe Coupの音楽も最高。でも、すごく変な映画ではあるので、人を選んでおすすめします(笑)。
配信限定でこうした挑戦的な映画が見られる時代であることの喜びと、素晴らしい作品に出会えたとき抱く「映画館で見たかったなー」という感情と、こうした良作がほとんど宣伝されず好事家の間でだけ評判になる現状に対する「それはどうなのかなー」という気持ちと……全部まとめて噛みしめながら、それでは今宵はこのあたりで。また次回のミステリアス・シネマ・クラブでお会いしましょう。
| 今野芙実(こんの ふみ) |
|---|
 webマガジン「花園Magazine」編集スタッフ&ライター。2017年4月から東京を離れ、鹿児島で観たり聴いたり読んだり書いたりしています。映画と小説と日々の暮らしについてつぶやくのが好きなインターネットの人。 webマガジン「花園Magazine」編集スタッフ&ライター。2017年4月から東京を離れ、鹿児島で観たり聴いたり読んだり書いたりしています。映画と小説と日々の暮らしについてつぶやくのが好きなインターネットの人。twitterアカウントは vertigo(@vertigonote)です。 |