年寄りの冷や水というか、いい歳をしていきなり管楽器に手を出した話は、すでにこの連載でも書いたことと思う。フリューゲルホルンから入って、同類のコルネット、トランペット。つまり金管楽器である。指で操作する部分が3つのピストンのみなので、出音の大半を口もとでコントロールすることになるという、きわめて厄介な楽器だ。その難しさゆえにかえって、すっかりのめり込んでしまっているのだけど。
この楽器の世界で神的存在といったら、言うまでもなくマイルス・デイヴィスだろう。天才的なトランペット奏者というだけにとどまらず、ここ半世紀の音楽界においてつねに新たな領域に挑んできた最高のクリエイターだ。にしても小生、チェット・ベイカー大先生を敬愛するあまり、この神様のことを少々おざなりにしてきたことは否めなくて、そんな負い目もあってか、先だって日本公開されたドキュメンタリー映画『マイルス・デイヴィス クールの誕生(Miles Davis: Birth of the Cool)』(2019年)には、さっそく駆けつけてみたのだった。
あらためて知ったのが、意外なことにマイルスは、歯科医の息子という富裕で恵まれた家庭環境だったということ。幼くしてトランペットを親から授かり、15歳ですでにクラブで演奏し始めている。中退ながらもジュリアード音楽院にも通い、予想外にたいへん勉強熱心で、自ら進んで音楽理論を徹底的に頭に叩き込んでいったようだ。何となく叩き上げというか、そんなイメージを勝手に抱いていたのだけど。まあ、神様の生涯について詳しく知りたい向きには、『マイルス・デイビス自叙伝(MILES The Autobiography)』(1989年)なんて本が邦訳紹介されているので、そちらを参照していただくとして、今回はとにかく、マイルスそしてジャズの話題であります。
そんなわけで、あらためてマイルスの偉大さに感じ入ってしまい、映画『MILES AHEAD/マイルス・デイヴィス空白の5年間(Miles Ahead)』(2015年)なんかも拝謁して、二目惚れ的にますます神様に惹かれていったわけなのだけど、そこでふと脳裡に甦ったのが、この文章。
マイルスがあまりに美しい演奏をしたんで、おれは椅子から転げ落ちそうになった、その時、おれは目を閉じて、ゆっくり演奏しはじめた。空を飛んでるみたいだった――
稀代の実験的小説『石蹴り遊び(Rayuela)』(1960年)で知られるアルゼンチンの作家、フリオ・コルタサルの中篇小説「追い求める男(El perseguidor)」の作中にある印象的な一節だ。
コルタサルは、『Los premios』(1960年)や前出の『石蹴り遊び』といった長篇小説で英語圏でも名声を確立した作家ではあるけれど、どちらかというと幻想的な短篇小説の名手として高く評価されている。1959年の短篇集『秘密の武器(Las armas secretas)』には、ミケランジェロ・アントニオーニ監督の初英語作品となる映画『欲望(Blow-Up)』(1966年)の原案となったことで知られる「悪魔の涎(Las babas del diablo)」など、現実と非現実が交錯する名篇が収録されているけれども、この「追い求める男」だけは、ちょいと勝手が違う。それまでの幻想性を強く帯びたものとは異なる新たな創作の方向性として、より身近な題材と自身の嗜好を反映して書いたものだった。そう、大好きなジャズを題材に。主人公はジャズ・サックス奏者。若きマイルスが崇め街じゅうを探し回ったという“ビバップの父”チャーリー・パーカー(バード)をモデルとし、形式に縛られないジャズの即興音楽(インプロヴィゼーション)のように、それでいて生々しくリアルな人間を言語化しようとした野心作だった。
そして、ぼく同様にコルタサルのこの一文に囚われた作家がいた。フランスの作家フランソワ・ジョリ。フランス推理小説大賞とロカール賞を受賞した『鮮血の音符(Notes de sang)』(1993年)という彼のハードボイルド小説には、エピグラフとしてこの一節が引用されていたのだ。
かつてのアルジェリア戦争下で反OAS(秘密軍事組織)のコマンドだった自動車修理工場の経営者、ピエール・キュルベイエを主人公とするシリーズものの第3作にあたり、エピグラフにマイルスを登場させただけのことはあって、リヨン郊外のヴィエンヌの町で毎年開催されるジャズ・フェスティバルが舞台となっている。
冒頭、降りやまぬ驟雨にアート・ブレイキー&ザ・ジャズメッセンジャーズが早々にステージから引き上げてしまった後、即興で穴埋めをしようとトランペット奏者ディジー・ガレスピーが登場する場面で、物語は幕を開ける。
このフェスティバルに毎年欠かさず参加するほどのジャズ狂であるキュルベイエは、幕開き早々、殺人の容疑で逮捕されてしまう。《リヨン革命組織(ORL)》なるテロリスト組織の残党だった男《アルゴス》が演奏会場の一角で殺害され、その遺留品からキュルベイエの名前が見つかったからだ。どうやら組織の下っ端であるこの男が始末されたのは、極刑を言い渡されて投獄されている指導者たち《説教屋》と《使徒》以外に秘匿されている首謀者格の存在があって、その正体暴露へとつながる手掛かりを消すためだったと考えられていた。キュルベイエの名は、《アルゴス》のレコード・コレクションであるアルバム・ジャケットに《説教屋》の名前とともに記されていたとして、ORLとの関連も疑われ詰問されるが、もちろん身に憶えのないキュルベイエは、地元民でありフェスティバルにも通じているということから捜査への協力を約束させられて一時釈放される。《説教屋》はじつは高校時代の先輩にあたり、キュルベイエとも接触があったのだった。調査の過程でキュルベイエはかつての教師や友人たちのもとを訪ねて、過去の記憶を掘り下げていくことになるが、その後、主人公を待ち受けるのは、とんでもない窮地だった――。
そう、彼を待ち受けていたのは、凄まじいまでの拷問。最近のミステリー作品だと、アンデシュ・ルースルンド&ベリエ・ヘルストレムのグレーンス警部シリーズ第7作『三分間の空隙(Tre Minuter)』(2016年)での、コロンビアのゲリラ組織に囚われた合衆国下院議長への残虐極まりない拷問シーンを想起させるほど……いや凌駕するほどの暴行を受けることになる。
シリーズは、おそらくジーン・ヴィンセントのヒット曲「ビー・バップ・ア・ルーラ(Be-Bop-A-Lula)」と掛けたタイトルであろう第1作『Be Bop a Lola』(1989年)、第2作『L’homme au megot』(1990年)、そして、第4作『Le grand blanc』(1997年)まで、全4作発表されている。本作を単独で読んだだけでは少々わかりづらい箇所もあるようだ。
というのも、未読ながら類推するに、キュルベイエはどうやら第1作において最愛の妻ローラを失っており、その喪失の苦しみに苛まれ、本作でもその想いを引きずっている。作者のジョリの経歴とも重なるが、“反OAS”の狙撃手だったという過去を持ち、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を抱えているというあたりの背景が、本作同様に過去2作のストーリーにも深く関わっているようなのだ。
また、ロバート・B・パーカーの探偵スペンサー・シリーズや、アンドリュー・ヴァクスの探偵バーク・シリーズよろしく、自警団的な“ファミリー”がここには登場する。彼に捜査協力を強いた友人でもある警視マルダンをはじめ、彼と因縁の深い人物たちが、ジャズ・フェスティバルでの殺人事件をきっかけに登場することになる。本作に続く第4作も同様で、展開こそ冒険アクション的な要素も色濃いが、本作にも登場する武器商人サリアンの愛娘マリアンがマフィアの囚われの身となり、キュルベイエが救出に向かうといったストーリーだ。
このシリーズを語るうえでは、どうしたってアルジェリア戦争についての解説が必要となりそうだ。ヨーロッパ史に詳しい方は読み飛ばしていただくとして、つまりは、フランスの支配に対する当時フランス領だったアルジェリアの独立戦争のことである。1954年の民族解放戦線(FLN)によるテロ行為によって始まり1962年に停戦に至った。アルジェリア地域内に住むコロン(もしくはピエノワール)と呼ばれるフランス人と、ベルベル人やアラブ系住民などの先住民(アンディジェーヌ)との民族紛争でもあり、親仏派と反仏派の先住民同士の紛争でもあった。
キュルベイエが敵対していたOAS(秘密軍事組織)は、アルジェリア戦争末期の1961年に結成された組織で、アルジェリアの独立に猛反発し、就任後に路線転換したシャルル・ド・ゴール大統領をはじめ、それを容認しようとする講和派の政治家を標的としたテロを頻発させた。1962年にエビアン協定によってアルジェリア独立が承認されてからもなお、OASらのテロ活動は続くことになる。
海外ミステリー好きならば、アルジェリア戦争と聞けばすぐに思い起こすあの名作スリラーは、まさにそのあたりの時期をテーマとしていた。そう、フレデリック・フォーサイスの小説デビュー作にして代表作『ジャッカルの日(The Day of the Jackal)』(1971年)。これは、ド・ゴール大統領がアルジェリア戦争終結を宣言した後、なお体制転覆をもくろむOASが、外部のスナイパーに大統領暗殺を依頼するというものだった。アルジェリア戦争の爪痕というのは、本作での極右組織《リヨン革命組織(ORL)》のテロ活動しかりで、戦後もなお連綿と遺されていたということだろう。
余談だけれども、コロナ禍のなか、『ペスト(La Peste)』(1947年)が再注目されているフランスの小説家アルベール・カミュ。彼もまたアルジェリア戦争に関わりがあった。
戦争勃発当時、民族解放戦線のテロリズムを批判すると同時にフランス軍の武力弾圧も告発。どちらの民族にも権利を保証するような中立曖昧な態度を表明していたため、旗幟鮮明にしない態度が非難され、極右の植民地解放主義勢力によるデモによって講演会などを妨害された。以後、アルジェリア戦争問題については一切発言しないようになったという。そのあたりの事情は、謎めいた交通事故死(暗殺説もある)後30年以上を経て発表され、世界的ベストセラーとなった未完の自伝的小説『最初の人間(Le premier homme)』(1994年)に詳しい。同作は、2011年に名匠ジャンニ・アメリオ監督によって映画化もされている。
さてさて、そんな生々しい史実を背景としたキャラクターや事件の設定が、『鮮血の音符』のひとつの読みどころではあるのだけれど、もう一つの魅力は音楽。全篇通して伝わってくる、ジャズ・ライヴの臨場感だろう。
スコット・ハミルトン、ブランフォード・マルサリス、キャブ・キャロウェイ、スタン・ゲッツ、ジャック・ディジョネット、ハービー・ハンコック、ボブ・バーグ、マイク・スターンといった、名うてのジャズ奏者たちに言及し、統合失調症を患うトランペット奏者トム・ハレルが1988年に死去したチェット・ベイカーを悼んでクインテットを結成したとか、1965年にはフランスでの歴史的コンサートでジョン・コルトレーンが不動のカルテットを誕生させたとか、ジャズ史も盛り込むなど、ジャズ愛に充ち溢れている。
キュルベイエのコレクションから流出したと思われる署名入りジャケット3枚も、オーネット・コールマンの『からっぽのたこつぼ壕(The Empty Foxhole)』(1966年)、セシル・テイラーの『それは何なのだ』(『Look Ahead!』〔1959年、仏盤は1967年〕の意訳だろうか)、アルバート・アイラ―の『幽霊(Ghosts)』(1965年)という、みごとにフリー・ジャズの演者ばかりで通好みのセレクト。
ジャズにとどまらず、ブラジルからジルベルト・ジル&ジョルジュ・ベンジョールがフェスに参加。武器商人の裕福な邸宅を訪ねるシーンでは亡き妻ローラを思い、映画『上流社会(High Society)』(1956年)でビング・クロスビーが歌う挿入歌「愛しのサマンサ(I Love You, Samantha)」のメロディーを、キュルベイエが口笛で吹く。囚われの身にあっても、セロニアス・モンクの「ベンシャ・スウィング(Bemsha Swing)」をやはり口笛で吹こうとする。かように音楽に充ち満ちた、異色のフレンチ・ハードボイルドなのである。
マイルス・デイヴィスに話を戻すけれど、これまた海外ミステリー好きにしてみれば、どうしたってルイ・マル監督のデビュー作にしてヌーヴェル・ヴァーグの代表作『死刑台のエレベーター(Ascenseur pour l’echafaud)』(1958年)を思い出さずにはいられないだろう。編集された画像を観ながらコンボでの即興演奏(インプロヴィゼーション)で、サウンドトラックを完成させたということで話題となり、以降、ジャズの世界観を取り込んだヌーヴェル・ヴァーグの代表的作品として映画の評価を高めることにつながった。
1956年に発表されたノエル・カレフによる同名の原作小説はというと、じつは映画版の比較的ストレートな展開とは異なり、かなり複雑な構造で描かれている。登場人物それぞれが、自分の行動によってどのような事態が生じるかを認識しないまま、ひとつの大きな悲劇を創り上げていくという、きわめて稀な着想の作品だった(小森収氏による文庫解説参照)。しかしながら、原作には、まったくもってジャズどころか音楽のかけらも記述がないので、マイルスの起用は、あくまでもルイ・マルが作品の世界づくりのために求めたアイディアだったのだろう。
◆YouTube音源
■”I Love You, Samantha” by Bing Crosby
*映画『上流社会』でビング・クロスビーが歌う、コール・ポーター作詞作曲によるバラード。ルイ・アームストロングのイントロのトランペット演奏はルイ・アームストロング。
■”Ascenseur pour I’echafaud” by Miles Davis
◆関連CD
■『死刑台のエレベーター(Ascenseur pour I’echafaud) Original Soundtrack』Miles Davis
◆関連映画・DVD・Blu-ray
■『マイルス・デイビス クールの誕生』

■映画『マイルス・デイヴィス クールの誕生』 (Trailer)
■『MILES AHEAD/マイルス・デイヴィス空白の5年間』
■『死刑台のエレベーター』
■『欲望』
■『ジャッカルの日』
■『最初の人間』
| 佐竹 裕(さたけ ゆう) |
|---|
 1962年生まれ。海外文芸編集を経て、コラムニスト、書評子に。過去に、幻冬舎「ポンツーン」、集英社インターナショナル「PLAYBOY日本版」、集英社「小説すばる」等で、書評コラム連載。「エスクァイア日本版」にて翻訳・海外文化関係コラム執筆等。別名で音楽コラムなども。 1962年生まれ。海外文芸編集を経て、コラムニスト、書評子に。過去に、幻冬舎「ポンツーン」、集英社インターナショナル「PLAYBOY日本版」、集英社「小説すばる」等で、書評コラム連載。「エスクァイア日本版」にて翻訳・海外文化関係コラム執筆等。別名で音楽コラムなども。好きな色は断然、黒(ノワール)。洗濯物も、ほぼ黒色。 |
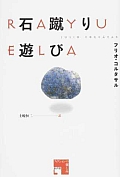 石蹴り遊び (フィクションの楽しみ) 石蹴り遊び (フィクションの楽しみ)出版社:水声社 著者:フリオ・コルタサル 取扱開始日:2016/08/25  価格:4,400 円(税込) 価格:4,400 円(税込) |