「犯人は創造的な芸術家だが、探偵は批評家にすぎぬのさ」
というのは、ブラウン神父譚「青い十字架」での、パリ警察主任ヴァランタンの台詞。
いかにもチェスタトンらしい逆説めいた警句だが、探偵は創造的な芸術家足りえないのかというのは、長年の疑問だった。
この台詞は、真田啓介『フェアプレイの文学』『悪人たちの肖像』にも何度か登場する。
■真田啓介『フェアプレイの文学』『悪人たちの肖像』
 古典探偵小説の愉しみ 真田啓介ミステリ論集 1 フェアプレイの文学 (叢書東北の声) 古典探偵小説の愉しみ 真田啓介ミステリ論集 1 フェアプレイの文学 (叢書東北の声)出版社:荒蝦夷 著者 真田 啓介 取扱開始日:2020/06/13  価格:4,400 円(税込) 価格:4,400 円(税込) |
 古典探偵小説の愉しみ 真田啓介ミステリ論集 2 悪人たちの肖像 (叢書東北の声) 古典探偵小説の愉しみ 真田啓介ミステリ論集 2 悪人たちの肖像 (叢書東北の声)出版社:荒蝦夷 著者 真田 啓介 取扱開始日:2020/06/13  価格:4,400 円(税込) 価格:4,400 円(税込) |
古典探偵小説の愉しみを語って、当代最高の書き手の一人である真田啓介の評論集が二冊同時刊行、というのは、ファンにとっては、大きな事件だろう。国書刊行会の『世界探偵小説全集』はじめ、解説にこの方の名前をみると、胸がときめいたものだ。
本書により、とりたててペンネームらしくもない真田啓介(まだけいすけ)という筆名は「murder case」のもじりと知った。探偵小説評論の書き手として、まさに完璧ではないか。
各500部という少部数の出版ながら、過去に書かれた解説文などを集成した仙台の出版社・荒蝦夷には感謝しかない。
第一巻『フェアプレイの文学』はアントニイ・バークリーや英国余裕派の作家、第二巻『悪人たちの肖像』はフィルポッツら英米の作家、そして乱歩、正史など日本の作家に関する文章をまとめている。
著者は、個人誌「書斎の屍体」やROM誌への寄稿で活躍されていたようだが、一般の読者にその名が広く知られたのは、国書刊行会の『世界探偵小説全集』の解説、なかでもアントニイ・バークリーの解説を通じてであるように思われる。
アイルズ名義も含め5冊程度の傑作の邦訳がありながら、なおよく知られざる作家であったバークリーの実像を明らかにし、精妙な作品分析を展開した、1994年『世界探偵小説全集』第1回配本巻である『第二の銃声』における著者の解説は、いまだに記憶に新しい。
第1巻の解説スタイルがそのまま、『世界探偵小説全集』の解説スタイルでもあった。それは、編集に当たった藤原編集室の姿勢でもあろうが、その特色を挙げると、
2 海外における最先端の評論・研究を参照すること
3 真相に触れることを前提として、指定箇所で作品の妙味を明らかにすること
4 詳細な著作リスト
従来の「解説」に飽き足りない思いをしてきた読者にとって、この解説における実証主義ともいえる徹底ぶりは、古典探偵小説の解説に清新な風をもたらした。
第1巻『フェアプレイの文学』で約半分を占めるのは、バークリーに関する論考だが、これらは、未訳作の紹介と相まって、従来のバークリー評価を一新させ、我が国でもバークリーを黄金時代の最重要作家と位置づけるのに貢献したといっても過言ではない。
著者の解説・論考の特徴として、先の『世界探偵小説全集』の解説の特徴に加え、
イ 明晰な論理
ウ 堅実な文体とにじみ出る教養
エ 探偵小説的記憶の豊かさ
オ 余裕派的態度
などが挙げられるだろうか。
■ア テキストの精読
「読むという行為は、一にも二にもテキストを、テキストそれ自体を(中略)読むことのはずである」(『毒入りチョコレート事件』論 あるいはミステリの読み方について)と著者はいう。テキストの意味するところを虚心に、仔細に吟味しつつ読む、それが著者の態度である
『毒入りチョコレート事件』は、傑作短編「偶然は裁く」(別題「偶然の審判」)を長編化したものという従来の定説を覆す論考(「The Avenging Chance」の謎)は、精密なテキスト・リーディングに基づき、従来の定説を覆している。人物の登場順等に着目して結論に至る「読み」の抜群の切れ味を見よ。
■イ 明晰な論理
アとも密接に関連するが、その論考は、ディテールを揺るがせにせず、常に明晰な論理で綴られている。
「小説におけると同様、評論においてもディテールは重要である。論理の鎖を構成する輪の一つひとつがしっかりとしたものでなければ、鎖は十分な強度を保ち得ないだろう」(「江戸川乱歩の「探偵小説の定義」をめぐって」)
バークリー作品の一大特徴である多重解決に関して、「多重解決――だろうか?」と疑問を投げかけ、「偽の解決が生れる原因」という斬新な課題設定をした上で、三つ要因に分けた分析のロジカルなこと。(前出『毒入りチョコレート事件』論)
「探偵小説の論理は、犯人の側の論理(構成の論理)と探偵の側の論理(解明の論理)の両面から検討される必要がある」(「謎と笑いの被害者捜し レオ・ブルース『死体のない事件』解説」)という明確な批評の軸。この発想は、ごく初期に属する個人誌に掲載された「犯罪と探偵」と題された乱歩の『陰獣』論で既に明確にされている。
ノックスのブリードン物の一見退屈な表面上のストーリーの裏側に「もつれ合い絡まり合うプロットの躍動」(「神経の鎮めとしてのパズル」)を見い出すことができるのも、この論理性ゆえだろう。
■ウ 堅実な文体とにじみ出る教養
詩的飛躍のある文体ではない。ブロックを堅実に積み上げ、趣旨が確実に伝わるクリアで精度の高い文章。さらに、探偵ロジャー・シェリンガムの発言から、シェイクスピアの作品への連想が働き、イネスを論じるのに、フォースター『小説の諸相』やスターン『トリストラム・シャンディ』が引き合いに出される。リリアン・デ・ラトーレの作品では、サミュエル・ジョンソン博士を縦横に語るなど、特に英文学への造詣が深く、読者の作品への理解を助けている。
■エ 探偵小説的記憶の豊かさ
フィルポッツ論では、バークリー、ヴァン・ダイン、フィルポッツと資質も志向も異なるような作家を並べて「人間の性格心理の重視」という「一九二六年のトレンド」を抽出してみせる。「探偵小説とウッドハウス」では、小説の細部に着目しウッドハウス好きの探偵作家を奇術師のように帽子から取り出す。多くの探偵小説を読んでいる読者でも、こうしたディテールは忘れていくものだが、関連する探偵小説の記憶が呼び覚まされ、それが次の批評的思考に援用されていくのは、探偵小説愛好者にとっては快感でもある。
■オ 余裕派的態度
『フェアプレイの文学』第二章では、ベントリー、ミルン、ノックス、レオ・ブルース、イネス、クリスピンといった作家を採り上げ、「英国余裕派」と著者の造語でひとくくりにしているが、そのユーモア、遊び心、ゆとりと落着き、品格、アマチュアリズムといった特徴は、著者の執筆の態度にも似ている。それはそのまま探偵小説への愛に裏打ちされたものであった。
著者はいう。
「クラシック・ミステリの発掘はけっして懐旧的な手すさびなどではなく、ミステリの伝統を誤りなく把握しようとする試みであり、現代ミステリでは味わえない新鮮な感動を求めての探求の旅なのだ」(「時計が巻き戻されるとき ディヴァイン『ロイストン事件』解説」)
愛好家は、力づけられることばではないだろうか。
さて、冒頭の言葉に戻ろう。
前出「『毒入りチョコレート事件』論」では、「探偵の推理と批評家の読解が同じ性質の行為であることは、改めてチェスタトンを持ち出すまでもなく承認されることだろう。事件の解決は、作品の読みに類比できる」と語る。
テキストの精読と明晰な論理。著者の批評行為は探偵行為に限りなく近接していく。
著者は、『ロジャー・シェリンガムとヴェインの謎』を「探偵小説の形式で書かれた探偵小説論」と位置づけている(「空をゆく想像力」)
そのことばを借りると、著者の論考の半ばは、「探偵小説論の形式で書かれた探偵小説」ではないだろうか。それも、ディテールもロジックも優れものの。
それでも、探偵は批評家に「すぎず」、批評家は探偵に「すぎない」のか?
そうではない可能性――探偵も創造的な芸術家である可能性――を著者のバークリー論は、示している。(前出「空をゆく想像力」)
すなわち、ブラウン神父は、想像の中で自ら犯罪者となるという通路を通って。ロジャー・シェリンガムは、自身の過度の想像力という通路を通って。
そうであるとすれば、批評家も、また、犯人=創造的な芸術家である可能性を本書は体現しているように筆者には思えるのである。厳密なテキスト・リーディングと明晰なロジックという通路を通って。
■荒蝦夷書籍販売ページ
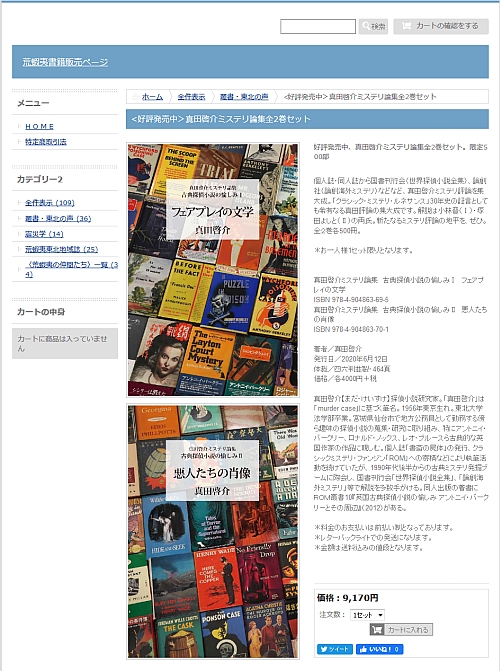
■エミール・ガボリオ『バスティーユの悪魔』
『バスティーユの悪魔』は、1866年に世界初といわれる長編ミステリ『ルルージュ事件』を刊行、名探偵ルコックを創造し、ミステリ史上の名を遺したフランスの作家エミール・ガボリオが初めて手がけた、知られざる長編(1882)。
初めての小説が、作者の死(1873)後に刊行されたのには理由があり、本書は半ばの11章までが雑誌に連載された中断作なのだ。中断の理由は、作者の眼の炎症だという。ガボリオは次々に別な作品を執筆し、本書の連載は再開されることもなかったのだが、ガボリオの死によって、ドル箱作家を失った版元が12章から15章を付け加え、『毒殺女の恋』として刊行したという曰くつきの作品。付け加えられた部分は、ガボリオの手によらないものとみられているという。
2014年にフランスで復刊されるまで、長らく忘れられていた珍品であることは間違いないが、本書は、書かれた当時から2世紀前を回顧した歴史小説であり、どうせ訳されるなら、ルコック物の未訳作のほうがありがたかったという気もする。
けれども、本作は、意外に読ませる伝奇ロマンであり、ミステリファンが眼を通しても損はない一冊だ。
主要人物の一人は、17世紀連続毒殺犯ブランヴィリエ侯爵夫人。ディクスン・カーが『火刑法廷』で侯爵夫人と彼女周辺の人物を作品の登場人物にタブらせていることはよく知られている。
本書には、彼女が毒殺を重ね大殺人者となる前日譚的な趣きがある。
騎士サント=クロワは、賭博にうつつを抜かした後、深夜の逢引に駆けつける。逢引の相手は、ブランヴィリエ侯爵夫人その人。彼女は10代の頃からサント=クロワと恋仲だったが、今は侯爵夫人の身分。安キャバレーの二階での逢瀬だったが、その夜はいつもと違った。家名を重んじる侯爵夫人の父らが密会の場所に急襲をかけ、サント=クロワはバスティーユの牢獄に拘引される。
当時の一大社交場だった〈浴場〉で放蕩にふける男女の集団、閑静な侯爵の大邸宅、安キャバレーで偽装した豪奢な逢引の場と舞台は移り変わり、密会する男女が現場を押さえられる場面のサスペンスも濃厚で、なかなかの滑り出しだ。
絶望に浸され復讐を誓うサント=クロワは、エグジリという毒薬の大家と牢獄の同房になり、彼に弟子入りをする。このエグジリこそ本書の影の主人公というべき人物で、牢獄の中で化学実験すら許されているという大犯罪者。獄中で殺人の陰謀や脱獄計画が進行する中、舞台は一転、美少女に身分違いの恋をするオリヴィエという青年の話となる。彼らを結びつける糸は次第に明らかになり、運命の糸車は苛烈に廻り始める。
現代の眼からみると、登場人物の語りが大仰すぎる面はあるが、大筋は史実に沿いつつも、人物相互の関係性に立脚したガボリオのプロット構築力はさすがで、後年あるを思わせる。これも実在したというメフィストフェレス的人物エグジリの造型は強く印象に残り、禁断の墓堀をはじめ、随所に、サスペンスを盛り込んでいく作者の手腕には瞠目させられる。
雑誌掲載時のタイトルが『ブランヴィリエ侯爵夫人』、副題が『バスティーユ年代記』となっていたそうだが、前半の主役、ブランヴィリエ侯爵夫人は途中から後景に退いてしまっているため、本書は付け加えられた章を遥かに超える長編になっていたものと想像される。
牢獄につながれ復讐を誓うサント=クロワの姿は、デュマ『モンテ・クリスト伯』に似て、作者の構想が十全に展開されれば、虚実ないまぜとなった一大伝奇ロマンになっていただろうに、そのことが惜しまれる。
| ストラングル・成田(すとらんぐる・なりた) |
|---|
 ミステリ読者。北海道在住。 ミステリ読者。北海道在住。ツイッターアカウントは @stranglenarita 。 |