みなさま、カリメーラ(こんにちは)!
Facebookにはギリシャのミステリ・ファンのウェブページがいくつかあります。「ミステリ文学の友 Φίλοι Αστυνομικής Λογοτεχνίας」とか「ギリシャ・ミステリ文学作家の友 Φίλοι Ελλήνων Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας」などは公開グループで、メンバーお気に入りの本の写真が数多くUPされており、眺めるだけで楽しいサイトです。
◆「ミステリ文学の友 Φίλοι Αστυνομικής Λογοτεχνίας」
https://www.facebook.com/groups/1680551212181112
◆「ギリシャ・ミステリ文学作家の友 Φίλοι Ελλήνων Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας」
https://www.facebook.com/groups/2319599004949980/?multi_permalinks=2647633502146527¬if_id=1592739888445862¬if_t=group_highlights&ref=notif
最近あるファンが後者のページにこんな投稿をしました。
「コロナウイルスと防疫のギリシャを背景にしたミステリを最初に書くのは誰だと思う?」
圧倒的に多かった回答は、やはりと言うべきか、ミステリ作品で社会の矛盾を描き続けるペトロス・マルカリス(ギリシャ・ミステリ六歌仙No.2)【エッセイ2回】でした(もう一人、目に付いた名前はエヴィア警察カペタノス警部のディミトリス・シモス【エッセイ11回】)。
ギリシャ・ミステリ史上で最も重要な名前を挙げるなら、何をおいてもジャンルの創始者ヤニス・マリス【エッセイ1回】ですが、ついで中興の祖ペトロス・マルカリスであることは、誰にも異論のないところです。
今回は《国境を越える》ペトロス・マルカリスのその後の作品を三作ご紹介します(最近出たばかりの『殺しは金になる』(2020年)はすでに13作目。精力的に執筆を続けています)。
デビュー作『夜のニュース』(1995年)はシリーズ探偵コスタス・ハリトス警部が登場し、アルバニア移民殺しに始まる国境を越えた大掛かりな組織犯罪を、第二作『ゾーン・ディフェンス』(1998年)ではマフィアの縄張り抗争と思われた中に、まさにゾーン・ディフェンスのように張り巡らされた複雑な金融犯罪を暴きました。
これ以降は事件の奥行きの深さに加えて、犯罪そのものが大仕掛けになっていきます。
◆不思議な題名の第三作
第三作には『チェは自殺した』(2003年)という奇妙な題名が付けられています。表紙デザインにはチェ・ゲバラのプリントタオル(?)。ゲバラはボリビアで処刑されたはずですが、自殺っていったい……?
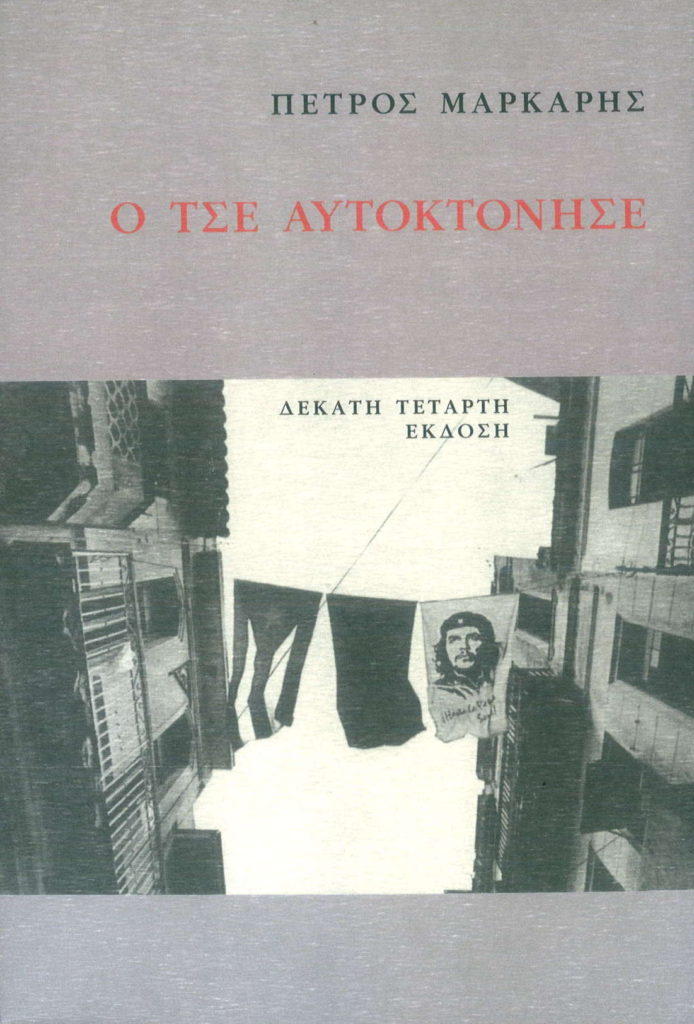 ペトロス・マルカリス『チェは自殺した』 ペトロス・マルカリス『チェは自殺した』ガヴリイリディス社、2003。 |
前作の最後で深手を負ったハリトス警部は療養休職中です。アドリアニ夫人や娘カテリナ、その恋人ファニス医師(心臓外科医。第二作『ゾーン・ディエンス』で急病になったハリトスを診察してくれた医者)など常連キャラが次々に顔を見せ、鶏肉料理で精をつけさせなくては、と夫人は腕を振るっています。上司ギカスは一度見舞いに来ただけ。
そんな折り、衝撃的な事件が起こります。テレビで対談中だった大手建築業者ファヴィエロスが突然カメラの前で拳銃自殺を遂げるのです。アテネ・オリンピック(2004年)を前に大型受注をものにし羽振りの良かったこの男、政界・官界との癒着の噂も絶えませんでしたが、1967-74年の軍事政権の時期には左派の抵抗運動リーダーだったという複雑な人物です。
すぐに《マケドニア人フィリポス》なる極右組織が犯行声明を出します。
さらに後日、驚くべきことにファヴィエロスの伝記が謎の著者により出版されます。彼の業績を讃えながら後ろ暗い部分も臭わせているという非常に微妙な内容。出版社からも著者の正体がたどれません。もしかしてファヴィエロス自身が生前に書いたものなのか?
公式には自殺となりますが、裏があることを感じた本部長ギカスは、休職中のハリトスに内偵を命じます。ファヴィエロスは建築会社で稼ぐ一方、不動産のチェーン店を展開し、なにやら画策していた形跡があります。
そうこうするうちに、有力政治家ステファナコスがテレビ対談中に短剣で自殺という、これまた奇怪な事件が起き、またしても謎の伝記が出版されます。ステファナコスもまた軍事政権下で抵抗運動をしていたという過去がありますが、二人の自殺者の間にどんなつながりがあるのか? さらに、第三の自殺者が…… おまけに、ハリトス警部には何者からかチェ・ゲバラのプリントTシャツが送られてきます。ここで題名につながるわけです。極右組織が犯行声明を出してはいますが、元左翼が暗殺されたのではなく、自殺とはどういうことなのか? ハリトス警部はギリシャ近代史の迷宮を歩み続けます。
連続公開自殺事件、というのが実にゾッとする展開です。ただし、そこはリアリズムが身上のギリシャ警察ミステリ。ジョン・ディクスン・カー『連続殺人事件』の謎のバスケットとかコーネル・ウーリッチ「九一三号室の謎」の客が必ず飛び降りるホテルの部屋などを想像してはいけません。なぜ犠牲者たちが自殺するのか。その背後には軍事政権という三十年前の過去が絡んでいます。
マルカリス作品が読み応えがあると感じるのは、個人と社会とのかかわりが強く意識されている点です。
個人の行動の背後にはその時代の社会があり、本人の意識の中では金銭や愛憎や保身のために悪事に走るにしても、視点を広げて見れば、その行為を促し、あるいは強いる社会状況があります。しかし社会がねじれているからと言って、それに後押しされた罪は許されるのか? ある者は罰されるけれど、ある者は要領よく渡りきって生き延びる。ならばそういう者に対して個人的制裁で報いるのは正義なのか? 謎解きサスペンスのストーリーの底に、こういった重い問題が流れています。作家は声高に訴えるのではなく、あなたならどうするという問いを静かに突きつけてきます。
ハリトス警部にもむろん答えはなく、自分に与えられた役割――謎を解き犯人を逮捕することしかできません。主人公は全肯定のヒーローなどではなく、読者と近い位置に立っています。
今回の作品で恐ろしいのは、社会の状況によって善悪が簡単に逆転するという点です。
軍事政権中は左翼の活動家が逮捕され虐待されていたのに、崩壊後は逆に軍事警察官が逮捕され裁かれてしまう。ある体制が崩壊すると直後に正義が真逆に入れ替わってしまう恐ろしさ。
当時、左翼に対する拷問で鳴らした元軍事警察官が出てきます。十年の懲役を受けたこの男、自分は体制の正義に従って行動しただけだとハリトスに抗弁しますが、今ではチェ・ゲバラのプリントグッズで何とか食いつないでいる、というのが何とも痛烈な皮肉です。
◆味のある脇役たち
マルカリスの筆致は人物を単純なタイプにはめ込むような平板な造形に終わりません。特に印象に残る人物を二人紹介しておきましょう。
まず、ハリトス警部の上司であるギカス准将。デビュー作では巧妙に立ち回るくせもの官僚として登場します。政府高官との関係は抜け目なく維持し、公式発表用原稿など面倒な仕事はハリトスに押しつけるというパワハラタイプ。ところが、『チェは自殺した』ではなぜか、病気休暇中のハリトスの自宅にまでやってきて、公式には終了した自殺事件の内偵を密かに依頼します。代理の警部がいるのに、とハリトスは戸惑いながらも、結局は頼りにされているのかもな、とけっこう悪い気はしません。しかし、よくよく考えてみて、休暇中の警官が捜査で失敗してもギカスには責任なし、成功すれば手柄は自分のもの、嫌っている代理警部の面目もつぶせるからか、とハリトスは気づきます。やはり食えない男ギカス。
もうひとりの渋い脇役は元左翼の活動家ジシス。軍事政権下で敵対する相手としてハリトスの前に現れます。駆け出し警官だったハリトスは弾圧や拷問方法を上官から叩き込まれますが、体制への不信を心のどこかに抱えており、芯の通ったジシスに対して残酷になり切れません。何十年かぶりに事件のヒントをもらうため隠遁生活を送るジシスを訪ねた時(彼の情報量は警察の資料室以上)、ある親近感と敬意を覚えながらも、やすやすとは越えられない立場の違いを感じます。この付かず離れず、決してベタベタした友情にはならない二人の関係が何ともいい味を出しています。
◆ハリトス警部のお気に入り
ハリトス警部の大好物といえば、詰め物料理「ゲミスタ」でした【エッセイ2回、写真あり】。
https://www.facebook.com/lidlgr/videos/269622994286942
しかし本作で二つ目のお気に入りが判明しました。ナス料理の「メリジャネス・イマーム」です。ナスはそのままトマトソース煮にしてもおいしい(「メリジャネス・コキニステス」)のですが、刻んだタマネギを先にトマトソースで炒めてからナスに詰めて焼くとメリジャネス・イマームになります(警部は詰め物系がお好き。)
 【メリジャネス・イマーム。トマトソースで炒めたタマネギをナスに詰めて焼いたもの。】 |
「メリジャネス」は「ナス」、「イマーム」は「イスラムの僧」のこと。もともとトルコから伝わった料理で、トルコ語そのままに「イマーム・バイルディ」とも呼ばれます。《(美味しすぎて)坊さんが気絶した》という意味だそうです。
オスマン帝国が舞台のジェイソン・グッドウィン『イスタンブールの毒蛇』にはこの名前がチラッと出てきます。宮廷の宦官探偵ヤシムが調理中のナス料理の名を尋ねられて、「イマーム・バイルディじゃありません、ヒュンカル・ベンディ(スルタンも認めた味)です」と答えています。二つは宮廷料理の双璧だそうですが、ギリシャ料理のメリジャネス・イマームは家庭で作れる庶民の味になっています。
ついでながら(駄弁お許しあれ)、台湾には対岸の福建地方から伝わった「佛跳牆」という料理があります。フカヒレやアワビなどの高級食材が入ったこってりスープです。《(おいしさのあまり)坊さんも寺の塀を乗り越えて食べに来る》という、これまたユニークなネーミング。定訳はまだないようですが、日本語専攻の学生は「ぶっとびスープ」と言ってました。坊さんの気絶と坊さんの修行逃亡、どちらも強烈なおいしさですね。
 【佛跳牆(ぶっとびスープ)。もともとは高級料理ですが、近所の大衆食堂には廉価メニューがありました】 |
◆お堅い書名の経済犯罪第四作
マルカリスに戻りましょう。続く四作目は何やら金融入門書のようなお堅い題名の『筆頭株主』(2006年)。どう考えても複雑な経済犯罪に違いないと思い、ちょっと敬遠していたのですが、ぜんぜん違っていました。
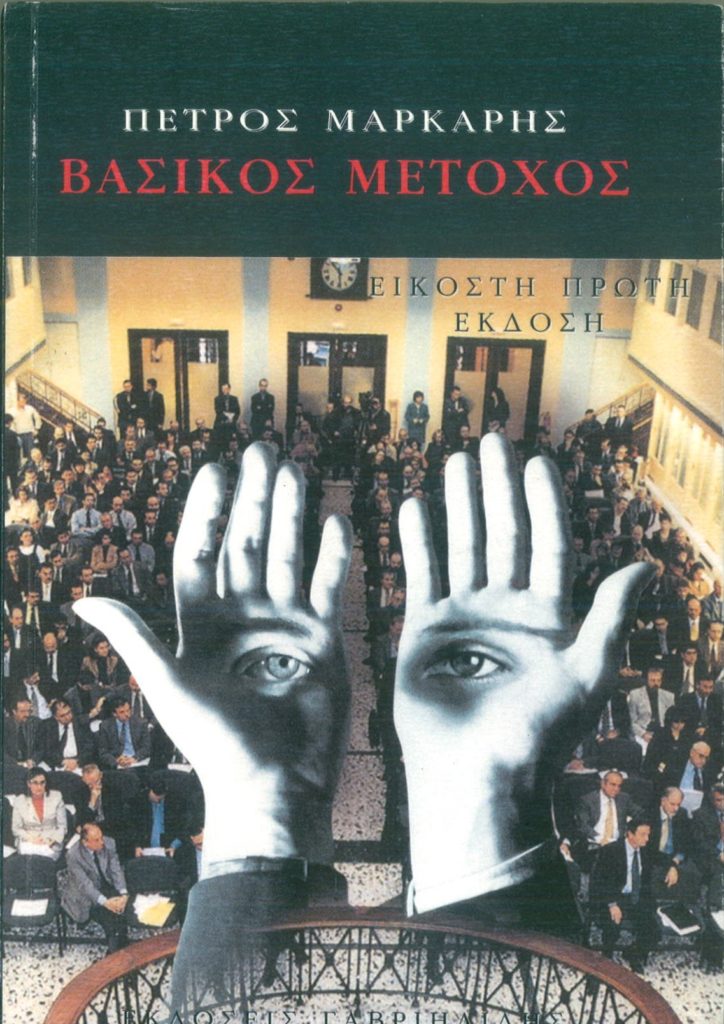 ペトロス・マルカリス『筆頭株主』 ペトロス・マルカリス『筆頭株主』ガヴリイリディス社、2006。 |
冒頭で司法界を目指す警部のひとり娘カテリナが博士課程の最終口頭試問を受けています。公開審査なので客席で両親と婚約者ファニスが心配そうに見守る中、カテリナは堂々と質問に回答します。ハリトスおやじさんは自分が逮捕した犯人を将来判事となった娘が裁くのを夢見ています(どこにでもいる普通の父親です)。
カテリナは無事首席で課程修了(優秀です)、ファニス医師と連れだってクレタ島へ卒業旅行に出かけるのですが、その《エル・グレコ》号(有名なこの画家はクレタ出身)が何とテロリストに乗っ取られてしまいます。船は島の西方ハニア沖に停泊(パトリシア・ハイスミス『殺意の迷宮』で主人公たちが抗争した町)し、港にはテロ対策本部が置かれます。小さな町にはジャーナリストたちが殺到し大混乱。船の上空ではヘリが舞っています。ハリトス警部も妻アドリアニと島に飛びます。娘を案じヒステリーが止まらないアドリアニをハリトスは賢明になだめ食事に連れ出します。三十年連れ添った夫婦のなかなかいいシーンです。
テロリストはじらし作戦に持ち込むようでなかなか要求を掲げません。パレスティナ・ゲリラ説やらチェチェン独立派やらのさまざまな説が飛び交います。
ところが、折悪しくアテネ市の方でCMスターの射殺事件が起こり、アテネ本部殺人課のハリトス警部には帰還し指揮せよとの命令が下ります。沖合の船をじっと見つめるアドリアニに帰還命令を説明する警部の姿が切ない。
こうして、クレタ沖でカテリナの命がかかるシージャック事件が硬直したまま、アテネ市内では射殺事件の被害者が増えていきます。テロリストたちの正体と要求も気になりますが、一方でなぜCM関係者ばかりが殺されなければならないのか? それも今時手に入らない古いルガー拳銃を使って。射殺事件の犯人は次第に大胆になり《筆頭株主殺し》を名乗り始めます。その真意は?
いつもながら、サスペンス溢れるストーリーの背後では、社会の矛盾がどっしりと描かれます。
折しも警察改革の一部として、国内在住の外国人にも平等に警官採用を広げようという反差別の動きがあり、世間ではこれに対し賛否両論が沸き上がっています。船の乗っ取り犯たちもこの撤回を要求の一部に掲げてきます。
また、最初の射殺事件が起きるのはアテネ海岸部の元オリンピック会場ですが、アテネ大会が終了した後、現在は巨大なゴミ置き場として無残な姿をさらしています。(短編「三人の騎士」(2018年)でもここで類似の事件が起きますが、単に事件のセッティングではなく、国中を巻き込んだあの興奮は一体何だったのか?という疑問が負の遺産を前にして投げかけられます。)
終盤で誇大妄想狂の異様な人物が姿を現します。第二次大戦中は枢軸国占領下で《防衛大隊》として占領ドイツ軍の手先となり(占領軍以上に)自国民を虐待。内戦後この組織は警察組織に組み入れられますが、十数年後の軍事政権下で拷問官となって悪名をはせた人物。『チェは自殺した』でチラリと顔を出す元軍事警察官の拡大版といったところで、近代ギリシャ史の負の側面が一人の人物に凝縮されたかのようです。
そういうわけで作品に盛られた社会への眼差しの深さはデビュー作以来一貫していますが、その一方で、「連続自殺事件」「シージャック事件」と事件そのものも派手になってきました。特に『筆頭株主』のシージャック事件は、映像化したら巨額の費用がかかりそう。静かに進行するスケールの大きなサスペンスは、(昔々の映画作品ですが)「ジャガーノート」を思い出してしまいました(ただし、こちらは乗っ取りではなく船に爆弾を仕掛けて脅迫する話)。
◆リラックスしたトラベル・ミステリ第五作
 ペトロス・マルカリス『昔、遙かな昔』 ペトロス・マルカリス『昔、遙かな昔』ガヴリイリディス社、2008。 |
大がかりなテロ事件が解決した後、ハリトス警部は妻アドリアニといっしょにトルコのコンスタンチノープル(イスタンブール)観光を楽しんでいます。警部にとって文字通り《国境を越える》のは初めてです。聖ソフィア大聖堂のモザイク画をのんびり見上げたりしていますが、実はここに来たのはちょっとワケありです。前回事件に巻き込まれた娘カテリナの療養も進み、ファニス医師と結婚することになったのはめでたいのですが、現代っ子で何事も理詰めの法官の卵カテリナは役所への結婚届けだけですませます。ギリシャ女性が教会で伝統的な式を挙げないなんて信じられない!と悲嘆に暮れるアドリアニを気分転換させてやろうとハリトス警部は休暇を取り、旅行に連れてきたのです(口には出さないながら父警部もガッカリしています)。
しかし、もちろんハリトス警部の観光旅行記で終わるわけはなく、やっぱり事件に巻き込まれてしまいます。
偶然知り合ったコンスタンチノープル在住のギリシャ人から、知り合いの九十歳近い女性マリアが当地を訪ねてきたはずなのに連絡がない、警部さん捜索に協力してくれまいか、と頼まれます。異国の地でなんだかフィリップ・マーロウ化してしまったハリトス警部。迷惑だなと思いながらも、マリア在住の北ギリシャの町ドラマに連絡を取ると、女性は行方不明になっており、しかもその弟は何とティロピタ(チーズパイ)に入れられた毒で殺害されていました(マリアはパイ作り名人として近所で有名だった由)。
 【ティロピタ(チーズパイ)。中に入れる具によっていろいろなピタ(パイ)ができます。前回トリピ・チームのドナス巡査長が差し入れていたのは奥さん手製のホウレンソウ(スパナキ)が入ったスパナコピタでした】 |
その後、コンスタンチノープルで毒殺事件が続きます。高齢のマリアがパイで殺して回っているのか? そう想像すると相当不気味ですが(貴志祐介『黒い家』の登場人物を思い出す)、シージャック事件の前作に比べて何だか地味な展開ではあります。
しかし、ハリトス警部が地元のトルコ人警部補と組んで捜査をしていくうち、マリアの壮絶な生涯が浮かび上がってきます。そこにはまさにトルコ在住のギリシャ人の歴史が濃縮されています。マリアの生まれはポンドス地方(黒海沿岸)ですが、オスマン・トルコの迫害を受け(これはアルメニア人も同様。クリスティー『ものいわぬ証人』でちょっと触れられていた事件)、首都コンスタンチノープルへ逃れてきます。家族とも離れて他家の下働きで日々の糧を得ていましたが、1955年の九月事件の被害をもろに受けます。当時過激化していたキプロス独立運動のあおりを受け、コンスタンチノープルで起こった大暴動です。これによりギリシャ人コミュニティーは壊滅、現在では(首都の総人口千四百万人中の)二千人というマイノリティーになってしまいました。(マルカリスはこの事件を短編「三日間」(2007年)――ハリトス警部物ではないのですが――で正面から取り上げています【エッセイ2回】)。
迫害され続けたマリアは唯一自信のある手作りパイによって恨みの相手を殺しているのでしょうか?
リラックスしたトラベル・ミステリとか、地味な物語とか、とんでもない誤解でした。現在の事件は昨日今日のことではなく、《昔、遙かな昔》に根ざしています。マルカリスの筆は読者の想像をはるかに越えた歴史と社会の深みへと連れていってくれます。
実はマルカリスはコンスタンチノープルの生まれです。作品中で初めてトルコを訪れたハリトス警部は、ここはギリシャと同じだ、ここは違うな、などと個人的感想を口にします。作家自身は逆に、生粋のギリシャ人主人公を通して、自分のかつて知った土地に対する思い――時に冷静な比較文化論、時に言い尽くせぬ郷愁――を語っているということでしょう。
脇役に至るまで人物一人一人の人生が凝縮されているのはいつも通りですが、この作品で印象に残るのはなんと言っても、ハリトスと組むトルコ警察の若きムラト警部補でしょう。
最初はよそ者ハリトス警部に素っ気ない態度を取り、警部の方も上司や退役軍人からトルコ警察には騙されないように、などという忠告に影響されてなかなか胸襟を開けません。しかし、コンスタンチノープル在住のギリシャ人のことはギリシャ人のあんたよりおれの方がよく知っているよ、というムラトのことばに警部が心を揺さぶられるあたりから両者が接近し始めます。実はムラトはドイツ在住トルコ人移民の息子で、当地警察に就職したものの、わけあってトルコに戻り現職にあります。マイノリティーの心情は自分自身のこととしてよく知っているのです。
ムラトは最後のクライマックスまでハリトスにつきあい、なかなかいい関係が生まれます。このへん、作者の願いが込められているようです。
ところがリアリストのマルカリスは、同時に、上で触れた「三日間」で、二つの民族の関係が辿るもう一つの道を示しています。作品の最後である登場人物が投げつける拒絶のことばには絶望の深淵が口を開けています。
2011年の短編「馴染みの土地」はムラトが主人公となったスピンオフ作品で、生まれ故郷ドイツの村を訪ね、トルコ人移民同士の対立やドイツ人極右派の介入する厄介な事件に出遭います。人はどこに住むべきか、という作家の追求してきたテーマはここにも流れています。
マルカリスの作品はこの後、ハリトス警部物の《経済危機三部作》が続きます。その一作目『期限切れの負債』(2010年)は2011年の第11回《欧州ミステリ大賞Prix du polar européen》を受賞した作品です。(2003年フランスの週刊誌《Le Point》により創設された賞で、フィリップ・カー、ピエール・ルメートル、アーナルデュル・インドリダソンなども受賞しています)。
このお話はまたいつか。
◆《小さなスクリーン》のハリトス警部
「
」はテレビの意味です。ハリトス警部は「夜のニュース」(1998-99年)と「ゾーン・ディフェンス」(2007-08年)の二作でテレビにも登場しています。どちらもYouTube で見られます。
◆https://www.youtube.com/watch?v=D7xjK4ECpSw&list=PL8Pra97AUsbtf6hr1eCoZBWzgo8J2ou3d&index=1
【「夜のニュース」(全18エピソード)。ベッドで辞書を読むハリトス警部。「靴は脱いでよ」とアドリアニ夫人に怒られてます】
マルカリスの特徴である《警官の一人称語り》がどう映像化されるのかがどうしても気になります。
冒頭でカメラの主観ショットが殺しの現場にずんずん入っていき、オールバックで決めた粋な刑事の一人が話しかけてきます。いやいや、これは野暮な庶民派ハリトス警部じゃないでしょう。はい、部下のヴラソプロス警部補でした。カメラの目が凄惨な室内をなめまわし、レポーターたちをかき分けパトカーに乗り込んだところで、主人公らしき顔がバックミラーに映ります。まさかこの主観ショットでこのままずっと?と思っていたら、タイトルバックが終わってから警部が画面に登場、普通の三人称映像になります。(まあ、そうでしょうね。)
ハリトス警部を演じるのはミナス・ハジサヴァスという古典劇で知られた舞台俳優。見た目は普通のおじさんで、声が渋いでもなく、主役オーラが強烈とも思えなかったのですが、部下を叱りつけるわ、奥さんと派手に喧嘩するわ、だんだんハリトス警部に見えてきます。捜査中しつこい風邪や歯痛に苦しめられたり、会議中カギをうっかり落としてトロトロ探し回ったりと次々に小技の演技も繰り出します。いつも仏頂面なので地かと思っていたら、娘と電話で話すときには急にデレデレ顔になり、つまりはどこにでもいる普通のオヤジ警官に見事になりきっています。
朝食のクロワッサンとギリシャ・コーヒーとか、警部の辞書オタクぶりなど、製作スタッフも原作を非常に大事にしているのが感じられます。夫婦げんかの後の和解のしるしとしてアドリアニ夫人はゲミスタを作っているし、オフィスの窓越しに向かいのアパートで演じられる住民たちのミニ・ドラマを警部がちらりと覗き見るのも、原作通りです。何度か挿入されるこのシーン、時に警部の幻想が混じり不思議な雰囲気を漂わせます。軍事政権下でたたき込まれ身に染みこんだ暴力的な尋問に、今も警部自身が苦しめられる悪夢もちゃんと描かれています。
ついでながら、ハジサヴァスは警部に怒鳴られっぱなしのサナシス巡査長を演じるコスタス・ファレラキスとは長年の同性愛カップルだそうです。「赤い輪」という犯罪ドラマシリーズの第一回「訪問者」(2000年)でも二人は共演し、息の合ったところを見せます。こちらではファレラキスの方が主役刑事で、ハジサヴァスは殺される役になっています。
残念なことにハジサヴァスは2015年に亡くなっており、テレビのハリトス警部シリーズはこの二作で終わりのようです。
◆欧米ミステリ中のギリシャ人(7)――ワシントンD.C. のギリシャ人(1)――
これまでも何度か触れましたが、ギリシャ系の人物がチョイ役ではなく堂々と主役を張るミステリといえばやはりこの人、本人もギリシャ系のジョージ・P・ペレケーノスになります。ありがたいことに邦訳がかなり出ています。
デビュー作『硝煙に消える』(1992年)で主役を務めるのは(作家自身の出身地)ワシントンD.C.で暮らす三世移民の《わたし》ニック・ステファノス。大学で美術を専攻し、家電製品店で広告を担当する管理職に就いています。移民にとってホワイトカラー職は成功のしるし、と周囲からは羨望の目で見られていますが、ともすると以前おぼえたマリファナに手が伸びてしまうちょっと危ない三十前。
定番のように、失踪した元同僚ジミーを捜してほしいという依頼から物語が動き始めます。私立探偵でもなく、体力系でもないニックはためらいますが、頼んできたジミーの祖父に(最近亡くなった)自分の祖父
ニックは万一のため探偵免許証を偽造し(オイオイ)、捜索の準備を始めますが、店内でマリファナを吸っていたのがバレて解雇されてしまいます。身軽にはなったものの、ちょっとでも稼がねばと、気の合う同僚マッギネス(アイルランド系ですね)と組んで消えた元同僚探しの旅へ。バドワイザーを片手に車を走らせ、森の中を走る汽車に飛び乗ったり(少年時代にやってたらしい)、海水浴ではしゃいだりと青春を謳歌してます。ところが、ジミーに関わった人物が殺され、話は何やら物騒な方向へ。新米探偵は消えたジミーを無事見つけられるのか? さらにニック解雇の理由にも実は裏があるらしい……
途中で出てくる大ニックの相棒
おじさんは肉親のように可愛がっているニックに、店のトルコ・コーヒー(ギリシャ・コーヒー。小さなカップで飲む)始め、クルラキア(ねじれた形のクッキー)、クラビエデス(粉砂糖を振ったクッキー)、ガラクトブレコ(クリーム入りミルフィーユ)、バクラヴァ(ナッツ類をパイ生地に挟んで焼いた菓子)とギリシャ菓子の大盤振る舞いです。ニックしあわせ。
    |
このあと、ニックとコスタスおじさんはギリシャの誇るブランドのブランデー、メタクサに進みます。一気に飲み干したニックに「スパルタ人らしい飲みっぷりだな!」。大ニックとコスタスはペロポネソス半島スパルタ近郊の村から渡ってきたようです(母親は今もそこに住んでおり、ニックと国際電話で話しています)。
二作目『友と別れた冬』(1993年)では、ニックは私立探偵の看板を掲げたものの仕事が来なくて、バーのバイトで何とかやりくりしています。
十五年ぶりに親友ビリーがニックを訪れ、(やっぱりと言うか)失踪した妻を探してほしいと依頼。実は知り合いのイタリア系移民と駆け落ちしたのでは、とビリーは疑っています。
(ビリーは時にニックを名前ではなく「ギリシャ人」と呼びますが、これどんなニュアンスなのでしょうか? ケイン『郵便配達は二度ベルを鳴らす』でも店の主ニックおやじがこう呼ばれていました。)
平行して、ニックは友人の記者殺害事件の真相も探ることになります。記者はあるピザ店の火事を取材していました。こちらの事件も深い闇へと続いていそう。
こうして原題Nick’s Tripの通り、またもやニックの旅が始まります。
途中で、事件から手を引けと脅してきた高圧的な警官は、「軍隊時代にギリシャ人たちと知り合ったが、たいていはレストラン関係だ。医者とか弁護士もいる。だがギリシャ人の探偵にお目にかかったのはこれが初めてだ」なんて驚いています。ギリシャ人もついにスペードやマーロウの仲間入り、という作家の宣言なんでしょうかね。
最後にニックは味方とともに黒幕の屋敷に乗り込み、マカロニ・ウエスタンか香港ノワールかというような大銃撃戦へ。アクション度は前作よりずっと上がっています。家電店の管理職だったニックがいつのまにかタフなハードボイルド探偵に成長しているあたり、
この大ニックの生涯が本作では詳しく語られます。エッセイ8回にも書きましたが、大ニックは第一次大戦終結直後(1918年)にスパルタに妻子を残し、一獲千金、貧困脱出を夢見てアメリカにやって来ます。腕っぷしの強い大男で、禁酒法時代にスミス&ウエッソン三十八口径を携帯しながら、ニューヨーク北部で密造酒トラックの運転手をやっていました。30年代にワシントンへ移住。野菜の露天商から出発し、数件のコーヒーショップを経営するまでになります。イタリア系の友人ディジョルダーノに籤を買わせたところ大当たり。ディジョルダーノの方はこれを元手に高利貸しや賭博業を展開。大ニックには恩義を感じており、孫ニックを何かと支えてくれます。
この魅力ある男大ニックは、数年後の《ワシントンD.C.
この作品でも、ギリシャ・レストラン《ヨルガキス》に入ったニックの前に、ザジキ(キュウリとヨーグルトのサラダ)、タラモサラダ(魚卵のサラダ)、レモン汁をかけたタコ、レツィーナ(松ヤニ入りワイン)、カントリー・サラダ(オリーブオイルたっぷりのグリーンサラダ)、スズカキア(細長いハンバーグ)といった料理が豪勢に並びます。
    |
ニック本人も料理をするようで、魚市場でイカを買いこんでは輪切りにして、パン粉、にんにく、オレガノをまぶしオリーブオイルで揚げています。カラマラキアですね。レモン汁をかけるだけで絶品です。
 |
食事では地中海色が満開なのですが、ニックはアメリカ育ち、ギリシャ語で会話する場面はほとんど出てきません。コスタスおじさんとはがんばってギリシャ語でしゃべっていますが、下手くそと言われるのがイヤで、簡単なセンテンスで通します。ギリシャ・レストランへ行ってもアフリカ系ウエイターの方が流暢に話すと自ら認めてしまう始末。
ニックと女友達とのやりとりでちょっと面白いことがあります。彼女はワシントンD.C. の「カロラマKalorama」地区に住んでいるのですが、ガイドブックにはギリシャ語「美しいkalo」+「光景orama」から来ている、と書かれています。ニックは「些細なことをあげつらうわけではないが」、「カロ」は正確には「善い」の意味なんだ、「美しい」なら「オラヨorayo」の方が正しいんだぜ、などと蘊蓄を垂れようとします。意味の点では確かにその通りですが、ただ、この「orayo (ωραίο)」が問題です。古代語の発音なら「ホーライオ」、現代語なら「オレオ」となります。ニックの「オラヨ」はスペリング通りに無理矢理読もうとして、二つが混じり合う奇妙な発音になっています。この「オレオ」、「すごい、すばらしい、いいね!」の意味でよく使われる基本単語ですが……ニック大丈夫なんでしょうか?
続く《ワシントンD.C.
この話は次回に続きます。
| 橘 孝司(たちばな たかし) |
|---|
|
台湾在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっと紹介するのがライフワーク。現代ギリシャの幻想文学・一般小説も好きです。 「バックは新聞を読まなかった」、半世紀前に出会った作品なのに鮮烈に記憶に残る冒頭の一文。バックは犬なのでもちろん読まないのですが、そのせいで、カナダのゴールドラッシュに人々が殺到し橇犬が多数必要とされ、飼い犬にも災いが降りかかるのを知らなかった、と導入が見事に続きます。野生の掟は獰猛と狡猾だけ。慈悲は存在せず、ハードボイルドをはるかに超えています。バックとライバル犬の死闘や決死のヘラジカ狩りなど、セリフのない描写にぐいぐい惹き込まれました。ジャック・ロンドン『荒野の呼び声』(すみません、今回ミステリじゃなくて。これも図書館の廃棄処分を免れた一冊)。 |
| 【この作品がお気に入りのカー・ファンは多いはず。ぜひ新訳をお願いします! できれば題名もオリジナルに近い『連続自殺事件』で。自殺か他殺かで揺れ続け「事件そのものも意外なものであった!」(扉頁の紹介文©)が肝なので】 |
| 【「九一三号室の謎」所収。前半の都会の夜の雰囲気とサスペンスの盛り上げがたまりません。その分最後の謎解きがちょっと……】 |
| 【沈みゆくオスマン帝国を舞台にした豪華絢爛絵巻ミステリとでも呼びたい。訳者和爾桃子氏があとがきでこれらの料理に詳しく触れています。写真もあり】 |
| 【16-17世紀の画家エル・グレコ(クレタ島出身、本名ドミニコス・セオトコプロス)の名が登場し、ちょっとした騙しの仕掛けになっています(あまりに些末すぎてふつうはスルーされるでしょう)。カー作品とギリシャの関係ってこれくらい? イタリアは何回か舞台になっていますが……。子供たちの前で魔術師に扮したH・M卿が笑わせてくれます】 |
|
【中学の時映画館で見ましたが、併映(新作二本立てが普通という時代!)の「サブウェイ・パニック」の方がスピーディーな展開で子供心には面白かった。しかし、今考えると、「ジャガーノート」は(「許されざる者」の伊達者ガンマン)リチャード・ハリス、(人喰い博士になる前のなんとも凛々しい)アンソニー・ポプキンス、(ロシア人からベドウィン族まで演じる)オマー・シャリフ、(これまたサイボーグからホビットにまでなりきる演技派。最近亡くなりました)イアン・ホルム、と錚々たる顔ぶれでした】 |
| 【戦う家電店員ニック・ステファノス・シリーズの最初の二作。1990年代初めのワシントンD.C. が舞台】 |