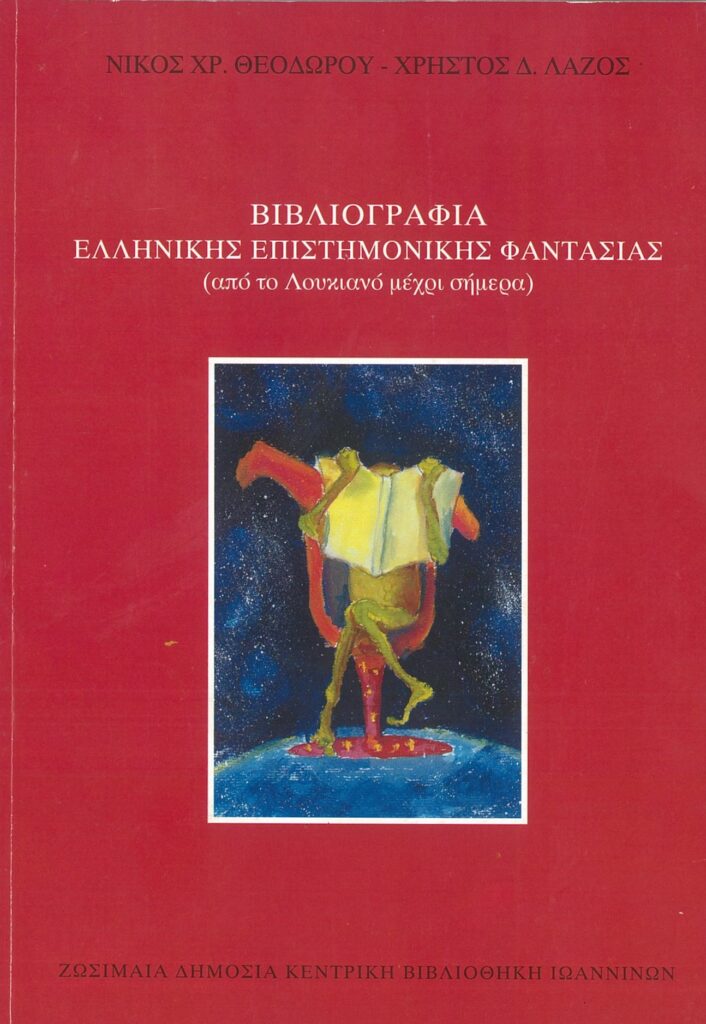みなさま、カリメーラ(こんにちは)!
◆ 心躍るビブリオグラフィー
最近はミステリの話よりもこちらが先になってしまいました。まずはギリシャSF (ε. φ.) に関するミニ情報からです。
1998年刊でちょっと古いのですが、ギリシャSFの貴重な資料集をご紹介します。ニコス・セオドル&フリストス・ラゾス編『ギリシャSFビブリオ』(Νίκος Θεοδώρου & Χρήστος Λάζος, Βιβλιογραφία Ελληνικής Επιστημονικής Φαντασίας, 1998) です。
本書は四つの章から構成されています。
最初に置かれた「ギリシャSF略史」の章は実にありがたい情報で、1920年代のヴティラス『地球から火星へ』から本書の出版年である1998年までのギリシャSFの流れが簡潔にまとめられています。内容をかいつまんでご紹介しましょう。
1920年代のSFと言えば、まずは純文学者が社会風刺や人間心理の分析のために空想科学的設定を取り入れる試みでした(ヴティラス、ハリスなど)。しかし、その後大衆向けのパルプマガジン『鋼鉄人』(Χαλύβδινος Άνθρωπος, 1931-) や『超人』(Ο Υπεράνθρωπος, 1951-) が発行され始め、掲載された翻訳や外国作品の模倣作が若い世代から広い人気を得ます。平行した二つの流れによる発展はミステリ小説の場合と似ています。
ギリシャで現代SFが花開き、興隆を見せるのは1970年代以降の20年間です。もっぱら宇宙探検に限られていた以前のテーマから、宇宙人と地球人の和平、地球上の戦争の宇宙への影響、ロボット、精神剤、エコロジー問題、人間とマスコミ、ディストピア社会など多様に広がっていきます。女性作家も徐々に増えてきます。
1975年には初の本格的な専門誌『万有の謎』(Αινίγματα του σύμπαντος) と『アナロギオ』(Αναλόγιο) が創刊され、後者は作品コンテストも開催します。1990年にはファンジン『サイボーグ』(Cyborg) 創刊に加え、一般雑誌もSFを取り上げるようになります。SFが市民権を得始めたということでしょう。
1990年代に入ってから、SFへの偏見が減るとともに作品数が激増し、さらにはヴティラスの再評価、SFファンクラブの増加、《イカロメニッポス賞》などのSF賞やサイトの設立といった様々な動きが見られます。アカデミズムからの接近も見られ、(『ノヴァ・ヘラス』にも名の挙がる)ドムナ・パストゥルマジ教授がテサロニキ大学でSF講座を開設します。
第一章の最後には各賞・ファンクラブ・サイト情報の他に、ごく簡単な統計表が付けられています。それによると、70年間に出版されたSF単行本は207冊、発表された短編小説は722篇を数えます。ここで興味深いのは作家の男女別の比率です。男性作家が圧倒的に多く、書籍では約74%を、短編になると実に9割近くを男性が占めています。これに比べるならば、2021年の『ノヴァ・ヘラス』は11作中7作が女性の手になり、女性作家の躍進ぶりがわかります。
メインとなる第二章「ギリシャSFビブリオ」では100ページ近くにわたって作家別データが集積され実に重宝ですが、何と言っても壮観なのは続く第三章「ギリシャSF長編、出版年代順紹介」です。簡単な解説を付された200点近い作品の表紙カラー写真がズラリと並び、眺めるだけで幸せな気分に浸れます。第四章は雑誌とファンジンの情報に充てられています(これも表紙写真あり)。
現代までのデータを追補した続編をぜひ出してほしいものです。
◆ 《ホラーの帝王》に捧ぐアンソロジー
さて今回のお薦め本は、ミステリを少々はみ出していますが、本エッセイに登場した作家たちの名も並ぶアンソロジーです。たっぷり楽しめましたので、ぜひご紹介したいと思います。
『王の木陰で』(Στον ίσκιο του βασιλιά, 2017)はその名の通り、スティーヴン・キングを敬愛するギリシャ人作家16人のオマージュ短篇集です。
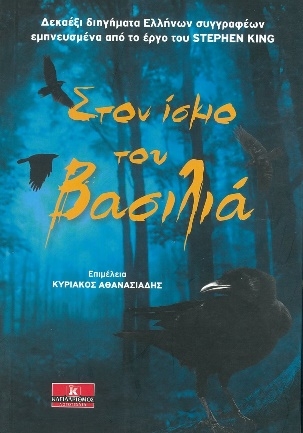 キリアコス・アサナシアディス他『王の木陰で』 クリダリスモス社、2017。 https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=222894&return_url |
最初にお断りしておきますと、私はほとんどキング初心者で(『シャイニング』と短篇集を数冊読んだだけ)、本書の収録作が巨匠のこれこれの作品へのオマージュで、といったことはとても言えないので、ギリシャ人作家たちの力のこもったエンタメ短編アンソロジーとしてご紹介します。
16人中、本エッセイですでにご紹介の作家四人(つまりミステリ寄り)が作品を寄せています。まずはこの面々からいきましょう。
こういう企画にはやはりこの人が出てきます。本書の企画編集も担当しているキリアコス・アサナシアディス (Κυριάκος Αθανασιάδης) 、リレー・ミステリ『黙示録』(Αποκάλυψη, 2018) で血まみれパートを担当した人です(エッセイ第10回)。もちろんグロいだけの作風ではありません。
「バーバ・ヤーガ」(“Baba Yaga”) は語り手をつとめる作家(挙げられた著作名から見て本人)が、遅々として進まぬ新作執筆のネタを求めてプラハに赴き、「バーバ・ヤーガ」なる怪しげなバーで身の毛のよだつ体験をします。「バーバ・ヤーガ」はスラブ伝説で子供を喰らう魔女だそう。作品はキングへの言及に溢れ、よほど私淑しているようです。
作家はテサロニキ生まれですが、2017年からプラハ在住で、よく知る街角を舞台にしたのでしょう。
《イタリア派》ディミトリス・ママルカス(Δημήτρης Μαμαλούκας, 第19回)には《閉所恐怖症》ならぬ《閉所嗜好症》みたいな性癖があって、『赤い旅団の隠れた中核』(Ο κρυφός πυρήνας των Ερυθρών Ταξιαρχιών, 2016) の洞窟や『ディミトリオス・モストラスの失われた蔵書』(Η χαμένη βιβλιοθήκη του Δημητρίου Μόστρα, 2007) のワイン蔵で延々と続く主役たちの受難は恍惚感さえ入り混じったかのようでした。本作所収の「晩餐への招待」(“Πρόσκληση σε γεύμα”) でもエレベーターに閉じ込められたギャングが脱出しようとあがいています。下品さを突き抜け笑いさえ誘うほどの展開で、これ、ホントに巨匠へのオマージュなの? と少々疑問でしたが、最近『夜がはじまるとき』所収の「どんづまりの窮地」を読んで納得しました。
最新作として『スティーヴン・キングのように殺せ』(Σκότωσε σαν τον Στίβεν Κινγκ, 2023)なる長編を出しています。
 ディミトリス・ママルカスの新作『スティーヴン・キングのように殺せ』 https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=279363&return_url |
『後ろの座席で』(Στο πίσω κάθισμα, 2016) という暗示的なタイトルで家族再生の物語を紡いでみせたエフティヒア・ヤナキ(Ευτυχία Γιαννάκη, 第17回)は「ギリシャの神々」(“Έλληνες θεοί”) を書いています。
無関心、無慈悲に生きてきたスイスの若い看護士が、安楽死に臨むギリシャ人の老教授から身の毛のよだつ告白を聞き、ある野望を抱いてギリシャの灼熱の砂浜に向かいます。「神々」は複数形で、古代の神話、それも系統化されたオリュンポスにまします神々ではなく、もっと原始的なパーンやサテュロスがイメージされているようです。
中欧西欧の人間の目には、ギリシャはキリスト教国でありEUメンバーでありながら、まだまだ神秘の国と映っているようです(読みながら、デュ・モーリア「真夜中になる前に」でクレタ島の浜辺に現れる異形のものをちょっと思い出しました)。
意外だったのは、純文学志向だと思っていたカテリナ・マラカテ(Κατερίνα Μαλακατέ, 第22回)の登場です。不思議な長編『失った顔』(Χωρίς πρόσωπο, 2020) は猟銃暴発事故に遭った少年が顔を取り戻そうと奔走する話でした(思わず安部公房『他人の顔』を読み返してしまった)。
「白い家」(“Άσπρα σπίτια”) はキングへのオマージュだからと言って、森の中にたたずむ謎めいた小屋というわけではありません。ギリシアはボーキサイトが採れるので、アルミニウム生産が主要な鉱業の一つになっています。その大規模な精錬工場がデルフィの東南、コリントス湾に面して建てられ、その近くには従業員と家族向けの集合団地群が並びます。これが「白い家」と呼ばれているのです。
この工場に雇われてやって来た化学専攻の女性を主人公に、リアルな物語が始まるのですが、過去の言い伝え(北のディストモ村は第二次大戦中にドイツ占領軍による虐殺で知られる)を聞くうちに、よそ者である彼女の心が次第にねじれていきます。
この四人以外は初めて出会う作家ばかりで、ミステリ畑の外の人たちのようですが、ホラー専門とも限りません。それだけキングの作風と影響が多岐にわたるということなのでしょう。
ごく大雑把に分類しながら簡単にご紹介することにします。
まずはもちろんホラー作品ですが、外国人読者としては、ギリシャ土着の伝説を取り込んだものが特に面白く感じます。
ストレートに怖かったのはコンスタンディノス・ケリス「洗礼式」(Κωνσταντίνος Κέλλης, “Βαφτίσια”) 。旧家に帰省した母親と赤子が禍々しい儀式に巻き込まれ、森の奥で悪夢のような体験をします。
ディモステニス・パパマルコス「汝ら王に告げよ」(Δημοσθένης Παπαμάρκος, “Είπατε τω βασιλεί”) では村の愚か者と呼ばれていた大工が意外な能力で女怪ラミアと対決。古代ギリシャにまで遡る伝説を利用した伝奇作品です。この作家については、下でもう少し詳しく書きます。
フォークロア・ホラーとでも呼びたいこの二作に対し、ヨルゴス・ミタス「マリゴ夫人の最期の旅立ち」(Γιώργος Μητάς, “Η τελευταία έξοδος της κυρα-Μαριγώς”) はもう少しリアルで、周囲に横暴にふるまってきた老婆が最期に見る忌まわしい夢。救いのない「クリスマス・キャロル」の趣きです。
他に不思議な雰囲気を持つのが、アリス・スファキャナキス「波間の夢(第二巻)」(Άρης Σφακιανάκης, “Όνειρο στο κύμα (Volume 2) ”)。この作家は純文学の方で知られる人です。そもそも「波間の夢」というのは19世紀の著名な小説家アレクサンドロス・パパディアマンディス (Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 1851-1911) の短編作品で、島の貧しい牧童が、溺れかけた幼馴染みの美少女を助ける幻想的な物語です。
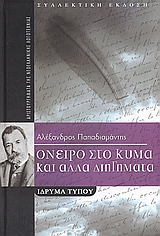 アレクサンドロス・パパディアマンディス『波間の夢、ほか短篇集』 2007、モティヴォ社。 https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=119611&return_url |
スファキャナキス作品はその骨格を借りながら、経済危機で建設を中断し幽霊屋敷と化した海辺の別荘群(すぐれて現代的)を舞台に、気味悪い真逆の結末をつけています。
以上では怪異の正体がまるで実在するかのように思わせますが、個人の生み出した妄想(?)に追われるのが、ヴァシリス・パパセオドル「芋虫」(Βασίλης Παπαθεοδώρου, “Προνύμφη”)。スランプから再起を図るかつての人気作家が虫の幻想に付きまとわれます。デビューした新人作家の背後に見えたものとは……いかにも作家自身の体験に基づいていそう。
似たような方向性なのが、イリヤス・マグリニス「箱の猫」(Ηλίας Μαγκλίνης, “Γάτα στο κουτί”)。「自分を監視してもらいたい、観察者がいてこそ自分の存在が確実になるから」との面妖な相談を受けた精神分析医が、逆に影響され取り込まれていく皮肉な話。タイトルは、観察者がいないと箱の中に猫がいるかどうかは確証できない、という心理学の思考実験から来ているそうです。
ニコラス・セヴァスタキス「命令」(Νικόλας Σεβαστάκης, “Εντολή”) は、世間の俗悪に染まるまいとする潔癖症の軍人が、島で知り合った女からある命令を受けます。骨格はクライムストーリーっぽいのですが、女に絡み取られる軍人の歪んだ心理が異様です。
サナシス・ヒモナス「夜の騒音」(Θανάσης Χειμωνάς, “Tapage nocturne”) では深夜に隣室から壁を叩く騒音が響き(《オーバールック》ホテルの槌音?)、主人公を妄想と現実の間で苦しめます。十年後アパート取り壊しで隣部屋が開かれた時、姿を現わす壮絶な光景とは?
あちらの世界から襲来する怪異とは真逆の、リアリズム犯罪ものもあります。
ジョン・D 「神の意志」(Τζον Ντ., “Θέλημα Θεού”) は本書の中で私が特に楽しめた作品の一つです。三十年間地道に働いてきた鉄道員が夢の叶うビッグチャンスに遭遇したとき、何が起きるのか? 読み進めるうちに時間が逆に語られていく点に気づき、結末まで引き込まれます。
人を喰ったこの名前はもちろん覆面作家のペンネームです。著者紹介のページにも情報は一切なし。
ニコス・ファルポス「敵(フライト204)」(Νίκος Φαρούπος, “Ο εχθρός (Πτήση 204) ”) は実際に1996年ギリシャとトルコが衝突しかけたイミア危機がモチーフ。フリゲート艦がカルパソス島沖へ発進しポートからヘリが飛び立つ冒頭は、強大な敵に立ち向かう冒険ものかと思わせますが、途中から海に潜む怪異の話になります。ヒギンズかマクリーンで始まり、ホジスンに終わる感じ。このねじれたストーリー展開がたまりません。
SF風の趣向が盛られたものとしてはディミトリス・ソタキス「Λは眠らない」(Δημήτρης Σωτάκης, “Ο Λ. δεν νυστάζει”)。科学者たちが村の男を森の小屋に連れ込み、不眠の実験を始めます。かつてべリャーエフのSF「眠らぬ男」に出て来るマッドサイエンティスト、ワグナー教授は自分の意志(研究のため一秒たりとも無駄にしたくない)で睡眠を放棄しましたが、こちらのΛはなぜ眠らないのか、が読む者の興味を引きます。
キング作品翻訳では第一人者(14作を翻訳)というミハリス・マルコプロス「少年」(Μιχάλης Μακρόπουλος, “Το αγόρι”) はタイトル通り、死期の迫った男が少年時代の自分と邂逅する話。珍しい設定ではないでしょうが、語られる内容にほろっと来ます。怪奇と恐怖の多いこの本の中では異色作ですが、《少年もの》にも強いキングの翻訳者ならではなのでしょう。『呪われた町』の冒頭からインスピレーションを受けたそうです。
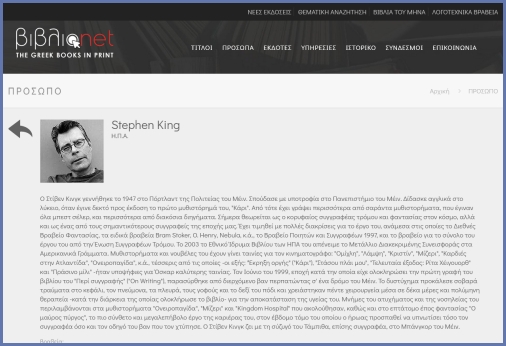 ■S・キングのギリシャ語訳リスト。 |
以上16作、たっぷりと堪能させていただきました。
◆小アジア戦役と血の掟
この16人の作家のうちに、書評やブログでしばしば見かけてぜひ読んでみたいなと思っていた話題作の著者がいました。ラミア退治の「汝ら王に告げよ」のディモステニス・パパマルコス(Δημοσθένης Παπαμάρκος)です。アンソロジーで出会ったのはまったく偶然ですが、せっかくなので件の本の電子版を購入し読んでみました。
今回エッセイの三冊目としてご紹介するパパマルコスの短編集『血』(Γκιακ, 2014)です。
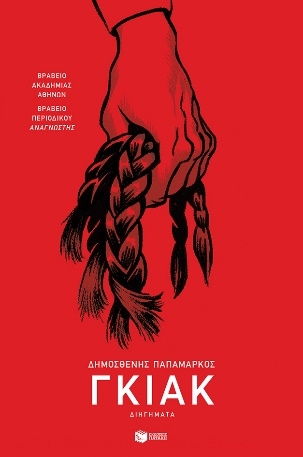 ディモステニス・パパマルコス『 パタキス社、2020(初版はアンディポデス社、2014)。 https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=248181&return_url |
九つの短編が収められていますが、目次には「ブクバルディア」、「タララルーラ」「ノッカー」などと辞書にもない不思議な題名が並びます。表紙絵も何やら不穏な感じ。題名の『血』ですが、ギリシャ語「エーマ」(αίμα)ではなく、アルバニア語「ギャック」(gjak)です。これは作品の登場人物たちがアルバニア系ギリシャ人であり、その風習《血の掟》が中心テーマになっているためです。
いずれの作品も時代は1920年代から30年代、第一大戦に続くギリシャ・トルコ戦争という血なまぐさい時期の前後で、ストーリーもまた異様です。雰囲気をいくぶんでもお伝えするため、巻頭作の「髪の房を切ってやろう」(“Ντο τʼ α πρες κοτσσίδετε”)を選んでご紹介しましょう(この題名もアルバニア語。広く知られたアルバニア民謡の一節だそうです)。
幼くして母を亡くした《私》は、何かとグズって手のかかる子供ですが、姉シルモに優しく育てられます。ある日そのシルモが姿を消し、家族は総出で村や森を捜索。翌日マスティックの木の下で血まみれの遺体を発見します。そばには切られた彼女の髪の房が投げ捨てられていました(本のカヴァー絵はここから)。《私》は憎んでも余りある犯人を見つけ出し必ず復讐する、と心に誓います(アルバニア人やギリシャのアルバニア系住民の《
やがて成人した《私》はトルコの小アジア戦線へ。戦場での残虐行為を目の当たりにしますが、そんな中で同じ村出身の戦友がトルコ人女性捕虜に暴虐を働いては髪の房を切り取っていくのに気づきます。
かくして《私》の血の復讐が始まります。
この作品に見られるある特徴は、他の所収作にも共通しています。
それは異様な「一人称語り」です。語り手は各作品で別人ですが、いずれも熱に浮かれたかのように饒舌にしゃべりまくります(まるで夢野久作作品)。
この語りがけっこう読みにくい。溢れる思いが止められず、ことばが滔々と流れていきます。そのため、引用符号をこまめに入れるのは面倒とばかりに省かれ、話し手が誰なのか不明のことがよくあります。また、埋め込まれた内側の話の中に外枠の語り手が突然感想を挟んだりすることさえあり、これ誰がしゃべってるんだろう?と立ち止まることが何度も。
しかもその中に、北部ギリシャ方言の訛りが混入してきます。
現代ギリシャ語の方言分類にはいくつかの説がありますが、よく知られた一つは北部と南部の違いです(標準語は南部方言に基づく)。大きな差異としては、北部方言ではアクセントのない母音が落ちることが挙げられ、そのため、全体にゴツゴツした印象を与えます。
特徴的なこの「一人称語り」ですが、緻密に計算して使われています。漠然と誰かに(読者一般に?)向けて話しているわけではありません。というのも、話の聞き手は最後の最後になって正体を現し、誰が誰に向かって、何のために語っているのかというストーリーの全体像がそこでようやく明確にされるのです。
「髪の房を切ってやろう」で言うと、語り終わった《私》は「自分はこんな人間だが、それでもいいなら……」と断ってから、聞き手にとんでもない提案をします(フーダニット・ミステリではないのですが、ネタバレはぎりぎりここまで)。
ハードボイルドの「一人称語り」が苦手でアレルギー療養中の私も、これにはビックリさせられました。
こういう仕掛けに乗って語られるのは、書名にも明示された「血」の物語。多くの作品にギリシャ・トルコ戦争の陰惨なエピソードが挟まれます。ただし、残虐なグロい描写が出てくるわけではありません。描写自体はドライです。それより恐ろしいのは、非情な現実が人の精神を蝕んでいく過程です。最悪の場合には、戦場での残虐行為が復員後も常態化して他人の苦痛にまったく疑問を感じない、という恐ろしい状況になります。
例えば、「ホジャが寺院に出るとき」(“Σα βγαίνει ο χότζας στο τζαμί”) では自身の武勲に酔う老人が、周囲がドン引きするのにも気づかず、戦場での忌まわしい行為を得々と自慢し続け、「ノッカー」(“Νόκερ”) では残虐行為で村からはじき出された元軍人が、その行為のエクスタシーから抜け出せなくなり、気兼ねなく陶酔できる仕事を求めます。
登場人物の多くがアルバニア系であるため、上に述べたような方言の訛り以外に、アルバニア語も頻出します(「お前は
アルバニアで薄気味悪い怪事件が展開するピーター・ブラッティ『ディミター』にも《ベッサの掟》として出てきます。
総人口一千万人を少し超えるギリシャ国民の中で、最も多い外国系住民は約三十七万人のアルバニア系です。割合は3.5%ほどですが、それに続くブルガリア系やルーマニア系は一桁少なくなります。居住地域で特に多いのは、アッティカ北部ボイオチア地方(エヴィア島の対岸)。作家パパマルコスはこの地域の出身で、幼時よりアルバニア系住民と接触することが多かったそうです。
アポストリディスやマルカリスのミステリ作品に登場するアルバニア人は本国から送り込まれた殺し屋とか、密入国して後暗い仕事に就く犯罪者といった役柄が多く、かなりステレオタイプ化されているように感じます。
逆に純文学作品では、近年移民ないし出稼ぎに来るアルバニア人の受ける偏見差別が描かれます。特に小中学校の国語教科書には、社会問題提起の意味を込めたジュブナイル作品が掲載されています。
例えば、リツァ・プサラフティ『茸の復讐』(Λίτσα Ψαραύτη, Η εκδίκηση των μανιταριών, 1999) では両親と引き離され車道で雑貨を売るアルバニア人少年と一人住まいの孤独なギリシャ人老婆が復活祭の日に慰め合い、マルラ・クリアファ『天国への道は遠い』(Μαρούλα Κλιάφα, Ο δρόμος για τον παράδεισο είναι μακρύς, 2003) では差別を受けるアルバニア人移民の少女と脚に障害を負ったギリシャ人の少女が手紙を通してお互いの悩みを打ち明けます。
しかしながら、『血』に描かれるアルバニア系の人々は、ミステリ特有の非情な犯罪者とか、あるいは近年の移民難民ではなく、古い時代に移住してギリシャの土地に根付き、祖国の《血の掟》を不文律として受け継ぎながらも、ギリシャ国民として希土戦争に駆り出された人々です。
ストレートな復讐譚の他にも、戦場・戦後の残酷物語や民話起源のようなホラーが並びますが、一番驚かされたのは五番目の「パラロギ」(“παραλογή”) でした。この名称はもともと民謡の一ジャンルを指し、民話のようなまとまったストーリーのある長めの歌のことです。一行が十五音節から成り、偶数番目の母音にアクセントが落ちる(イアンボス調)ひじょうに単純な詩形で、現代の民謡以外にも、中世ビザンツや近世クレタ文学の恋愛ロマンス、叙事詩、諷刺・教訓詩、民衆年代記、悲喜劇の多くがこの《
なので、短篇集である本書の半ばあたりで、作家によるオリジナル民謡が出てきた時はビックリ。内容はと言うと、死神カロンが村の娘の願いを聞き入れて、死んだ夫を墓から蘇らせてやる話です。
「じいさんが言ってた、おれらのこの土地にゃ、
死神が巣食って、やり放題。
だからよ、死んだ奴らは居つかずに、
我も我もと出て来やがる……」
土中で変わり果てた夫を目にして娘が怯えるシーンは、よく知られたパラロギの一つ「死せる兄弟」(“Του νεκρού αδερφού”) がモチーフになっているようです。(「死せる兄弟」は老母の哀願によって兄が墓から蘇り、遠国に嫁いだ妹を助けに行くストーリーで、帰途兄と妹が馬上で交わす身の毛もよだつ対話はドイツのバラード「レノーレ」に類似。)
『血』の強烈なテーマと異様な語り口は読者に好評で、2015年『
パパマルコスは1983年の生まれで、『シリコンの同胞たち』(Η αδελφότητα του πυριτίου, Αρμός, 1998) で第四回《イカロメニッポス賞》新人部門を受賞し注目されました。この賞は文学者グループ《幻想アルゴナウテス》とSF雑誌「プレアデス」が主催し、1996年から2000年まで続いた賞です(残念ながら賞も雑誌も短命)。本エッセイに登場した『ギリシャ幻想短篇集』の編者マキス・パノリオスや『王の木陰で』企画のキリアコス・アサナシアディス、『ノヴァ・ヘラス』のヴァソ・フリストゥも受賞しています。
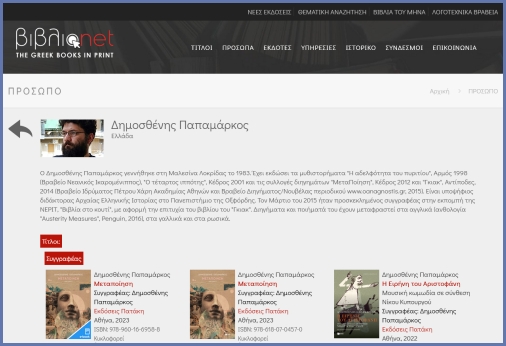 ■パパマルコスのビブリオ。 |
また、17世紀ヴェネチア支配期のクレタで書かれた恋愛ロマンス詩『エロトクリトス』のコミック本の脚本をランゴス(エッセイ第23回。実話ミステリ『血が匂う』)と共同で執筆もしています。
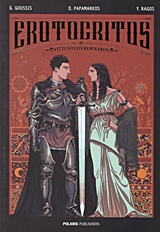 ヴィンチェンゾス・コロナロス『エロトクリトス』のコミック本。 英訳版。 https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=211190&return_url |
| 詩アンソロジーの英訳本Austerity Measures, Penguin, 2016にもパパマルコスの詩が収録されているそうです。 |
◆ 欧米ミステリ中のギリシャ人(29)―― ロティ・ペトロヴィッツのギリシャ人――
申し訳ないのですが、今回の「欧米ミステリ中の~」はタイトルと内容が少々食い違っています。ミステリ作品ではないうえに、作者は正真正銘のギリシャ人です。
しかしながら、貴重な日本語訳が出ており、ギリシャの歴史や現状を生き生きと伝えてくれる好作品なので、ご登場願いました。
その作家とは、児童ジュブナイル文学作家として名高いロティ・ペトロヴィッツΛότη Πέτροβιτςです。佑学社から『弟たちよ――戦火の中のギリシャで――』と『ぼくたち五人家族』の二作品が刊行されています(残念ながら、この出版社は閉業してしまったようです)。
二作とも子供が主人公ですが、「昔々あるところに~」ではなく、明確な時代と場所の中でスリル溢れる冒険が展開し、大人が読んでも楽しめる小説です。
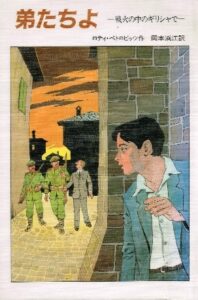 |
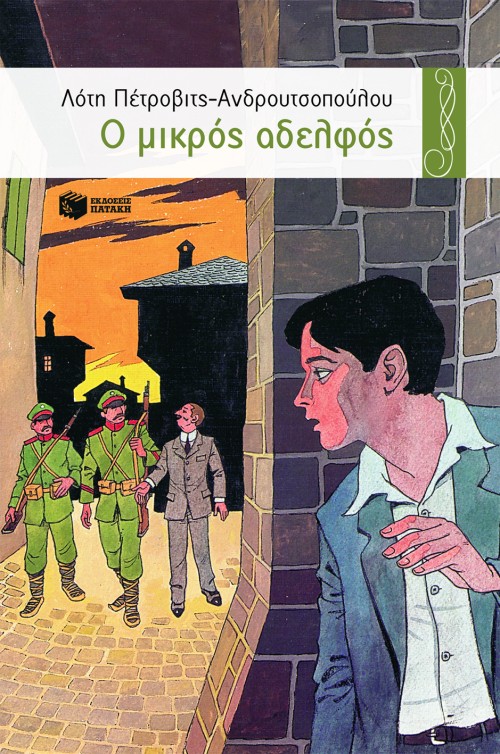 『弟たちよ』ギリシャ語原書 パタキス社、1991年版。 最新版ではカバー絵が変更されています。 https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=13197&return_url |
『弟たちよ――戦火の中のギリシャで――』(Ο μικρός αδελφός, 1976) はペトロヴィッツのデビュー作であり、すでに32刷を重ねるロングセラーになっています。
物語の舞台はギリシャ北部の町セレス(エッセイ第21回のスピロプル『ざわめく湖水』に出てきた町)。1913年の第二次バルカン戦争でブルガリア軍によりセレスは手ひどい打撃を受けますが、復旧する暇もなく、翌年にはドイツ・オーストリア同盟国と英仏露三国協商国の間で大規模な戦争が勃発します。
戦車や毒ガスが登場し、塹壕戦が主戦術となった第一次世界大戦です。
当初ギリシャは中立を掲げていましたが、協商国の軍隊がテサロニキに上陸。夜間の外出禁止令や灯火管制がしかれ物々しい雰囲気になっていきます。
1917年6月には中立派のコンスタンディノス王が亡命し、親英仏のヴェニゼロス政権の下でギリシャは協商側に立って参戦、同盟国側のブルガリアと戦火を交えることになります。ブルガリアの方は、バルカン戦争でギリシャと敵対し領土を取られた恨みを忘れず、国境を越えて侵攻しセレスを占領してしまいます。
このような激動の時代の中に放り込まれるのが主役兄弟、16歳のパヴロスと四つ下の弟アレクサンドロスです。
セレス住民はいくつかのルートを選んで避難を開始。パヴロス一家は鉄道で南へ逃れようとするのですが、弟アレクサンドロスが逃げ出した愛猫を追って下車、パヴロスも後を追いかけ二人は逃げ遅れてしまいます。町は孤立し、捕えられたパヴロスは強制労働のためブルガリアへ送られることに。
こうして、パヴロスの異国での壮絶な試練が始まります。
スリルに満ちた戦争冒険ジュブナイルもの、と言ってしまえばそれまですが、実は作者ペトロヴィッツ女史のお父さんの実体験にもとづくと知ると、感動がいっそう深くなります。献辞には「父は第一次大戦中、十七歳で敵の人質となり、この本の主人公と同じ体験をしました」とあります。
パヴロスはブルガリアへ護送される道中、そして強制収容所に入れられてから、様々な人に出会います。逃げ遅れた女子供、捕虜仲間たち、祖国解放を目指すレジスタンス。敵方にも捕虜を残虐に扱う兵士たちから、パヴロスの勤勉ぶりを認める収容所のブルガリア人将校、あるいは町の親切な書店の主人までいろいろなタイプがいます。ギリシャの小説(純文学のみならずヤニス・マリスのミステリ)でもおなじみの、敵軍に協力する裏切者の姿も見え隠れします(表紙絵のスーツ姿の人物)。
凄惨な体験を続けるパヴロスは自問せざるを得ません。「戦争が人間を残酷にしてしまうのだろうか。もとはいい人間でも、荒っぽい野獣のようになってしまうのは、なぜだろう」
歴史的には1918年協商側がブルガリアのソフィアに入城して和平条約を結び、大戦はひとまず終結することを後代の私たちは知っていますが、当のパヴロスは弟や家族との再会がかなうのでしょうか。
苛酷な経験を通してたくましくなっていく少年の精神と、非情な現実世界が並行して描かれ、最後までストーリーの緊張は切れません。
題名『弟たちよ』についてひとこと。
英訳ではThe Little Brother、もとのギリシャ語もΟ μικρός αδελφόςで、ともに単数形です。これをあえて『弟たちよ』としたのは(「たち」を複数形と取るにしろ、代表形と取るにしろ)、訳者岡本浜江氏の強い思いからだと思います。パヴロスとアレクサンドロスは二人兄弟(他に姉がもう一人)なのですが、パヴロスは行く先々で戦火で苦しむ子供たちに出遭い、弟に対するように愛情を注ぎます。それもギリシャ人だけではなく、見知らぬセルビア人やブルガリア人の子どもにまで。「弟と(急病で避難できない)従弟とどこが違う?」、「弟も町の仲間も同じことなのだ」との心の声が何度も繰り返されます。
最終シーン、駅の雑踏で迷う幼いブルガリア人を見かけたパヴロスの叫びには、作者の思いのたけがこめられています。
本作はギリシャの「女性文学チーム賞」(Bραβείo της Γυvαικείας Λoγoτεχvικής Συvτρoφιάς. 1955年に創設され、特にギリシャ児童文学普及を目的に活動する団体の賞)を受賞しています。
『ぼくたち五人家族』(Σπίτι για πέvτε, 1987) のほうは打って変って、発表当時の八十年代が舞台です。『弟たちよ』同様すでに32刷、ギリシャの読者に愛されてます。
 |
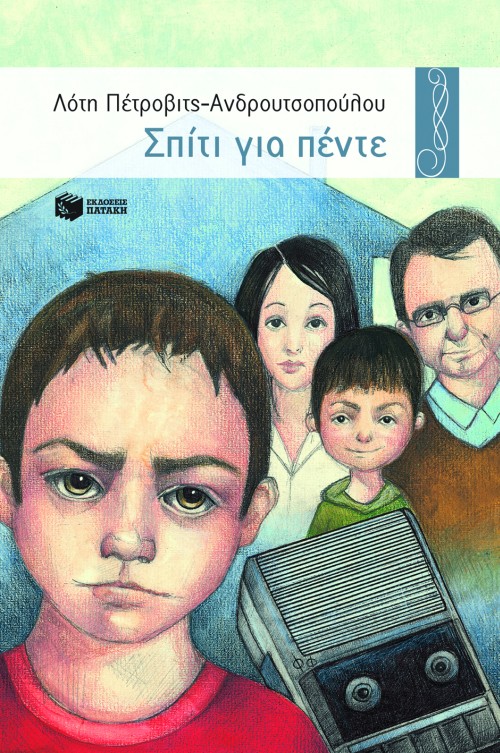 『ぼくたち五人家族』ギリシャ語原書 パタキス社、2011年版。 https://biblionet.gr/titleinfo/?titleid=12213&return_url |
中学生フィリポスはアテネで母アンナと二人暮らし。離婚した父はドイツで新しい家庭を持っていますが、母にも新しいパートナー、オレステスが現れます(前妻は事故で死去)。二人は再婚し幸せに満ち溢れますが、問題はオレステスの連れ子アレスです。九歳のわんぱく盛りで、何かとフィリポスをイラ立たせます。大人の眼から見れば、新しくできた兄に興味津々で後を追いかけているだけなのですが、フィリポス本人にとっては、道具を壊されたり、ガールフレンドとの仲がこじれる原因を作ったりと鬱陶しいかぎり。で、アレスについたニックネームは《怪獣》。
おまけに、両親はそれぞれの実子に厳しく(「いじめないでね。あの子には愛情が必要なのよ」「新しい兄ちゃんに生意気な口をきくな!」)、兄弟はなんで自分にばっかし、と嫉妬し合います。
血の繋がりのない二人兄弟を中心に、けっこう複雑な家庭の日常が語られていくのですが、おもしろいのは語りのスタイルです。
「ぼくはきょうから『しゃべる日記』をつけることにした」と始まる通り、フィリポスは贈り物のカセットレコーダーを《フィロン(親友)》と名付け、日々の思いを吹き込んでいきます。漠然と読者一般に語るのではなく、(想像上の)親友への告白という状況がはっきりしており、その正直さを読者も受け入れやすいのがミソです(パパマルコス『血』とは別種の「一人称語り」の有効活用法ですね)。
ところが、弟アレスもこれに対抗して、自分のレコーダー《フィフィ》に録音を始めます(微笑ましい)。
かくしてストーリーは立場の違う複眼の語りとなります。
フィリポスが「アレスは甘ったれの《怪獣》だ」と不満をぶちまけるかと思うと、アレスは「フィリポスはやたらぼくを怒る。でもかわいいクリスチナと会うとニコニコし始めるんだよ」。
あるいは兄弟喧嘩の後、フィリポスは部屋で母アンナに説教されますが、無邪気なアレスには「アンナが寝室で(ぼくに聞こえないように)、フィリポスになにかいっていました」と映るだけ、という具合です。
それだけではありません。母アンナと父オレステスも、姉や親友相手に手紙や電話で、二人兄弟の不仲を心配する心境を打ち明けます。
こうして、ささやかな四人家族の物語でありながら、《ポリフォニー》によって、各人の想いのすれ違い、もどかしさや切なさがスペクタクルのように描き出されます。
題名は「五人」じゃないかって? ご心配なく。ちゃんと五人目も登場します。
話が大きく動くのは、《フィロン》の盗難(親友の誘拐に等しい)。そして突然のアレスの交通事故(緊迫したこの場面は中学校の国語教科書にも採録されています)。これらの事件を通じて、不器用に遠慮し合いうまく距離感の取れない二組の親子が、はたして信頼しあえる家族となっていくのか。最後まで見守らずにはいられません。
人間関係とともに描写されるギリシャの一年も魅力です。「
『弟たちよ』は第一次大戦を物語に取り込んでいましたが、こちらで目を引くのは同時代のある社会の出来事です。
アレスが《フィフィ》にこんな風に吹き込みます。
「新しい法律ではお母さんも結婚したあと名字を変えなくてもいいそうです」
その結果、母アンナの身分証には夫の姓ではなく、父方の姓「パパダキ」が登録されます(ちなみに、ギリシャ人の姓は男女で形が若干異なり、男性「パパダキス」(Παπαδάκης)に対して、女性「パパダキ」(Παπαδάκη)となります。ただし、外国語に翻訳する場合は、誤解を避けるために区別しないことが多いようです。例えば女優「イレーネ・パパス」(Irene Papas)は、実はギリシャ語で「イリーニ・パパ」(Ειρήνη Παππά))。
この夫婦別姓の法律が施行されたのは作品発表の数年前、1983年のこと。加えて、子供の姓も夫婦の話し合いによりどちらの姓からも選べるようになりました。男女同権を目指す当時の流れの中で実現したそうです。保守的なイメージのあるギリシャですが、意外にも先進的です。
ついでながら、2008年の法改正によって、結婚後も夫の姓をハイフン付きで付け加えることができるようになります。そこで作者の場合も、「ロティ・ペトロヴィッツ=アンドルツォプル」(Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου)となり(ご主人の姓はアンドルツォプロス)、著書にもこちらが表記されています。
こういった社会的動向がうまく取り込まれるのも、ペトロヴィッツ作品の魅力です。
『ぼくたち五人家族』は1989年にパドヴァ大学から「ピエール・パオロ・ヴェルジェリオ全欧州児童文学賞」(Pier Paolo Vergerio European Prize for Children’s Literature) を受賞しています。1992年にはギリシャのMegaチャンネルのテレビシリーズにもなったそうです。
作家の経歴について少し書いておきます。
ロティ・ペトロヴィッツ=アンドルツォプルは1937年にアテネで生まれました(『弟たちよ』主役のモデルとなった父親は北部セレスの出身)。英文学を学び、英仏伊語に通じています。27年間、移民難民支援の国際組織で働きますが、並行して児童文学の研究と執筆にたずさわってきました。著書は『弟たちよ』を始めとして50冊を超え、翻訳書も4冊(ロアルド・ダール 『おばけ桃が行く』など)。コラージュ、挿絵の腕も趣味以上で、自著6作のカバーを手掛けています。
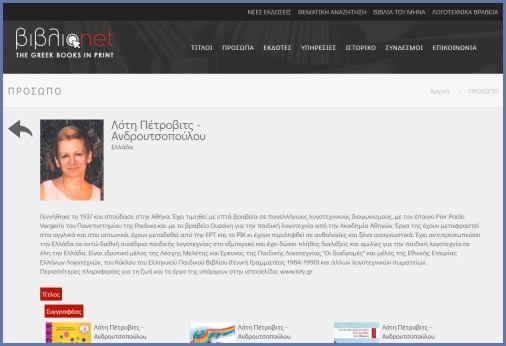 ■https://biblionet.gr/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF/?personid=3151 ■ロティ・ペトロヴィッツ=アンドルツォプル著作リスト |
アテネ学士院ウラニス財団児童文学賞(1984年)、国家児童文学賞(1999年)など9つの文学賞に輝きます。1978年からは3年間国際児童図書評議会(IBBY)のギリシャ支部の運営に関わり、2000年から8年間その代表を務めています。
現代ギリシャの児童・ヤングアダルト文学を代表する作家と言えましょう。
なお、『弟たちよ』『ぼくたち五人家族』翻訳者の岡本浜江氏は、ミステリ関係では《修道士カドフェル・シリーズ》の『修道士の頭巾』や『氷のなかの処女』を訳しておられます。
| 橘 孝司(たちばな たかし) |
|---|
| 台湾在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっともっと紹介するのがライフワーク。現代ギリシャの幻想文学・一般小説も好きです。 《イカロメニッポス賞》の名称のもとになったルキアノス「イカロメニッポス(空を飛ぶメニッポス)」。「本当の話」と並ぶ西洋SFの元祖です。宇宙に興味津々のメニッポス君が哲学者(同時に科学者)たちの言説を信じられず、自らイカロスの翼を改良して天空探索へと飛翔する奇抜なストーリー。最後のオチが笑えます(エピクロス派とストア派がライバルというのがミソ)。■ルキアノス『本当の話』。「空を飛ぶメニッポス」所収。 |
| 【べリャーエフ『眠らぬ男:ワグナー教授の発明』。《ソ連SFの父》もいつか本エッセイにも登場することになりそう。】 |
| 【ホジスン『海ふかく』。海に潜む怪異の百鬼夜行。作家は完全に憑りつかれてます。】 |
| 【『ディミター』。『エクソシスト』の作家が編み出すアルバニアとイスラエルでの奇っ怪な事件。この二つの国が舞台になったのはなぜか? 驚愕のたくらみは最後に明らかになります。】 |
【エリス・ピーターズ《修道士カドフェル・シリーズ》の『修道士の頭巾』『氷のなかの処女』】 |