今月は豊作の月。通常の月だったら、トップを張れる作品が幾つもある。
そんな豊作の中だが、本欄は、やはりこれから行ってみたい。
■レオ・ブルース『レオ・ブルース短編全集』
ファン垂涎ともいえる短編集だ。
『レオ・ブルース短編全集』は、英国黄金期を代表するレオ・ブルースの文字通り、全短編を収録。既訳があるものはわずかで、大半が日本の読者に初お目見え。さらに、すごいのは、図書館で発掘された未刊のタイプ原稿から直接翻訳した11編 (うち世界初紹介作9編) を含んでいるところだ。海外のマニアもこれには切歯扼腕しているに違いない。さらに、1992年、当時知られた28編を短編集にまとめたバリー・A・パイクの序文、図書館で原稿を発掘したカーティス・エヴァンズの文章まで収録されているのだ。
全40編。そのうち14編がビーフ (巡査部長、後に私立探偵) 物だ。11編がグリーブ巡査部長物。400頁足らずの本に40編だから、各編ショートショートといってもいい長さだが、全体の多くを占める謎解き物も、単なる謎解きパズルのようには書かれていない。ビーフ物には、ビーフの機嫌のいい語りがあって、ときにギラッと意外性がきらめく。
意外な殺人方法と手がかりを扱った「手がかりはからしの中」、大胆なトリックでニヤリとさせる刑務所の消失事件「休暇中の仕事」、小人症の芸人殺しという素材を生かした「棚から落ちてきた死体」など、ビーフ物は、総じて出来がいい。最後の一行で犯人を言い当てる「鈍器」、相思相愛夫婦に起きた殺人を扱って異色の「一枚の紙片」、クリスマスミステリ「ビーフのクリスマス」、筋のいいアリバイトリック「死後硬直」などなど。各短編から、ビールやダーツが大好物で自己顕示欲旺盛のビーフの個性が垣間見られるのもお楽しみ。
クリーブ物では、短い中に秀逸なアイデアを投入した「逆向きの殺人」、推理に華のある「単数あるいは複数の人物」「沼沢地の鬼火」、毒殺トリック「強い酒」などが魅力的。
本格物の短編の間に、クライムストーリーが挟まれる構成も楽しい。給与の強奪を目論む警部のクライムストーリー「犯行現場にて」、鋭いオチが潜む「犯行現場」など佳作も多く、殺人者はへまをする風の短編もいいアクセントになっている。
一編ごとの短さを考えるなら、ウィットに富んだ大変クォリティの高い短編集といえるだろう。
古くから〈レオ・ブルースファンクラブ〉を主宰するなど、訳者の小林晋氏のブルースにかける情熱がなければあり得ない企画だった。ファンの夢を形にした版元にも感謝したい。
■ライオネル・ホワイト『気狂いピエロ』
ゴダール監督の代表作でもある『気狂いピエロ』の原作がノワール作家ライオネル・ホワイトの作品と知って驚いた。しかし、映画には原作名もクレジットされていないらしい。そういえば、映画には殺人と逃避行のストーリーはあったかもしれないが、詩的で哲学的な言語に包まれてよく判らない映画だった。
その原作というのは、本邦初訳の『気狂いピエロ』(1962) 。原題Obsession。おりしも、本年、50周年2Kレストア版が劇場公開されるということで、本書も企画賞ものだろう。
おれは、やつらがここに到着するまで、椅子にすわって文章を書いている。6か月前、アリーと知り合ってからのことを。
おれ、コンラッド・マッデンは、38歳。2か月以上も職を失っており、妻と大喧嘩した夜、ベビーシッターのアリーという17歳の娘と知り合い、彼女のアパートで関係をもつ。翌日、ナイフで刺された死体が彼女の部屋に転がっていた。二人は部屋にあった1万6000ドルを手に警察や組織を恐れ、逃亡の旅に出る。
本作がノワールの形式を意図的に破っているのは、ファム・ファタル役のアリーが17歳という点だろう。彼女はほんの子供のように見え、17歳という年齢も自称で実はさだかではない。肌は透きとおるに白く、横長のアーモンド型をした瞳は信じがたいほど鮮やかなブルー。
解説の吉野仁氏も指摘しているが、アリーの設定は、明らかに、ナボコフ『ロリータ』、キューブリック監督による映画版を意識したものだろう。(ホワイトは、キューブリックに『
二人は結婚の式を挙げ、別の名を手に入れる。自分は完全に気が狂っているとマッデンは疑うが、アリーに深く没入する。「あいつは子供だが、女でもある」「アリーはまるでものを知らない。それでいて、すべてを知っている」
二人は、サウスカロライナ州のエイケンという街で、富裕な市民というしっかりとした身元を手に入れ平穏な二か月を手に入れるという幕間が面白い。さらに、物語が進むと、ラスヴェガスでの現金輸送車襲撃プランまで出てくるのは、同種の小説の第一人者ホワイトらしいところ。ただ、後半に行くにつれ、アリーの未成熟・不定形の魅力が減じているようにも感じる。
本書は、中流の郊外生活者が魔女に誘われ、とことん堕ちていく話でもある。堕ちていく先には破局しかないが、堕ちることの甘美さも、またこの小説は描いているのである。
■ジョルジュ・シムノン『運河の家 人殺し』
ジョルジュ・シムノン初期の「純文学」志向の
純文学志向の作品だが、いずれも犯罪と謎を基調としたものであり、本書をミステリと呼んでも一向にかまわないと思う。
『運河の家』(1933) は、ベルギーを舞台に、両親を亡くした都会育ちの少女エドメがまだ見ぬおじの家に赴く場面からドラマは始まる。おじとおばの家(ヴァン・エルスト家) は広大な灌漑地を有する豪農で、6人のこどもがいた。エドメが着くや否やおじが急死。長男のフレッドがおじの後を継ぐが、次第に不幸な運命が一家に襲いかかる。
主にフラマン語が話される一家では、フランス語しか話せないエドメはよそ者でしかない。医者になることを志している彼女は、一家にうちとけたようにも見えず、「あんたたちみんな退化しているんだわ」と貧しく病んだ血に嫌悪を示す。しかし、次第にヴァン・エルスト家の次男 (ジェフ) のみならず、長男の心をとらえていき、やがて悲劇が到来する。
エドメがヴァン・エルスト家のいとこたちの心を掻き乱していくのだが、少女の内面は徹底的に明らかにされない。エドメは、大頭を揺らし黙々と仕事に精を出す「村一番の馬鹿者」ジェフに、「私が欲しいのは殺しのできる男」「何か危ないこと」をやってほしいとそそのかし、その後も不可解な行動を取り続けるのだが、彼女はいったい何を考えているのか。小悪魔というのとも違う。ジェフに解体された栗鼠をみたときの戦慄や昂りに捉えられているのか、馬鹿者の心を捉え操ることに酔っているのか、は明らかにされない。
この徹底した内面の欠如というか隠ぺいが本作品の大きな特徴だ。
フランドルの灰色の空、数年の時間をかけて、傾いていく一家の生活が季節感溢れる筆致で丁寧に描かれ、運河を行く船の沈没といった事件を通じて、悲劇への歯車は廻っていく。とにかく、この内面がうかがい知れないエドメの像が鮮烈で、この作品自体も創作意図については沈黙を続けるスフィンクスであるかのようだ。陰鬱で救いのない結末が待つが、物語を覆うピンと張り詰めた緊張感は忘れ難い。
続いて、『人殺し』(1937) は、冒頭から殺人事件が起きる。舞台は、オランダ。アムステルダムから少し離れた街で暮らす主人公クペルスは、中年の開業医。地域の医療に精励し、夜は街のブルジョアが集まるビリヤードクラブでゲームに興じ、月に一度、学会への出席のためアムステルダムに出張するという判で押したような生活を続けている。クペルスは、出張の折にピストルを購入、不倫中の妻と友人シュッテルを密会場所で撃ち殺す。とここまでは、よくある話かもしれない。クペルスは家に帰ると若い女中ネールをベッドに誘い、自らのものにしてしまう。ところが、ネールは、数か月にもわたって、誰にも知られずに、自らの愛人を部屋にかくまっていた-と話が転がっていくと本作品が尋常ならざる小説であることが了解できる。
死体は運河に没し、なかなか発見されないが、クペルスは、世間が自分のことをどう思っているか、妻の不倫を密告する手紙を自分に送り付けたのはだれなのか、と思い悩む。やがて、死体が発見されて…。
クペルスは、自らの殺人の罪には、まったく悩むことがない。こうした点で、ジム・トンプスンの主人公の系譜を先取りしているともいえるが、一方で、クペルスは、疑心暗鬼の状況に押しつぶされて次第に狂気に陥っていく。周囲がすべて自らに牙を向いているように思える医師に安息のときは訪れるのか。
殺人犯の狂気に陥っていく過程をサスペンスフルに描いて、『運河の家』に比べて、まだ「もてなしのいい」小説といえるかもしれない。彼が殺人を犯した真の理由は、終幕で明かされるが、読者の首元にも一瞬寒い風が入り込むことだろう。
■モーリス・ルヴェル『地獄の門』
モーリス・ルヴェル『地獄の門』は、日本のオリジナル編集で、既訳書と重複のない36編を新訳で収録。
ルヴェルは、大正末から昭和初めにかけ我が国にも紹介され人気を博したフランスの作家。夢野久作などは「今まで読んだ探偵小説の中でも一番好きなのはポオとルベルである」と書いているくらい。その後、急速に忘れられた作家になっていくが、今世紀に入ってからは、『夜鳥』が創元推理文庫から出ており、本書の編訳者による私家版の発行もあって、現代の読者にも関心をもつむきが多い。
ルヴェルの短編は、乱歩や久作が愛したことからも判るとおり、おおよそ明るい話はなく、人間の暗部を
冒頭の「
ルヴェルが描くオブセッションは、列車の同乗者への恐怖(「恐れ」)、死体の手首(「狂人」)、性愛(「金髪の人」)、自らの子(「どちらだ?」) 等、それこそ短編の数だけあるが、不倫と復讐を組み合わせたものも多い。中でも、やや軽妙なのは「足枷」、残酷なのは「古井戸」だろうか。
後年の作になると、初期のルヴェル調からちょっと離れたようなギミックのある恐怖小説「誰が呼んでいる?」、気球の冒険行の残酷な結末を描いた「高度九千七百メートル」などがあり、作風を広げる試みだろうか。
ともあれ、ルヴェルの作、読めば、残酷な結末が待ち受けているとは知っていても、次々と読まずにはいられない魔力を秘めている。続刊を待ちたい。
■エツィオ・デリコ、カルロ・アンダーセン『悪魔を見た
本巻は、戦後、欧州圏のミステリを紹介しようと精力的に翻訳活動を行った吉良運平による翻訳セレクション。実作家でもあった吉良運平の翻訳における業績は、横井司氏の解説に詳しいが、三井物産駐欧社員であった吉良は、トルコのイスタンブールで入手した全50巻の現代欧米探偵小説傑作集(スイスで刊行されたドイツ語訳)を全巻読破し、そのうち優れたものをオリエント書房〈現代欧米探偵小説選集〉全30巻として刊行する企画の中心者だった。この選集は、本書収録の『遺書の誓ひ』を出したのみで中絶したという。そのリストは、本邦未紹介のヨーロッパの作家が多くを占め、もし30巻本が刊行されていたら、英米仏一辺倒の戦後の翻訳シーンも変わっていたかもしれない。
エツィオ・デリコ『悪魔を見た
大衆食堂を経営する養父母のもとで育てられた孤児マリイは、18歳の娘。3人の実の娘を抱える養父母は、食い扶持を減らすために、バルバザンの「泉ホテル」に奉公に出される。マリイは、三等車に乗り、孤独な旅をするが、バスへの乗り換えの地で、言葉巧みな商店主にマフラーを売りつけられ、バルバザンへのバス代を失う。「泉ホテル」では、徒歩で辿りついた娘を迎えるが、その夜にホテルの逗留客の殺人事件が発生。続いて、唯一の目撃者と思われたマリイも殺害されてしまう。
心細くも異郷に送られる娘を描いてひんやりとした巧みな導入。さらに、殺された逗留客の周囲には動機も見当たらないという不可思議。捜査に当たるのは、リシャール警視だが、こちらは、酸いも甘いも嚙み分けたメグレ風の警察官。地道な捜査で次第に捜査の輪は絞られ、犯人逮捕に向かうが…。
リアリズムを重視した捜査小説なのかと思われたが、巧みな叙述と密接不可分なトリックが織り込まれており、唸らされる。ミステリではよく「もし~だったら、~だろう」という文章が読者の注目をひくために出てくることがあるが、読後にこの構文がここまで腑に落ちるケースは稀だろう。ペーソスを交えた語り口もよし。細かな点を除けば、本格派も満足させる佳品。
『遺書の誓ひ』(1938) は、デンマークのカルロ・アンダーセンによる作。本作がデビュー作で、「北欧犯罪コンクール」に一等入賞したという。
デンマークの作家ながら、本編は、英国を舞台にした純英国産風お屋敷ミステリであるのが、異色なとことろ。
主役は、スター新聞の犯罪記者スチュアートと私立探偵ウィリアム・ハモンドで、ハモンドは警察の信頼も篤い名探偵。公爵であるフィンスベリー卿が温室で殺害され、受け取ったばかりのダイヤモンド17個が紛失した。事件の背景には、かつての戦友たちの間で結ばれた「戦争遺書」――死亡により財産の三分の二が基金に繰り入れられ、生き残った最後の者が基金を継ぐ――も絡んでいるようだ。
誰もが嘘をついているような尋問、第二の殺人、家の間取り図、関係者を集めての謎解き。英国探偵小説の香りが十分だが、探偵の解明は、起こったことの解説に終始し、解明に至る論理や手がかりは十分とはいえない。賞が与えられた所以は、輸入に限られていた英国風謎解き小説がデンマークで生まれたところが評価されたことだろうか。
■加藤朝鳥訳/セクストン・ブレイク・コレクション1『
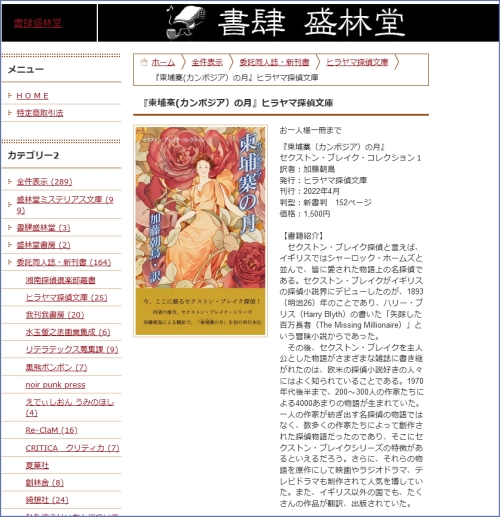
ヒラヤマ探偵文庫19は、セクストン・ブレイクの登場。
19世紀末に英国で登場し1970年代後半まで多数の作家により書き継がれたこのセクストン・ブレイク探偵物。本書解説(湯浅篤志) によると、そのすべてを数えると、200〜300人の作家たちによる4000余の物語になるという。目の眩むような長大シリーズだ。ブレイクに関しては、例えば、権田萬治編『海外ミステリー事典』にも立項されていないが、正統なミステリ史や批評からは無視されていたとしても、映画やラジオドラマ、テレビドラマにもなり、大衆の探偵物についての原イメージとして浸透していたに違いない。
我が国でも、ブレイク探偵物は、輸入され、例えば1920 (大正9)年の1年間に、セクストン・ブレイクの写真小説として、「新青年」に、6編が翻訳されたという。
本作『
■浅倉久志編・訳『すべてはイブからはじまった ミクロの傑作圏』
国書刊行会の〈ユーモア・スケッチ大全〉が第4巻にして最終巻。特に『ミクロの傑作圏』収録短編は「遊歩人」という雑誌に2002年から2004年まで連載された後、オンデマンド出版のみの発刊だったため、多くの人 (筆者も) にとって蔵出し作品集といえよう。
最終巻にも、色々なタイプのユーモア作品が満載。カフェテリアでの無料提供のロールパンを断ったため、途方もない成り行となるフレッド・トービイ「カフェテリア・コンプレックス」、日常のレストランでの不満の「真相」を明らかにするジョージ・コーフマン「給仕学校」、小学校の算数の問題に出てくるA、B、C の性格分析を行うスティーヴン・リーコック「ABC物語」など、日常のちょっとした違和や不満を種にして奇想をふりかけユーモアに膨らませていく手並み鮮やか。その他、カキの恋愛を描いたフランク・サリヴァン「みにくいモラスクの冒険」、会話による奇天烈家族の肖像ロバート・M・ヨーダー「家族ゲーム」、ホテル二階消失事件の顛末を扱ったロバート・ベンチリー「魅惑の犯罪」といったナンセンス編も楽しめる。
『ミクロの傑作圏』に入ると、〈ユーモア・スケッチ〉の幅がさらに広がり、より多彩な短編が楽しめる。短編小説の傑作はなぜ不幸や悪徳ばかり描くのかという疑問に端を発するスティーヴン・リーコック「多幸小説のすすめ」、エドワード・D・ホックの珍しいショートショート「最後のユニコーン」、異様な緊張感漂う小傑作スタンリー・クーパーマン「グランド・セントラル駅にて」、黒人の家庭の挿話を描いて心に残るジョン・オハラ「人はパンのみにて」、旅先のエロティック奇譚ウォルドー・フランク「一夜の宿」、奇想SF風のプライス・デイ「午後四時」、サスペンスから奇妙な心地よさに転化していくアーチボルド・マーシャル「バス」まで、編訳者の幅広い渉猟が窺える。スマートな艶笑譚がいくつも見られるのも本巻の特徴か。
浅倉久志という名編訳者が「発見」し、渉猟し、訳した〈ユーモア・スケッチ〉全編がここに4巻本としてまとめあげられたことは、ソフィスケートされた笑いを求める読者への無類の贈り物だろう。
| ストラングル・成田(すとらんぐる・なりた) |
|---|
 ミステリ読者。北海道在住。 ミステリ読者。北海道在住。ツイッターアカウントは @stranglenarita 。 |