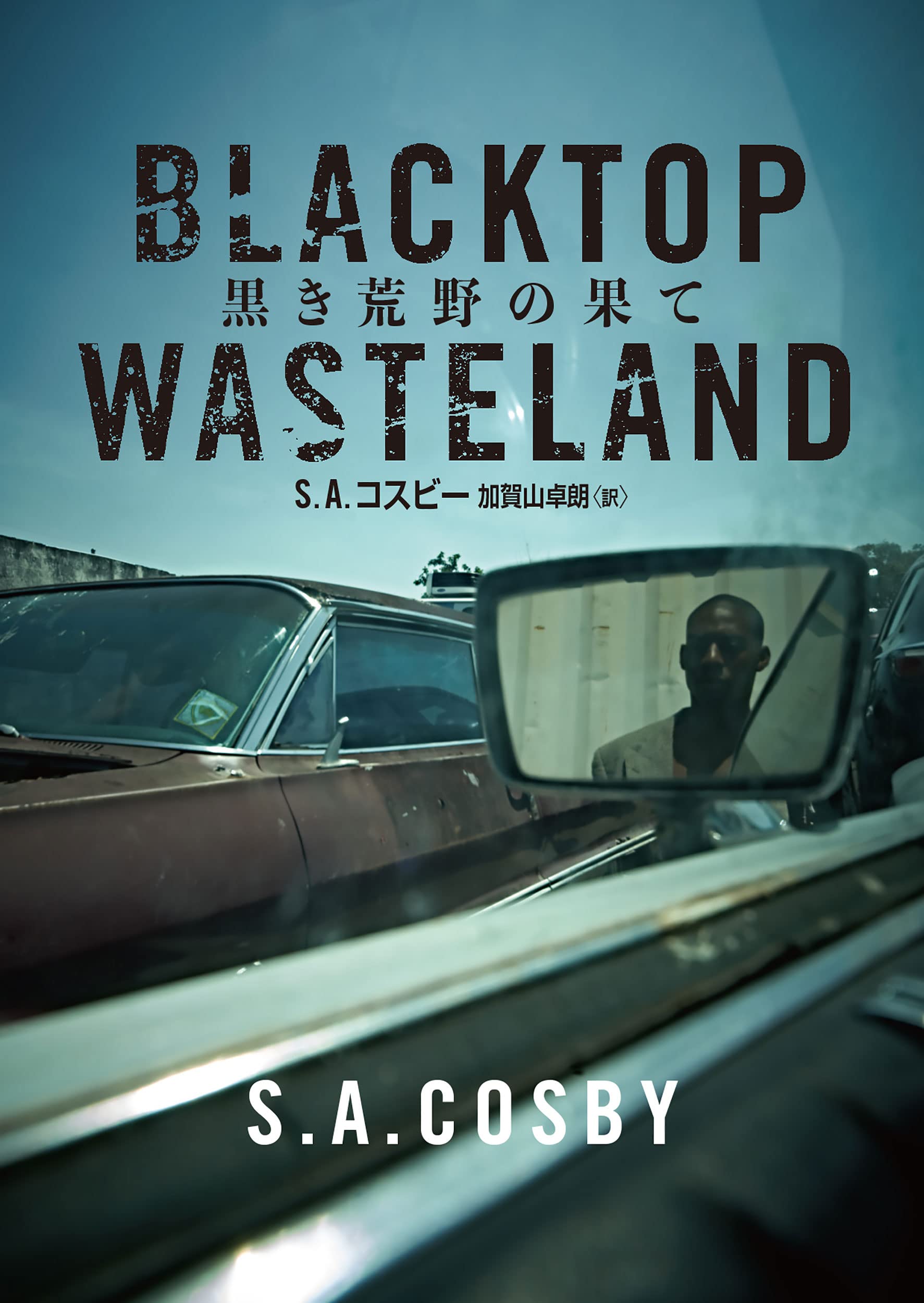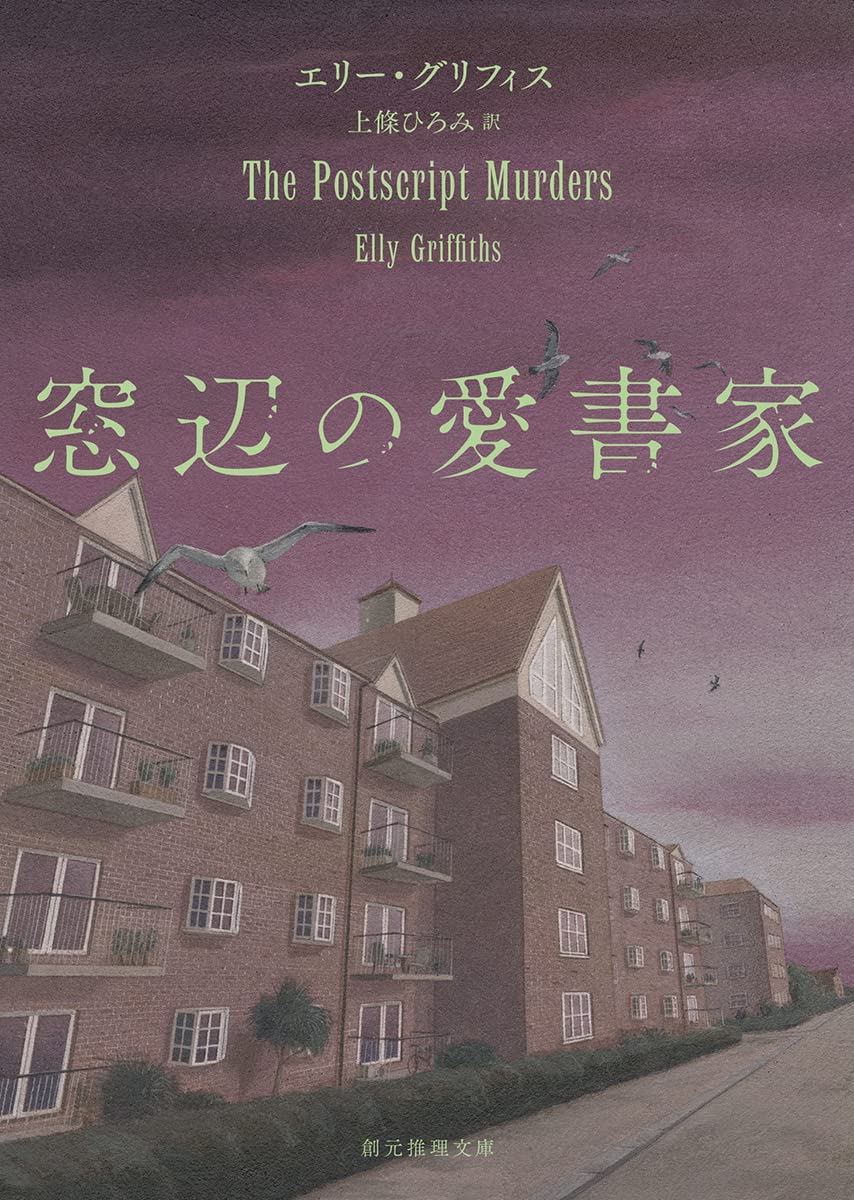田口俊樹
先月の七福神で、酒井貞道さんと杉江松恋さんが取り上げておられた『彼女は水曜日に死んだ』(リチャード・ラング著/吉野弘人訳/東京創元社)を読みました。収録10篇、描かれているのがどれも犯罪というところは共通していますが、実にヴァラエティに富んだ短篇集です。
味わいはミステリーというよりジュンブンですが、年々歳々ジュンブンに疎くなっている――ストーリーを追うことが小説を読む一番の愉しみになっている――私でも大いに心地よくすこぶる愉しく読みました。
比喩の巧みさ、人間観察の的確さ、無駄のない描写の鋭さ、どれも堪能しました。個という特殊を突きつめることで普遍に通じるというのが、私、ブンガクの醍醐味だと思っているのですが、どの作品でもその醍醐味を味わえました。でもって、なにより心に残ったのが主人公の住む社会は取りも直さずわれわれみんなが住む社会だということ。さらに言えば、われわれは今こんな社会に生きてるんだ、と改めて気づかされたところでした。
ま、あたりまえと言えばあたりまえなんだけれど、その気づきがちょっとほろ苦い。なのに全篇を通して読みおえたときには、ほっこりと心が温かくなっている。ほろ苦くも温かい。そんな読後感。宝石箱を覆したような(なんちゃって)まさに珠玉の短篇集です。
〔たぐちとしき:ローレンス・ブロックのマット・スカダー・シリーズ、バーニイ・ローデンバー・シリーズを手がける。趣味は競馬と麻雀〕

白石朗
突発的に伊豆へ一泊二日の小旅行をしてきました。集中工事の東名を抜け、沼津で海鮮丼を食べてから半島入り。韮山で反射炉も見学せずに地ビールを買い、伊豆の国市の大河ドラマ館で八重さんや千鶴丸の衣裳を眺めてきました。翌日は数年ぶりに河津の爬虫類動物園 iZooへ。園内もずいぶん変わっていました――イグアナと毒ヘビが増えていて、通路をリクガメがわがもの顔で歩き、ミシシッピアカミミガメの大きな池が増えていて、ヒャダインが歌うテーマソングの一部がエンドレスで流れていたり(→こちらです)。
楽しい二日間でしたが、日没後の街灯ひとつないカーブ多めの山道の天城越えは、ふだん街なかしか走らない身なので緊張しました。「山が燃える」どころか、燃えたあとの炭みたいな暗さなんだもん。
〔しらいしろう:老眼翻訳者。最近の訳書はスティーヴン・キング&オーウェン・キング『眠れる美女たち』。〈ホッジズ三部作〉最終巻『任務の終わり』の文春文庫版につづいて不可能犯罪ものの長篇『アウトサイダー』も刊行。ツイッターアカウントは @R_SRIS〕

東野さやか
届いたばかりの『石獅子探訪記 見たい、聞きたい、探したい! 沖縄の村落獅子たち』(若山恵里/ボーダーインク)をぱらぱら読んでいます。タイトルになっている石獅子とは、その名のとおり、石を彫ってつくった獅子のこと。沖縄の家の屋根や建物の入り口に置かれているシーサーをご存じの方は多いと思います。石獅子はその原型とも言われているそうで、かつては集落の入り口に守り神として置かれていて、村落獅子という呼び方もあるとのこと。『石獅子探訪記〜』は、各地に残るそんな石獅子を訪ね歩き、地元の方から由来や逸話などを聞き取り調査をし、それをまとめたもの。といっても学術書のようなものではなく、新聞のコラムだったものを編集しているので、読みやすく、わかりやすく、とても楽しいエッセイです。
石獅子といって、わたしがぱっと思い浮かぶのは、八重瀬町にある富盛(ともり)の石彫大獅子(一六八九年)と、首里にある御茶屋御殿(おちゃやうどぅん)石獅子(こちらは一九七九年に復元されたもの)くらいですが、著者の若山さんは百三十体ほどの石獅子を訪ねたそうです。なかには、とても獅子とは思えない、ゆるキャラのような石獅子もいますが、それぞれに個性的で見ていてあきません。
わたしもこの本を持って、あちこち見てまわりたくなりました。まずは若山さんが石獅子に興味を持つきっかけとなった、那覇市上間のカンクウカンクウからでしょうか。
〔ひがしのさやか:最新訳書はM・W・クレイヴン『キュレーターの殺人』(ハヤカワ文庫)。ハート『帰らざる故郷』、チャイルズ『ハイビスカス・ティーと幽霊屋敷』、クレイヴン『ブラックサマーの殺人』など。ツイッターアカウント@andrea2121〕
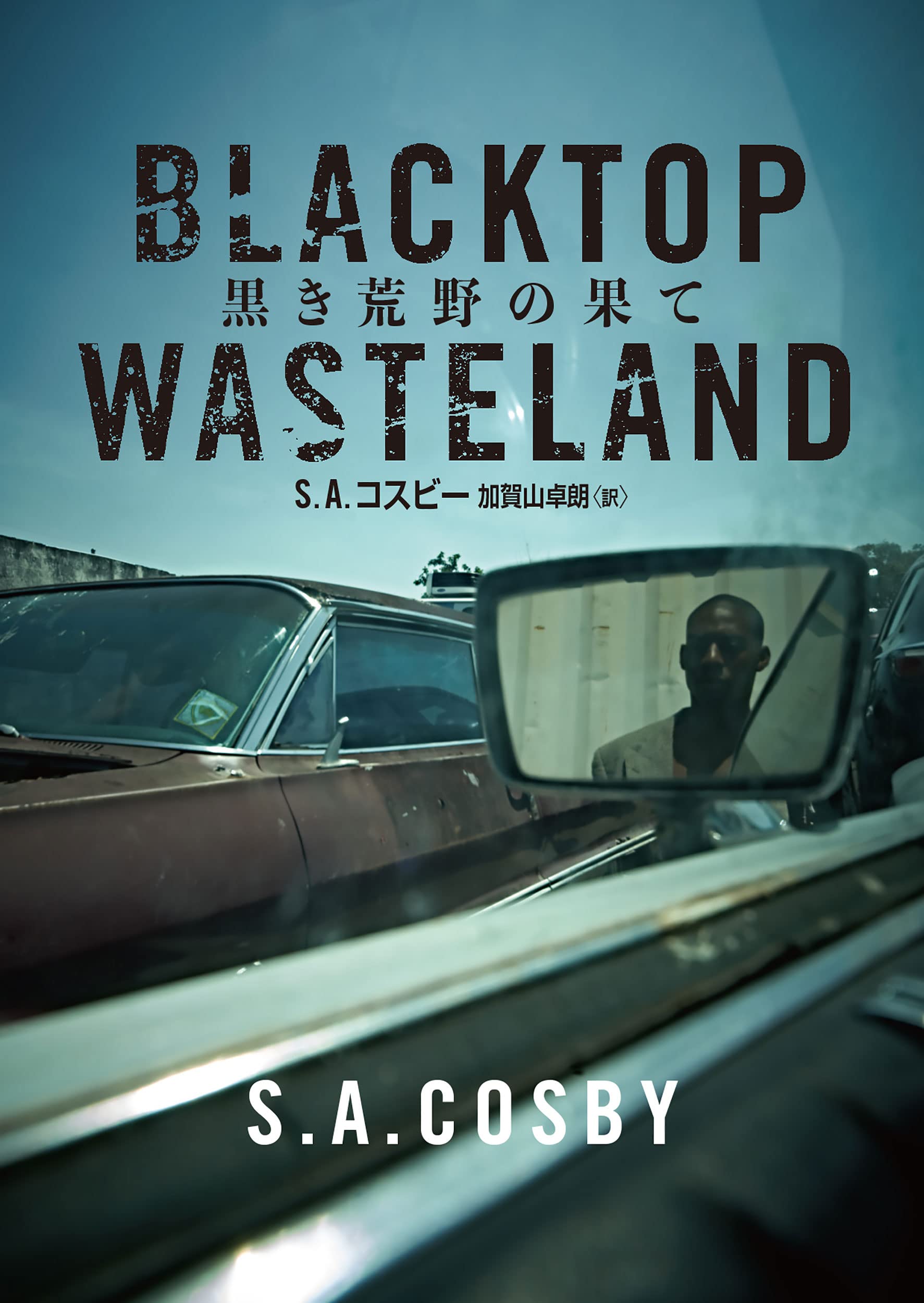
加賀山卓朗
夏ごろからなぜか集中的に重なっていた仕事が少しずつ片づき、谷崎潤一郎全集をパラパラめくるくらいの余裕が出てきました。幸せ。何度も中断していた劉慈欣『三体』シリーズもついに読了。いやこれすごいわ、いまさらですが。権謀術数というか、宇宙レベルの知恵比べみたいな第Ⅱ部が頂点かと思いきや、第Ⅲ部を読んでぶっ飛びました。こんな大風呂敷、初めて見たよ。SFの素人なのでよくわかりませんけど、宇宙と時間と空間の処理でこれを超えるものはなかなか書けないのでは? もっと驚かせてくれる本が出てくるのは大歓迎ですが。
新しいところでは、まもなく発売のジェイムズ・ケストレル『真珠湾の冬』が傑作です。ミステリとしてもよくできてるし、主人公が日本で暮らすところなんか、おいおいこれ『シブミ』かよ、と思いました。畠山さん加藤さん、勧進元じゃありませんが、これは必読ですよ!
〔かがやまたくろう:ジョン・ル・カレ、デニス・ルヘイン、ロバート・B・パーカー、ディケンズなどを翻訳。最近の訳書はスウェーデン発の異色作で意欲作、ピエテル・モリーン&ピエテル・ニィストレーム『死ぬまでにしたい3つのこと』〕
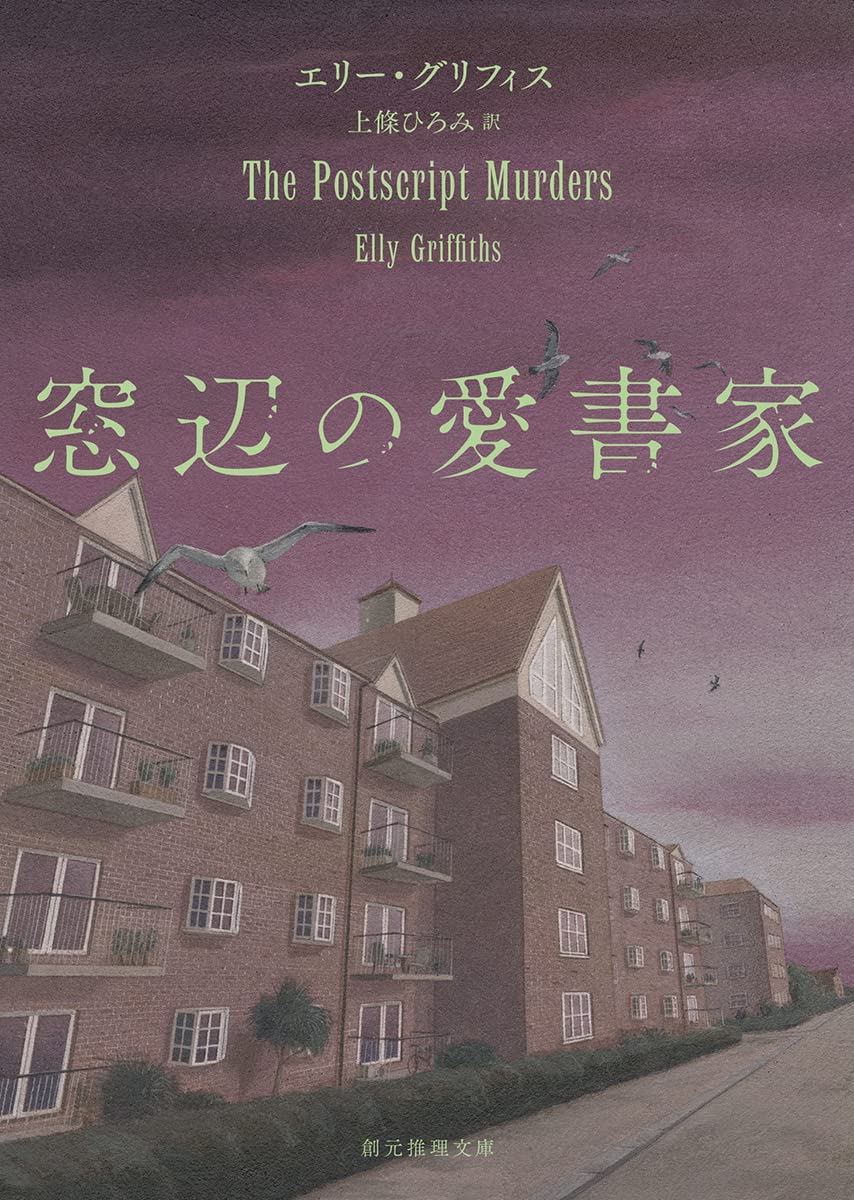
上條ひろみ
エル・コシマノの『サスペンス作家が人をうまく殺すには』(辻早苗訳/創元推理文庫)がおもしろすぎて震える。ブブー……ブブー……(上演中はスマホの電源を切ってください)。売れないロマサス作家の崖っぷちヒロインが、知力体力時の運という、アメリカ横断ウルトラクイズ(古い!)に求められるスキルを駆使して突っ走るユーモアサスペンスです。こういうの大好き。ヴィエッツ〈ヘレンの崖っぷち転職記〉シリーズやデリオン〈ワニ町〉シリーズ、そしてイヴァノヴィッチ〈ステファニー・プラム〉シリーズにも通じるところがあるので、同好の士は必読です。ふたりの幼児を抱えるシングルマザーというところは、拙訳のマキナニー〈ママ探偵〉シリーズともかぶっていて胸熱。続編も翻訳されるとのことなので(わーい!)要チェックです。
もう一冊の震えた本は、ポール・ベンジャミンの『スクイズ・プレー』(田口俊樹訳/新潮文庫)。ご存じのとおり、ポール・ベンジャミンはポール・オースターの別名義。正統派ハードボイルドと聞いてはいたけど、これほどとは!と驚く正統派ぶりで、デビュー作とは思えないほどの完成度です。絶体絶命の時でもワイズクラックを口にせずにはいられない「私」のやせがまんぶりは、芸術の域に達しています。好きだな〜、こういうキャラ。ワイズクラックを口にしていないと死んでしまうのかしら、この人、と思ったわ。
ペンネームを変えてまったくテイストのちがう作品を展開するといえば、『夜のエレベーター』(長島良三訳/扶桑社ミステリー)のフレデリック・ダールもそうでした。こちらは二転三転するストーリーに読みながら狐につままれたような気分になる、クラシカルなサスペンス小説。最後までどこか虚無的な男と女の心情と行動がすごくフランスっぽくて、そのあやういバランスがなんとも言えず魅力的です。クリスマスに読むのもいいかも。
マリー・ルイーゼ・カシュニッツの短編傑作選『その昔、N市では』(酒寄進一訳/東京創元社)にも震えました。こちらはゾッとする感じ。説明できない怖さがあとを引く、戦後ドイツを代表する女性作家の名作を集めた日本オリジナル短編集で、不気味なのに読みやすくて、どこかシーラッハの短編を思わせます。カシュニッツは1901年生まれで1974年没。1960年代に書かれた作品が多いけど、普遍的なメッセージを感じるものばかり。「その昔、N市では」は今でいうゾンビの話だし、「いいですよ、わたしの天使」はオレオレ詐欺に引っかかりにいく老婆の話みたいで悲しすぎる。あと、「精霊トゥンシュ」に出てくる高原放牧地(ルビ、アルム)は、「アルムおんじ」「アルムのもみの木」のアルムだよね。ずっと地名だと思っていた……勉強になりました。
〔かみじょうひろみ:英米文学翻訳者。おもな訳書はジョアン・フルークの〈お菓子探偵ハンナ〉シリーズ、ジュリア・バックレイ『そのお鍋、押収します』、カレン・マキナニー『ママ、探偵はじめます』、エリー・グリフィス『見知らぬ人』など。最新訳書はグリフィス『窓辺の愛書家』〕

武藤陽生
翻訳者は基本的に座って仕事をすることが多いので、腰を痛めがちですね。40歳を過ぎたあたりからいきなり腰痛に悩まされるようになりました。運動不足のせいもあるんでしょうか。そう思い、10年ぶりくらいにランニングを再開し、腹筋・背筋トレーニングをしていたら、3日目で腹筋を攣りました。腹筋を攣るなんて生まれて初めてだったのでびっくりです。かれこれ15分くらい悶絶していたのですが、痙攣が治まったらなぜか腰痛がだいぶよくなっていました。気のせいでしょうか。腰はほんとに大事ですね。
〔むとうようせい:エイドリアン・マッキンティの刑事ショーン・ダフィ・シリーズを手がける。出版、ゲーム翻訳者。最近また格闘ゲームを遊んでいます。ストリートファイター5のランクは上位1%(2%からさらに上達しました。まあ、大したことないんですが…)で、最も格ゲーがうまい翻訳者を自負しております〕

鈴木 恵
今日からもう12月。今年読んだ本のなかでとりわけ面白かったのは、ウィリアム・ダンピア『新世界周航記(上・下)』(岩波文庫・平野敬一訳)。17世紀英国の海賊が著した12年半にわたる航海記なんですが、町を襲ったり船を拿捕したりといった海賊行為のほかに、各地の動植物や気候風土などを旺盛な好奇心でつぶさに記録しており、海賊にもこんな人物がいたのかと驚かされます。ダンピアの最大の特徴は、けっして話を盛らないこと。自分の見聞したことだけを伝え、知らないことは知らないとはっきり書きます。
この本は、デフォーの『ロビンソン・クルーソー』にも影響をあたえたとされています。なかでもダンピア一行が、無人島に3年間も置き去りにされていた〝モスキート・インディアン〟を救出するエピソードは、『ロビンソン・クルーソー』の一場面とみごとに重なります。
しかし〝インディアン〟の描きかたはダンピアとデフォーでは正反対です。冷静な観察者ダンピアはこう書きます。「私は人食い人種というものにお目にかかったことは一度もない(……)カリブ諸島のインディアンは(ヨーロッパ人と)礼儀正しく交易を行なっている」
一方デフォーは、ダンピアのこの文章を読んでいたはずなのに、フライデーたち〝インディアン〟を野蛮きわまりない人食い人種として描きます。デフォーは小説家ですから、物語を面白くするために必要な部分だけを拝借し、あとは都合よく忘れることにしたのかもしれません。世界を旅してとらわれのない目でものを見ることのできる海賊と、イギリスという狭い世界で俗見を利用して物語を書く作家。面白い対比です。
〔すずきめぐみ:この長屋の万年月番。映画好きの涙腺ゆるめ翻訳者。最近面白かった映画は《宮松と山下》。ツイッターアカウントは
@FukigenM〕