
田口俊樹
今月、来月、再来月と三冊続けて出ます。まずは今月末、レイモンド・チャンドラーの『プレイ・バック』の新訳。この本はあの例の「タフでなければ生きられない~」って台詞が有名ですよね。それを田口はどう訳したか。ほんのちょこっと工夫をしました。そこんとこ、ほんのちょこっとご期待ください!
来月も新訳で、デイモン・ラニアンの『ガイズ&ドールズ』。ラニアンはすべての作品のすべての文を現在形で書いたことで有名ですよね。これを田口はどう訳したか。日本語と英語の時制ってちょこっとちがったりするんで、そこんとこ、ちょこっと意識しました。このちょこっとにご期待ください!
最後はドン・ウィンズロウのダニー・ライアン三部作の掉尾を飾る『荒廃の市(まち)』(仮題)。ウィンズロウはこの作品を最後に作家業から足を洗うみたいなんですよね。そんな意味ある作品を田口はどう訳したか。ウィンズロウも現在形に特色のある作家ですが、街場の話しことばをそのまま再現しようとしたラニアンの現在形とはだいぶちがいます。現代風のおしゃれな現在形です。そこんとこ、ちょこっとおしゃれしました。これまたちょこっとご期待ください!
〔たぐちとしき:ローレンス・ブロックのマット・スカダー・シリーズ、バーニイ・ローデンバー・シリーズを手がける。趣味は競馬と麻雀〕
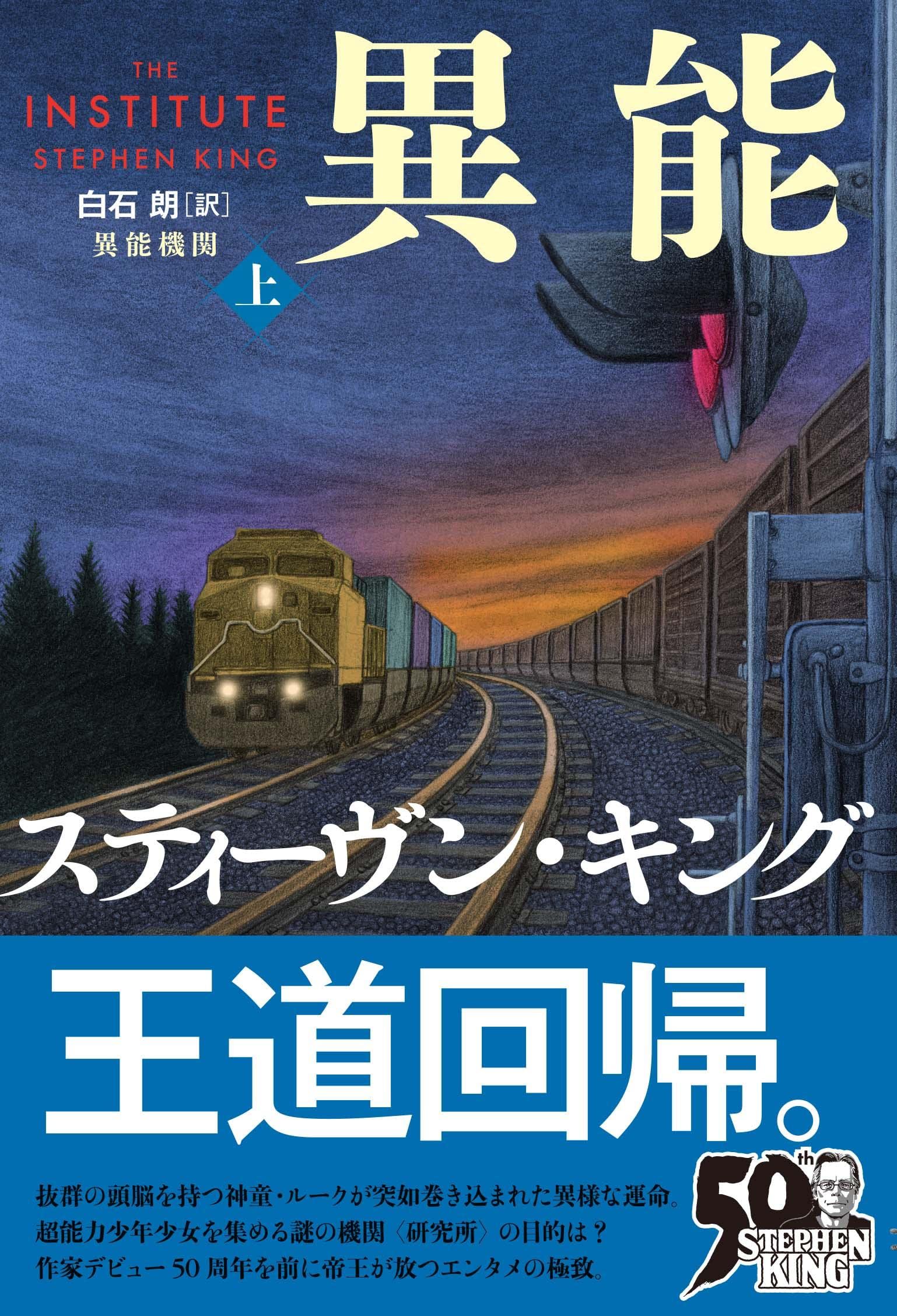
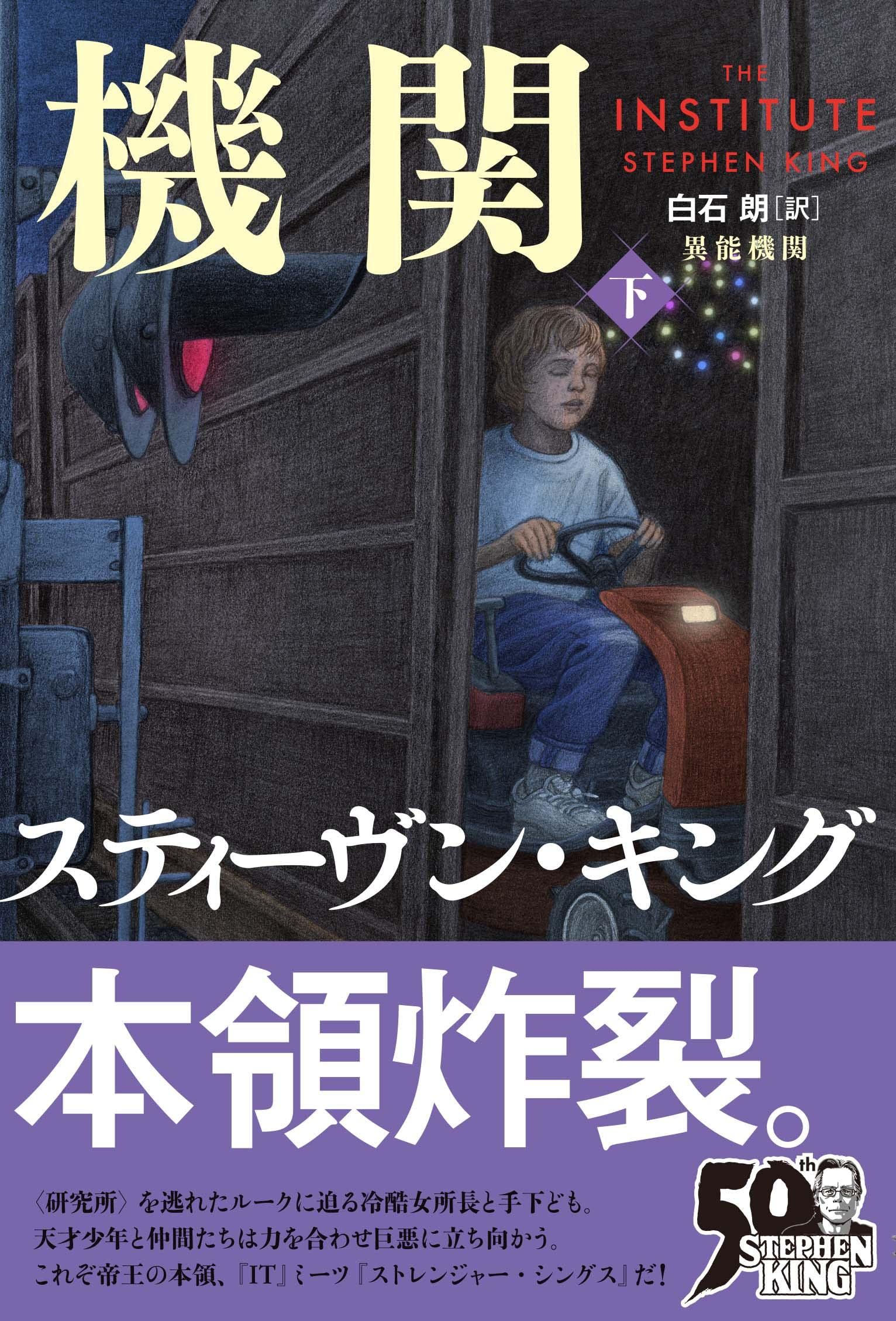
白石朗
来週の4月8日には、文藝春秋より拙訳でスティーヴン・キング『ビリー・サマーズ』が刊行されます。50周年記念刊行長篇第2弾。すでにネット各所では刊行予定が流れていますのでご存じの方も多いと思いますが、もし万一まだ書店等で予約されていない方がいらっしゃいましたら、この機会にぜひ。
『ビリー・サマーズ』は凄腕の殺し屋が引退前に引き受けた「最後の仕事」のてんまつを描いたクライム・ノヴェルとして開幕しますが、そこはスティーヴン・キング、大小さまざまなサプライズと意想外のツイスト繰り出しつづけ、小説だけが描ける思いもよらない地平へと読者を導きます。いやいや、もう少し中身を知らないとお代は出しにくいという方はまず以下の版元サイトをご参考に。
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163918310
https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163918327
また文春e-Booksより無料電子書籍のガイドブックも出ております。二章分(単行本で40ページまで)のためし読みとあわせて、文藝春秋編集者・永嶋氏と不肖白石の対談も掲載されていますので、こちらもご高覧たまわれば。
翻訳に使用したメインの原書の大判ペーパーバック版には巻末におまけがついていました。「読書会の手引き」として、参加者の話題や議論のきっかけになるようなトピックや「あなたならどうする?」的な問いかけが列挙されていたのです。たとえば最初の問いは――
主人公は自分を守るために〝お馬鹿なおいら〟という仮面をつくって利用していることをシートベルトにたとえます。この自己防衛法をどう思いますか? あなたやあなたのお知りあいに似たことをしている人はいますか?
――てな具合。ほかの問いかけもおもしろかったのですが、当然ながら本文読了前提なのでご紹介しにくいのが残念です。
〔しらいしろう:老眼翻訳者。最近の訳書はスティーヴン・キング『異能機関』。同じくキングが凄腕暗殺者の最後の仕事をテーマにした超異色作 Billy Summersは邦訳刊行待機中。ツイッターアカウントは @R_SRIS〕

東野さやか
ところできのうから、マイクル・コナリーの『警告』(古沢嘉通訳/講談社文庫)を読んでいます。ひさびさのジャック・マカヴォイ登場で、冒頭からぐいぐい引きこまれています……が、ひさしぶりすぎていろいろ設定を忘れています。どのくらい忘れているかといえば、マカヴォイに双子の兄がいたことも、その兄が殺されていたこともすぐには思い出せなかったくらい。もう、顔を洗って出直してこいって感じですね。
〔ひがしのさやか:最新訳書はシェルビー・ヴァン・ペルト『親愛なる八本脚の友だち 』。その他、クレイヴン『グレイラットの殺人』、スロウカム『バイオリン狂騒曲』、チャイルズ『クリスマス・ティーと最後の貴婦人』。ツイッターアカウント@andrea2121〕
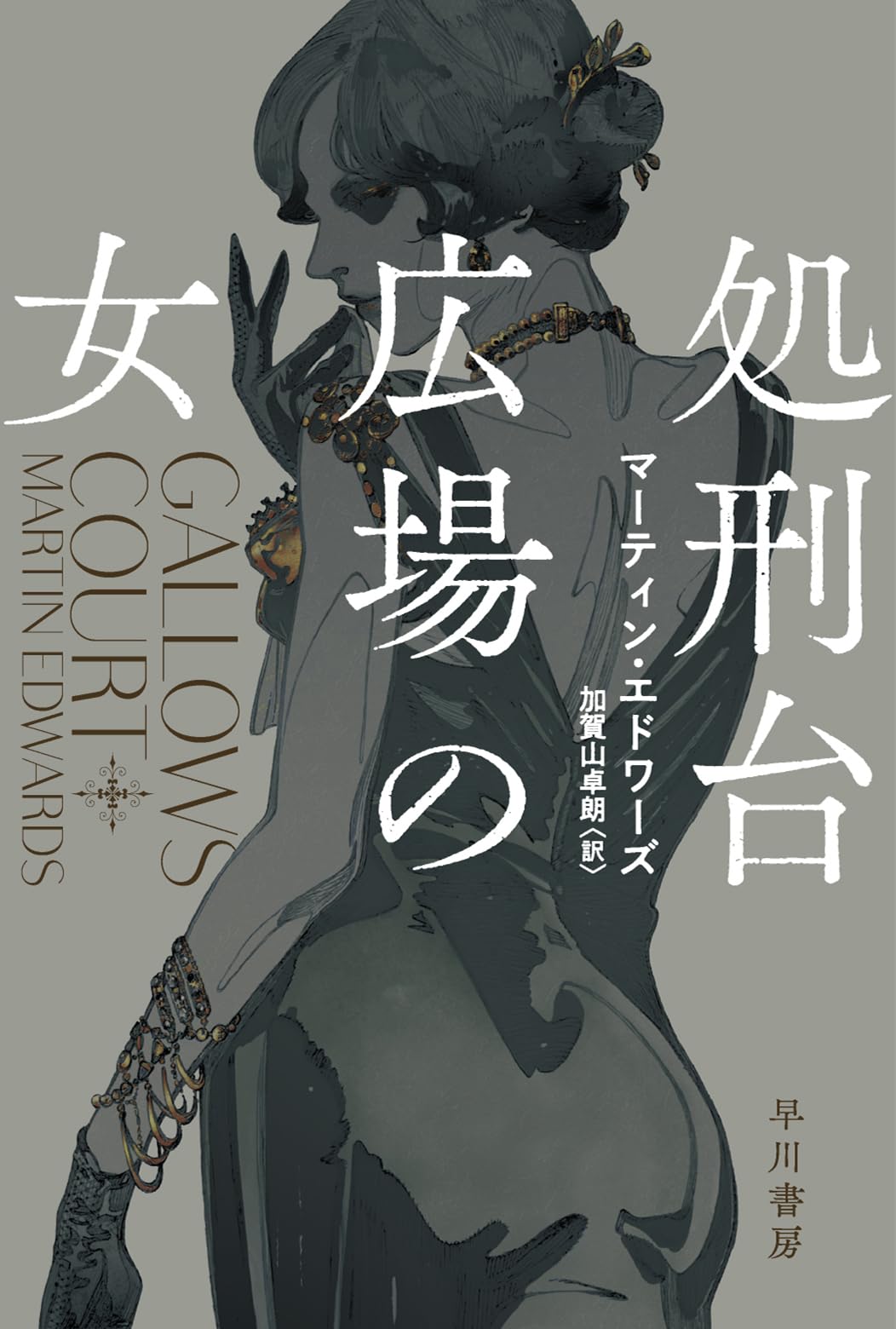
加賀山卓朗
唯一惜しいのは、小説版のように蟻の視点で物語が始まらなかったことかな(個人の好みです)。いま話題の『両京十五日』も第1章が蟋蟀(こおろぎ)の視点で始まるんですが、中国の小説家って虫の視点が好きなんでしょうかね。
〔かがやまたくろう:ジョン・ル・カレ、デニス・ルヘイン、ロバート・B・パーカー、ディケンズなどを翻訳〕

上條ひろみ
〔かみじょうひろみ:英米文学翻訳者。おもな訳書はジョアン・フルークの〈お菓子探偵ハンナ〉シリーズ、ジュリア・バックレイ『そのお鍋、押収します』、カレン・マキナニー『ママ、探偵はじめます』、エリー・グリフィス『見知らぬ人』、『窓辺の愛書家』など。最新訳書はフルーク『トリプルチョコレート・チーズケーキが噂する』〕

武藤陽生
今度の4/20(土)に、朝日カルチャーセンター新宿教室で『ゲーム翻訳の疑問に答える!』と題した講座をやらせていただくことになりました。現地の教室で開催されますが、オンラインでの視聴もできます。ゲーム翻訳業界がどういうところなのかについて俯瞰的な話をしようと思っています。対面でのこうした講座は久しぶりなので、自分も楽しみにしています。ご興味ある方はぜひお申し込みください。フォームから質問だけすることも可能です。
〔むとうようせい:エイドリアン・マッキンティの刑事ショーン・ダフィ・シリーズを手がける。出版、ゲーム翻訳者。最近また格闘ゲームを遊んでいます。ストリートファイター5のランクは上位1%(2%からさらに上達しました。まあ、大したことないんですが……)で、最も格ゲーがうまい翻訳者を自負しております〕
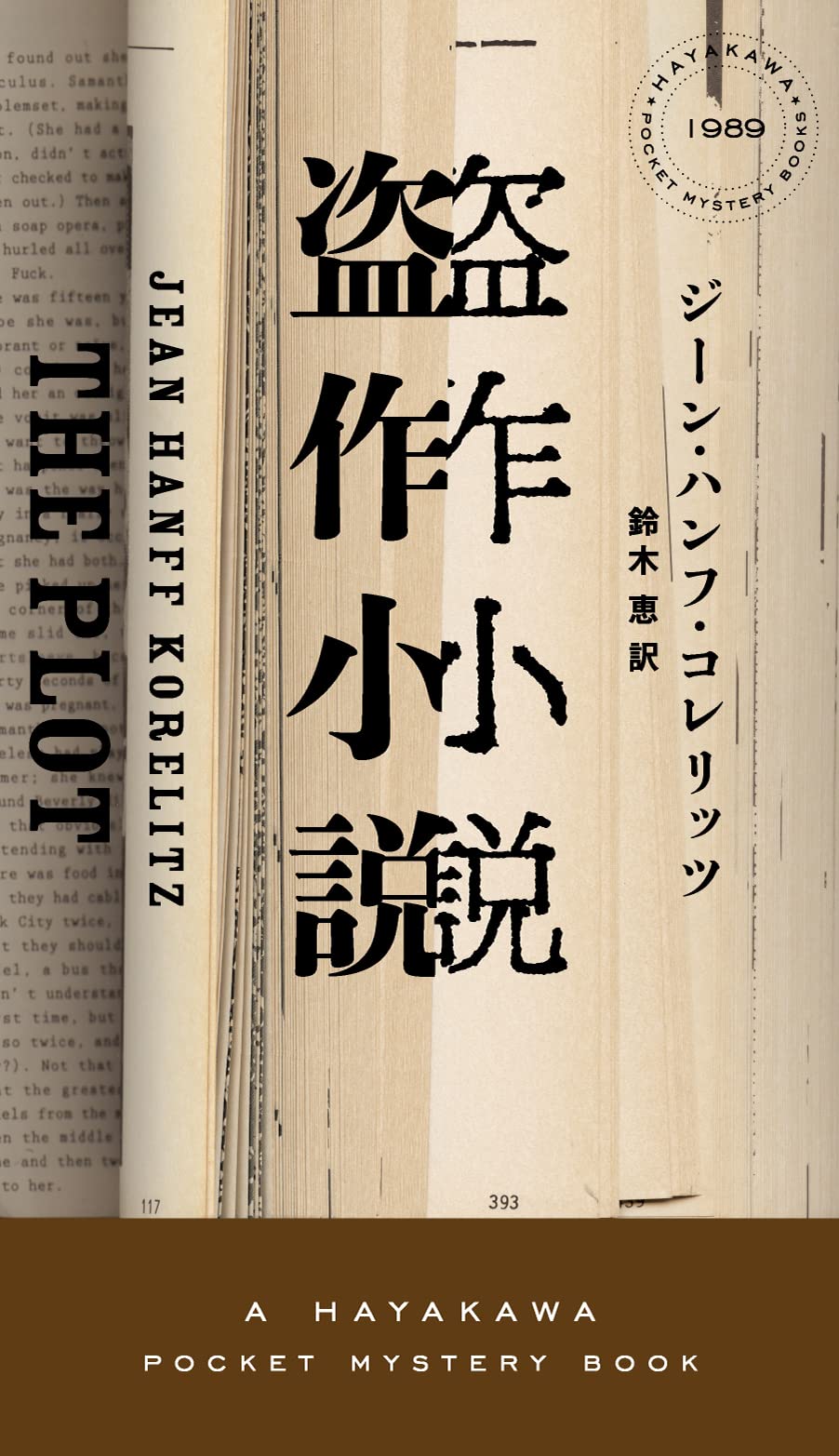
鈴木 恵
週一でテニススクールに通っている。そのクラスに、わたしと同年配のおばさんが新しくはいってきた。ちょっとお節介な人だな、というのが第一印象だったんだけど、数か月後、ひょんなことから中学の同級生だとわかった。なにしろ半世紀もむかしのことなので、おたがいに気づかなかったのだ。
中学時代、彼女とはあまり口を利いたことがなかった。いや、今でもそれは変わらないのだが、でも当時のことでひとつだけ、いまだに憶えているできごとがある。3年生のとき、彼女はクラスの図書委員で、ある日こんなことを言いだした。「このクラスは図書の貸出数が少ないです。とくに男子! わたしが借りてきてあげるから、貸出カードを渡しなさい!」
というわけで、わたしをはじめ数人が槍玉にあげられて、彼女にカードを渡すと、彼女はそれぞれに1冊ずつ小説を借りてきてくれた。ほかの連中が何を渡されたのかは忘れたけれど、わたしの分ははっきり憶えている——武者小路実篤『友情』。彼女のお気に入りの1冊だったのだろう。
もちろん読まずに返却した。ほかの連中もそうだったと思う。それは当時わたしたちが読書嫌いだったからではなく、学校の図書館にあるようなものとは全然ちがう本を読むようになっていたからだ。みな学校のではなく、市の図書館や街の貸本屋に通っていた。仲間うちではやっていたのは、「刑事コロンボ」のノベライズや国産のミステリー小説だった。小峰元の『アルキメデスは手を汚さない』とか『ピタゴラス豆畑に死す』とか、そんな題名をいま懐かしく思い出す。
『友情』はいまだに読んだことがない。でも、いい機会なので読んでみようかな、とふと思っている。読んで彼女に感想を伝えてみようかなと。憶えてるか?——と言って。そうすれば半世紀前の彼女のお節介に、いちおうは酬いたことになる。