みなさま、カリメーラ(こんにちは)!
別にジェンダーと作家性の関係についてこだわるつもりはないのですが、エッセイ第20回に書こうと思いながら本が入手できず、後回しにしてあった話題の女性作家たちの続きです。
《音楽ミステリ》ヒルダ・パパディミトリウ女史(エッセイ第8回。シリーズキャラはビートルズ命のイジられ役ハリス・ニコロプロス警部)はミステリ作品のレヴューをよく書いています。
 (またはΣυνέντευξη: Αστυνόμος Νικολόπουλος | Επιθεώρηση Εγκλήματος – Casopensato) 【最近電子ジャーナル《Caso Pensato》に出ていた、ハリス・ニコロプロス警部への架空インタビュー記事。実際は作者自身の趣味やミステリ観が披瀝されます。よく読む作家はジョージ・ペレケーノス、アンドレア・カミッレーリ、へニング・マンケル、将来ゆっくり読みたいのはヘロドトス(冗談ではありません。逸話に満ちた楽しい歴史物語です)。2007年のデビュー作でハリス警部はイジラレ役のチャーリー・ブラウンみたいなイメージでしたが、実はシブいマイケル・ダグラス風だったんですね。最新作『疑わしきは罰すべし』では退職して好きな音楽や読書にふけっているようです。】 |
2018年6月7日のBook Press紙(電子ジャーナル)への記事で、パパディミトリウは話題の女性ミステリ作家四人を取り上げています。
 > >【四人の顔写真も見られるのでリンクしておきました。】 |
そのうちの二人、《家族の絆》エフティヒア・ヤナキと《ユーモア探偵》コンスタンディナ・モスフは本エッセイでもすでに触れておきました(エッセイ第17、18回)。
今回ご紹介するのは残る二人、エレナ・フスニとフリサ・スピロプルです。
◆ノーベル賞詩人登場――エレナ・フスニ『黄金の復讐』
『そして誰もいなくなった』や『僧正殺人事件』と言えば《見立て殺人もの》の古典的名作ですね。詩や童謡の筋書き通りに事件が起きる、ミステリ小説ならではの妖しい虚構の世界にたくさんの読者が酔ったはず。日本でも横溝正史『獄門島』『悪魔の手毬唄』などは外国作品にも比肩できる傑作でしょう。『犬神家の一族』はギリシャ訳もあります(例の「斧・琴・菊」の見立ては外国人に理解できるのか心配ですが、やっぱり脚注で丁寧に解説してあります)。
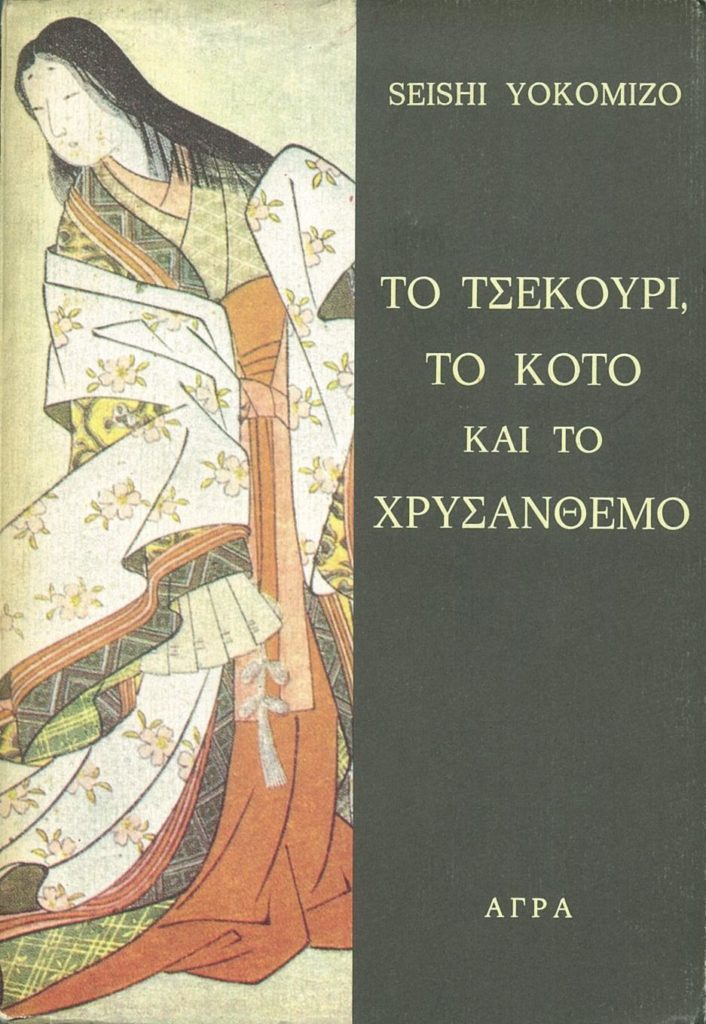 横溝正史『斧、琴、菊』 横溝正史『斧、琴、菊』(『犬神家の一族』ギリシャ語訳) アグラ社、1991 |
こういう趣向はしかし、ギリシャ・ミステリではまれです。アザリアディス『暗闇の迷宮』(エッセイ第13回)の復讐に燃えるエレクトラやパパディミトリウ他のリレーミステリ『黙示録』(エッセイ第10回)、あるいは(ミステリではないですが)ヴェネジス「アンティゴネ」(エッセイ第20回)などは、モチーフとしてオリジナル作品との平行性が暗示されるだけです。やはりリアリズム主流のギリシャ・ミステリは遊戯性の高い《見立てもの》と相性がよくないのか、と思っていたところ、ちょっと別の形ではあるのですが、著名な詩人をストーリーのカギに使っている作品に出会いました。
今回ご紹介するエレナ・フスニ女史の『黄金の復讐』です。
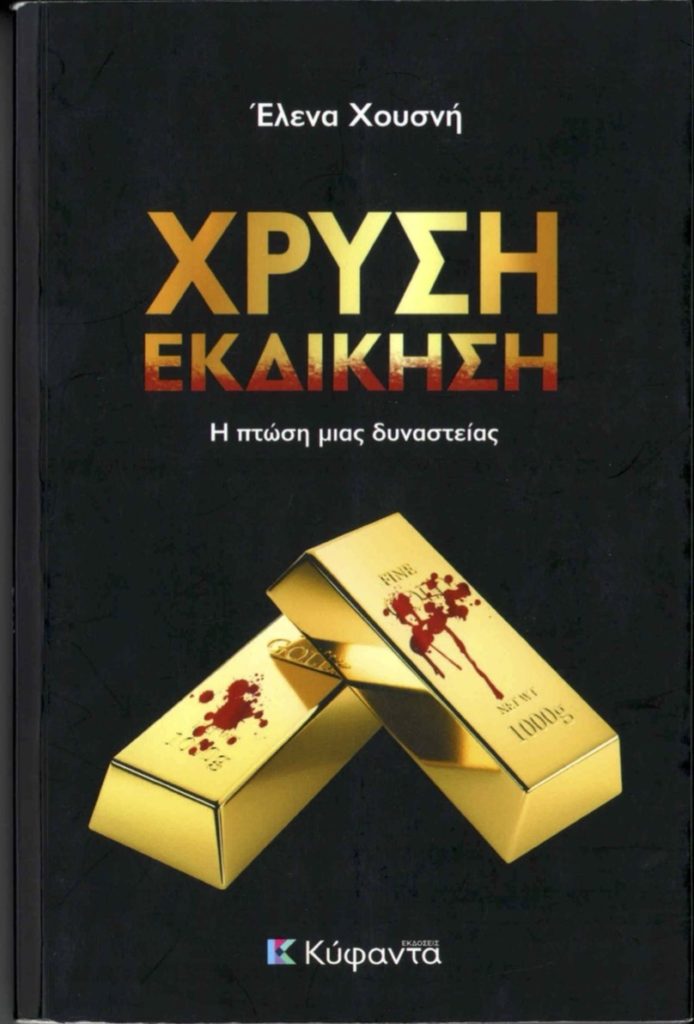 エレナ・フスニ『黄金の復讐』 エレナ・フスニ『黄金の復讐』キファンダ社、2016 |
副題に「ある王朝の崩壊」とあります。経済界の組織犯罪とその末路でしょうか?
有能なジャーナリスト、ナンシーに匿名の手紙が三通送られてきます。脅迫というのではなく、彼女に何かを訴えているようです。内容はというと……ここの語りの展開が面白いのですが、作者はすぐに内容を明かしてくれません。経済危機に押しつぶされそうな社会の喘ぎや、ナンシー自身の過去と日常がゆっくりと綴られていきます。そうしてようやく謎の手紙を検討し始めるのですが、まずは、封筒や切手から。封筒はいずれもコレクター垂涎のプレミアムもので、ギリシャ近代史に関係した図案が使われています。差出人の狙いと関係があるのか? さまざまな仮説が出てきます。そんなこんなで読者には内容がいまだ不明!
同じ頃、業界を牛耳る大実業家の娘イサヴェラが殺害されます。父の跡を継いだ彼女自身もバリバリのやり手でした。その殺し方が実に異様で、このへんから不可思議な雰囲気が漂い始めます。遺体は全裸で、両手が祈るように胸の上で組み合わされ、胸と顔に溶けた黄金を注がれているという奇っ怪なもの。
父の大物実業家コペルナロスは当然怒り狂って、政府と警察に圧力をかけ犯人の即刻逮捕を命じます。
死体の様子と並んで謎を呼ぶのが現場に残された紙片です。そこには高名なノーベル賞詩人ヨルゴス・セフェリスの短い作品が書かれていました。
「『ギリシャ』撃て! 『ギリシャ人の』撃て! 『キリスト教徒の』撃て!
死せる三つのことば。あなたたちはどうして殺したのか?」
これだけでは分かりにくいのですが、民族主義的な「ギリシャ人の、キリスト教徒のギリシャ」を標榜した軍事政権(1967~74年)への強烈な抗議を含んだ寸鉄詩です(詩集『練習帳II』(1968年)に所収)。してみると、犯人の動機は独裁制への抗議ということ? 軍事政権が崩壊してすでに40年以上、とすれば現在政界と癒着して国の経済を独占するコペルナロス一族への鬱憤? 溶けた黄金は金の亡者への当てつけなのか?
女性記者ナンシーに加えて、昔気質の退職編集長グリゴリウと沈着冷静な精神科医パパルギリウのトリオが謎に迫ります。論理的に謎を解き明かしていくのは精神科医ですが、描写の焦点はナンシーに置かれます。上に書いたように謎の手紙がナンシーに送られており、これはもちろん殺人事件と関係してくるでしょう。
手紙の内容がようやく明かされるのは100頁も過ぎたあたりです。
手紙というよりも、これもセフェリス詩の引用でした。詩人は軍事政権崩壊を目にすることなく1971年に亡くなりますが、その直後に発表された「アスパラソスの上で」という作品です。
ポセイドン神殿で有名なスニオン岬で黄色いアスパラソス(棘のあるエニシダ科の花)を目にした詩人が、プラトン『国家』に出てくるこの花のシーンを思い出すという内容。プラトンでは、生前父兄を殺した僭主が地獄に堕とされ、アスパラソスの上で懲らしめを受けるシーンが描かれています。
このセフェリスの詩にも軍事政権への批判が込められているようです。ということは、謎の犯人がナンシーに訴えたいのは、やはり現代の独裁的な巨大実業王朝の没落の予言なのでしょうか?
その後、もう一件の殺しが続きますが、意外なことに被害者は富豪の娘とは接点のない質屋の主人でした。ただしこの質屋、全国チェーンで展開していますが、黒いうわさが絶えません。またしてもセフェリス詩「聖ニコラス僧院の猫たち」が出現。軍事政権への抗議をこめて1970年に18人のギリシャ人文学者が出版したアンソロジー『十八のテキスト』の劈頭を飾る作品です。
 茂木政敏「現代ギリシャ文学ノート(1) ――セフェリスから「七十年代世代」へ(ギリシャ軍政下の詩人たち)――」 http://pubspace-x.net/pubspace/archives/2655 【以前にもご紹介した、現代ギリシャ文学研究者の茂木政敏さんによる文章です。『十八のテキスト』や「聖ニコラス僧院の猫たち」にも触れられています。】 |
他にも、ノーベル賞受賞スピーチや軍事クーデター当日のセフェリスの日記なども出てきます。つまりは、犯人は(自分にとっての)社会不正への抗議として犯行をおこない、詩人の詩句にその心情をこめたということなのか?
外見上を模倣する《見立てもの》ということではないのですが、犯罪の根底にある精神的なものを文学作品で暗示しようとしているようです。いずれにしても、ギリシャ・ミステリとしては珍しい方向だと思います。
作者エレナ・フスニは北部の町ペラの出身。ジャーナリストとして活躍しており、主人公ナンシーにはその姿が投影されているのでしょう。レズボス島やヒオス島からなる北エーゲ行政地域の情報センターやEUネットワーク関係で要職につき、サモス島で教育にも携わっているようです。
2009年と2012年に「全ギリシャ文学者連合」文学コンクールの演劇部門や長編部門で賞を得ているらしいのですが、書籍出版されていないようで(?)、作品の内容が分かりませんでした。
カタログにはっきり掲載されている最初の本『ダイバーたちの聖域』を出したのは2014年。これに続くのが『黄金の復讐』です。2017年の『縞のブラウスの子供』は幼児虐待、 2018 年『呪われた町』はサモス島にあったハンセン病院がテーマのようです。2019年の『F階梯』はなんといっても不思議な題名に目を引かれます。これはぜひ読んでみたい。
短編はあまりないようで、私もアンソロジー『暗闇の事件』(2018年)に入っている「わが魂が叫び声をあげる」を読んだだけです。親友を殺されたホームレスの復讐を描く、ちょっとマルカリスの世界のような社会派作品でした。
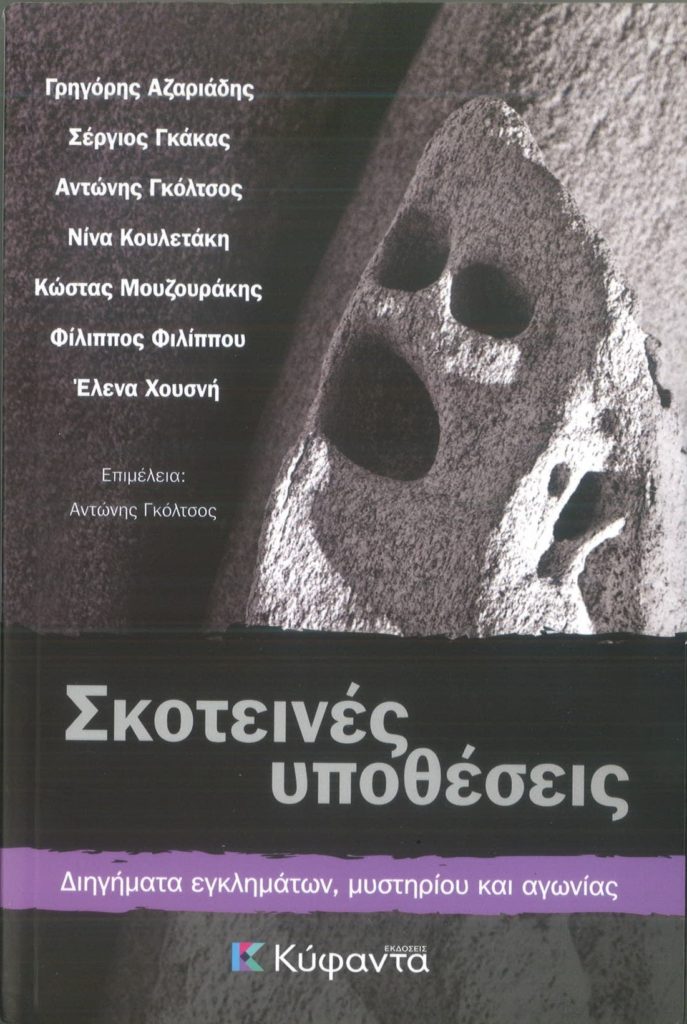 グリゴリス・アザリアディスほか『暗闇の事件』 グリゴリス・アザリアディスほか『暗闇の事件』キファンダ社、2018 |
◆霧の湖の伝説――フリサ・スピロプル『ざわめく湖水』
次の作品の舞台は北へ飛びます。主役たちがテサロニキの街角を奔走するミステリは《六歌仙No. 4》マルティニディス(エッセイ3回)の作品はじめいくつかありますが、北部の田舎町や村となるとこれはめずらしい。
フリサ・スピロプルの最新作『ざわめく湖水』(2018年)は北マケドニア共和国との国境にあるドイラニ湖で幕を開けます。湖と言っても面積40平方キロほどで、国内の湖ベスト10にも入らない大きさですが、写真で見ると繁った蘆と垂れこめる霧とがなかなか幽玄の趣を湛えています。
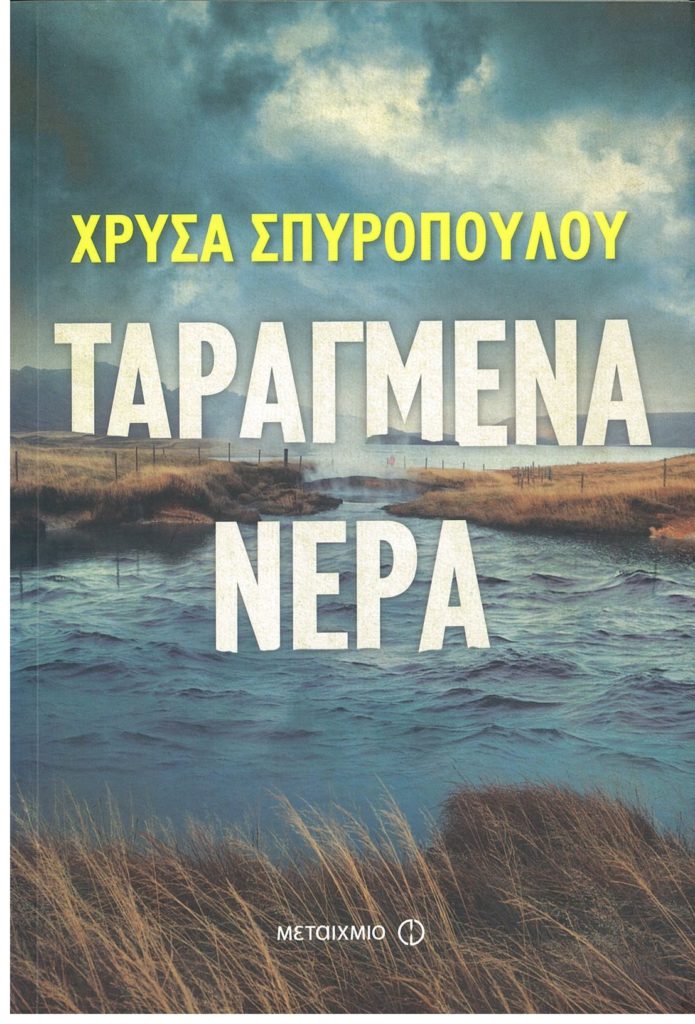 フリサ・スピロプル『ざわめく湖水』 フリサ・スピロプル『ざわめく湖水』メテフミオ社、2018。 |
湖畔に立つホテル《湖の真珠》に投宿中の人気作家サラが泳いでいるうちに姿を消し、恋人の映画監督ヤニスがうろたえています。サラはいっこうに現れず、そもそも事件に巻き込まれたのか、自殺か失踪か、単なる事故なのかわかりません。数日前からサラは不安な様子だったとか。「事件が起きて静かな湖の水がかき乱されてしまった」と客の一人がつぶやきます。
ドイラニ湖の底では水が巨大な渦を巻いているという伝説があります。
「湖のその部分は深くなっていると言う者があれば、湖には霊が取り憑いており、これまで潜水夫、漁師、何も知らない泳ぎ手たちを吞み込んできた、などと古の伝説を持ち出す者もいた。だから土地者は湖の一角を《悪魔の
棲 み処 》と呼んでいる、とある者は付け加えるのだった」
宙ぶらりんで時間が過ぎる中、サラとヤニスと取り巻く人々が少しずつ登場してきます。
裕福なサラの家庭はなかなか複雑で、父親が亡くなった後、母フェドラは再婚し、湖から70キロ東へ離れたセレスの町に暮らしています。フェドラの屋敷に転がり込んでいる再婚相手ランブルはウクライナで一山当ててきたという怪しげな男。この男には前妻との間に連れ子が二人いて、兄マルコスは商才に欠けるのに携帯事業を拡大しようとし、妹ジェニーはいまだに幼児的精神世界から抜け出せません。娘サラの失踪にもかかわらず、フェドラもランブルもすぐに湖に駆けつけようともせず、この点はなんだか不思議です。
そうこうするうち羊飼いの若者がサラの遺体を見つけます。土地の者しか知らないような隠れた一角で、そばの木の枝には何者かの布の切れ端が引っ掛かっていました。
つづいて母親フェドラが書斎で刺殺されてしまいます。直前にフェドラは、サラが残した書類に恐ろしい秘密を見つけて驚いていました。飼っていたオウムが「オマエ、デテイケ!」と遺体のそばで鳴き立てていたのは何かの手がかりなのか?
テサロニキ警察本部から出張って来たイリウ警部とゲオルギウ女警部補が事件を手がけます。このコンビは作家のシリーズ・キャラで、イリウ警部は事故で妻子を失って以来、感情を一切面に出さず事件を冷徹に解決する機械人間のようになっており、警部補のほうも何か過去の傷を抱えているようです(はっきりとは語られませんが)。
さて、フェドラとサラ母子連続殺人事件の容疑者は家族だけではありません。サラの以前の恋人や、家庭に絶望しヤニスを誘惑する女性、あるいは放蕩者ランブルをはげしく
さらに、息子マルコスまでがコンスタンチノープル(イスタンブール)で殺害されてしまいます。マルコスは事業の失敗を取り戻そうと、ブルガリアやウクライナでの投資にのめり込み、誰かに脅されていたらしい。
こうして事件は国境を越えて、霧立ちのぼるボスポラス海峡や雪におおわれたソフィアへと広がっていきます。
登場人物たちが複雑な関係を繰り広げますが、それぞれの心理を作家は一筆入魂という感じで繊細に描き分けていきます。
特に、ヤニスとサラそれぞれの亡き実父たちに対する対照的な思いが印象に残ります。ヤニスは生活力ない父に鬱積した不満を抱えていたのに対し、サラのほうはバリバリと事業に入れこんでいた父に崇拝の気持ちを抱いており、このずれが現在のカップルの不幸に、そして事件につながっていきます。
心理描写でもっとも読ませるキャラは文学少女のジェニーでしょう。いとこサラへのあこがれから、この有名作家の外見や文章を模倣しようとし、嫉妬が嵩じて不可解な行動を見せるようになります。ストーリーのカギとなる人物です。
読後感は満腹なのですが、ただし登場する誰もかれもが何かを隠しており、ミスディレクションを少々盛りすぎかなという印象を受けました。
犯人を突き動かした真の動機も、一重ではなく欲と復讐との二つがまじりあった複雑なものです。現実には人は単一の理由だけでは行動しないとはいえ、小説、特にミステリであれば、どちらかを主にしたほうがその人物像が強烈に残っただろうにという気もします(例えば、『赤毛のレドメイン家』最終章の悪人像のように)。また、復讐につながる70年前(内戦の頃)の因縁話がとても面白かったのに、割とさらっと書かれてあって、もっとページを費やしてほしかったなとも思いました。
連続殺人を扱ってはいますが、陰惨ではなく、むしろ、ドイラニ湖やセレスの町の神秘的、抒情的な雰囲気の中を読者は散策することができます。(アテネの街角のミステリに馴染んだ読者にとっては)湖を吹き渡る風や水鳥、トンボ、カエルの声、あるいはポプラやヤナギの風景がたまらなく新鮮に感じられることでしょう。
セレスは作者の生まれ故郷(人口6万人弱)であり、思い出にあふれているであろう湖畔や周辺に点在する小村の様子まで情感豊かに描き込まれています。
   ・しがしが留学記:マケドニア地方を旅して-サラカチャニ人との出会い – ギリシャ-日本ギリシャ-日本 (greecejapan.com) |
翻訳家の白石朗さんに教えていただいたのですが、昔ジェームズ・ボンドが《ロシアから愛をこめて》亡命してきた女スパイ、タチアナとオリエント急行に乗った際に、このセレスを通過しているそうです。田舎駅なのでもちろん止まることもなく、ボンドが窓外の風景に目をくれることもなかったでしょうけれど。
珍しく地方が舞台だけに、出てくるご当地料理には目を引かれます。
作品の終わりでイリウ警部が謎解きをしながら、「オオナマズのマスタード・バルサミコ・香草つき網焼き」なる料理を食べていますが、これはホテル《湖の真珠》の創作料理のようです。オオナマズはネットの写真で見ると、人よりも巨大でゾッとする外観ですが、食用にするのは幼魚のようです(まあ、そうでしょうね)。警部が注文したもう一品は「イワシのゲミスタ」。これは知りませんでした。「ゲミスタ」はハリトス警部も大好きな「詰め物料理」(エッセイ第14回)で、普通は大型のトマトやピーマンに肉や米をつめて焼くのですが、こちらは割いたイワシにピーマン、トマト、チーズなどを詰めたもののようです。
アカネスという地元セレスの名菓も出てきます。聞き込み先でお茶と一緒にふるまわれた警部は、事件解決後お土産に買うのを忘れないようにな、と部下にクギをさしています。例の《トルコの悦び》ルクミに似ていますが、ヒツジやヤギのバターを用い、炒りアーモンドを入れる点が特別らしい。
 |
最後に作者スピロプル女史のプロフィールを。
ミステリデビューは1998年の中編『湖の霧』です。《ミステリ六歌仙No. 4、テサロニキ派総帥》マルティニディスが『連続殺人』でデビューし(エッセイ3回)、同じく《六歌仙》マルカリスが第2長編『ゾーン・ディエンス』(エッセイ第2回)を、アポストリディスが短編集『ギリシャ警察五十年史』(エッセイ第4回)を発表した年ですので、スピロプルも彼らと同じくギリシャ・ミステリ第二世代のベテランとするべきでしょう。
実は『ざわめく湖水』はデビュー作『湖の霧』を20年ぶりに書き改め長編に仕立てたものです。私はこのデビュー作を読んでいませんが、書評などによると『ざわめく湖水』同様にイリウ警部が登場し女性作家の失踪を捜査、ただし、連続殺人や容疑者の群れが出てくるわけではなく、ミステリというより、ある死をめぐり人々の心理を描きあげる普通小説のようです。『ざわめく湖水』でも人間の内面描写が濃いわけです。
短編もけっこう書いていますが、ミステリだけではなく多彩な引き出しを持っているのがうかがえます。
「《バクテリア》作戦」(2008年)は新たなバイオ燃料を開発した研究者誘拐がテーマ。「エコ」の意味もよくわからず計画を練るマヌケな犯人や、誘拐で有名になって研究費の増額を夢見る研究者が笑わせます。
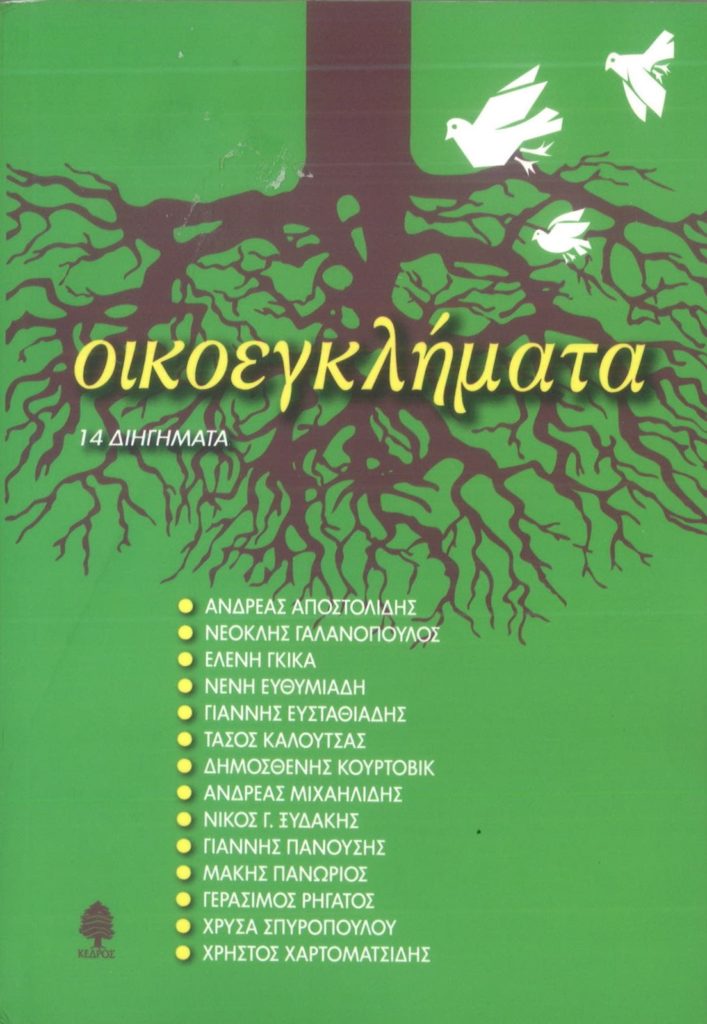 アンドレアス・アポストリディスほか『エコ犯罪』 アンドレアス・アポストリディスほか『エコ犯罪』ケドロス社、2008。 【「《バクテリア》作戦」所収。ミステリ作家・ホラー作家から研究者までが執筆、環境に対する犯罪14短編を集めたひと味違うアンソロジー】 |
「男と女は決して出会わなかった」(2008年)は2090年が舞台のSF設定で、大規模な核事故で世界が大災厄を受けた後に科学者が原因調査をするシリアスなストーリー。
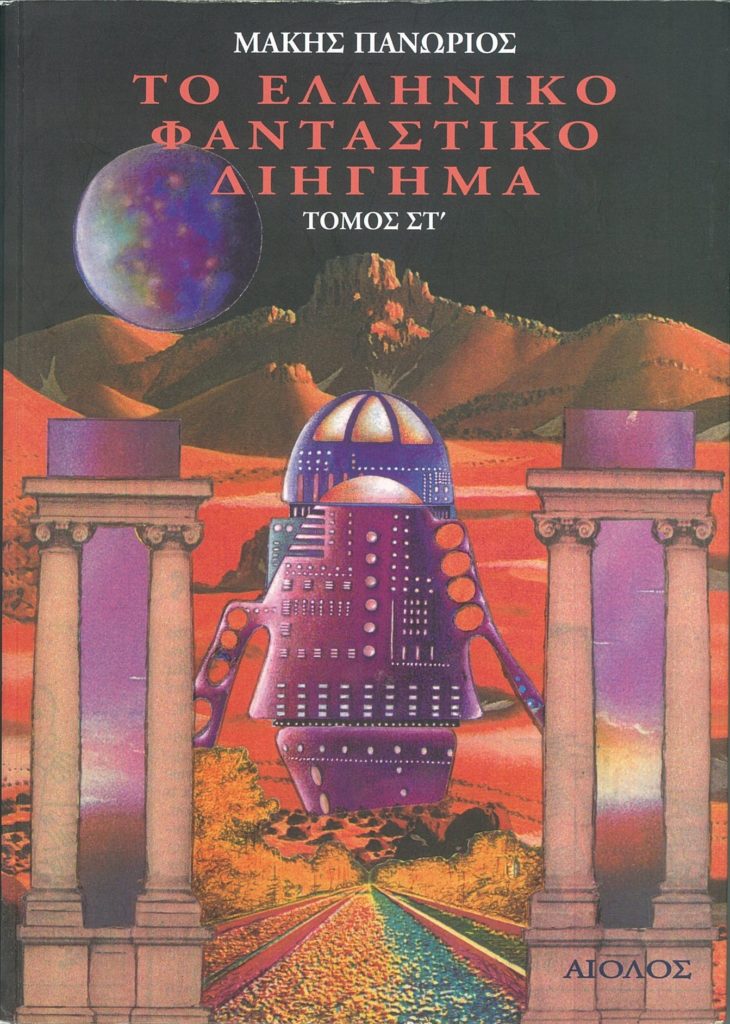 マキス・パノリオス編『ギリシャ幻想短編小説集』第6巻 マキス・パノリオス編『ギリシャ幻想短編小説集』第6巻エオロス社、2012。 【「男と女は決して出会わなかった」所収。19世紀から現代までのギリシャの幻想短編を集成した貴重なシリーズ。この最終巻には2003年以降の新しい作品30篇が収められています。】 |
「殺し屋求めます」(2013年)は三角関係にハマった妻が殺し屋を雇って解決を図るが思惑がズレていくシニカルな物語。『ざわめく湖水』のイリウ警部&ゲオルギウ警部補コンビが登場します。
 ネオクリス・ガラノプロスほか『泥棒と警官』 ネオクリス・ガラノプロスほか『泥棒と警官』プシホヨス社、2013。 【「殺し屋求めます」所収。ミステリのラジオドラマの原作アンソロジー。こちらはオーソドックスな犯罪ミステリ15篇。】 |
ミステリ長編としては他にイリウ警部ものの『無邪気な遊び』(2004年)、『痕跡なし』(2006年)などがあります。
また、『金の羊毛皮をもとめて』(2013年)、『コンスタンチノープルの秘密』(2015年)などジュブナイルものが3冊あります。少年と少女が謎を追って冒険旅行をする内容のようです。
いかにも心理解剖に執着する作家らしく、パトリシア・ハイスミス『キャロル』やキャサリン・マンスフィールド『アロエ』などの翻訳もしています。
◆欧米ミステリ中のギリシャ人(14)――ロアルド・ダールのギリシャ人――
1941年春からドイツ軍のギリシャ侵攻が始まります。そのころアテネ上空で戦っていたのが、二十歳代の英国空軍少佐ロアルド・ダールでした。もちろんまだ作家になる前のことです。その時の様子が自伝『単独飛行』に描かれています。ノンフィクション作品でミステリというわけでもないのですが(でもハヤカワ・ミステリ文庫)、読んでいてムチャクチャ面白かったのでぜひご紹介したいと思います。
1939年の秋、シェル会社社員として《私》は東アフリカへ出張しますが、第二次大戦が勃発。空軍勤務を志願し即席の訓練を経てカイロへ赴きます。所属の第八十飛行中隊とギリシャで合流した後、ドイツ空軍との凄まじい戦闘に身を投じ、三年後無事に英国へ帰還するまでが、本人の口を通して語られます。
前半のアフリカ編からオモシロ人間が続々登場します。甲板でとんでもない行為に勤しむ軍人夫妻とか、まっとうに見えて食事作法が奇妙な貴婦人とか。英国人が熱帯で何年も暮す場合は奇矯な振舞いによって正気を保つらしい、などとシニカルな観察眼が冴えます。モームの植民地ものに出てくるアクの強い人物たちもそういうことだったんですね。
後半ギリシャが舞台になってから、魅力がさらにヒートアップします。
リビアからひとりぼっちで(その後もずっと「単独飛行」)4時間半もかけてたどり着いたのはエレフシス飛行場。飛行場と言っても、戦時緊急に作った田舎の草っ原です。エレフシスはアテネから20キロほど西にある小さな町で、古代には豊穣の女神デメテルの秘儀が行われ、その娘ペルセポネを冥府の王ハデスが攫って行ったという洞窟があります。
《私》が命じられたのは敵のメッサーシュミット200機に対してハリケーン15機でギリシャ全土をカヴァーすべし(!)、という途方もない作戦。人員が少ないので、「どこにあるのかは知らないが」カルキス上空はお前が担当せよと、なんともアバウトに決められます。カルキス(ハルキダ)はエッセイ第11回でご紹介した島の警官カペタノス警部が活躍するエヴィア島の町です。
その後運命の分かれ道が訪れます。アテネ占領の後ドイツ軍は南下しクレタ島へ侵攻。同僚パイロットたちはクレタ島へ遣られ行方不明となりますが、《私》は中東へ移動を命令され生き延びることになります。
実話ながら、次々と立ちはだかる難関を前にして、いったいどうなっていくんだ、というアリステア・マクリーン調ばりのサスペンスにゾクゾクが止まりません。
ゴチャゴチャ減らず口を叩かず行動する登場人物たちの姿はまさにハードボイルドです。
気に入ってしまった箇所をふたつほど。《私》が飛行機の整備士にかけることばから。
「できるだけ頑張ってなおしてくれ」と、わたしはいった。「たぶんまたすぐ必要になる」。……ふたたび自分の手を見た。それは滑稽なほどわなわな震えていた。しかし気分は爽快だった。
もうひとつは、リーダーの英雄パイロットが撃墜されながらも、生還できた《私》に戦友が顔を洗いながら、
「無事だったか」と、彼は顔もあげずにいった。
「きみも無事だったらしいな」と、わたしは答えた。
……「このつぎはどうなるのかな?」
「たぶん生きちゃいないだろう」
「ぼくもそう思う」と、彼はいった。「もうすぐ洗面器を明けわたすよ。きみが無事に戻るかもしれないと思って、水差しに水を少し残しておいた」
……しびれる。
作品最後の一行のキレ味もすてきです。すさまじい冒険の後こそこんな余韻で終わってほしい。
サスペンス、ハードボイルドと並んでもうひとつ、全体を覆う
レーダーの設置状況を尋ねると、ギリシャ人農民が周囲のすべての山頂に一人ずつ坐っていて、敵機編隊を発見すると作戦室へ連絡するんだ、という答え。いつの時代でしょうか? まるでアガメムノンの頃のよう。
続くやり取りがまたふるってます。
「これがわれわれのレーダーだよ」
「そんなんでうまくいくのかい?」
「うまくいくこともある」
中東への移動には、車にスイカを積み込み(やっぱり「単独」で)トロトロと砂漠を横断したり、「リビアで撃墜された」と英雄並みに報じられたけれど、実は単なる着陸ミスだった、とあっけらかんに暴露してみたり。
うっすらとヴェールのかかったおとぎ話風の雰囲気すらします。(表紙絵にもそのへんがうまく表現されています。)
実を言うと、探偵の一人称語り小説が私はちょっと苦手なのですが、この作品(ミステリじゃないけど)では、むしろ《私》が語るスタイルにこそ魅了されてしまいました。特にとぼけた味の部分です。たぶん自身の体験を45年もたってから距離を置いて執筆している余裕が大きいのでしょう(発表は1986年)。「この話を今イギリスで書いているとひどく滑稽な感じがする」という一節が出てきますが、おれって青かったな、あれでよく死ななかったぜ、という感じで回想され、主人公《私》のハードボイルドなカッコよさと同時に、なんだか間の抜けた部分も指摘されています。
この自分ツッコミが、飄々とした魅力につながっています。
残念ながら、作品中でギリシャ人との交流はほとんどありません。
が、英国人パイロットにオリーブやレツィーナ・ワインをふるまいながら、ちゃっかりお代を請求する地元民たちのたくましい姿には笑ってしまいました。
| 橘 孝司(たちばな たかし) |
|---|
|
台湾在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっと紹介するのがライフワーク。現代ギリシャの幻想文学・一般小説も好きです。 《図書館廃棄本を救え》作戦続行中。今回処分を免れたのは角川文庫四冊もののサマセット・モーム『人間の絆』。主人公フィリップの周囲にさまざまな人間が登場。最初は相手の雰囲気や能力に熱狂し感嘆するのに、観察がシニカルすぎてすぐに幻滅してしまいます。もっとも印象に残るのは何といってもくされ縁の恋人ミルドレッドでしょう。第一印象からして最低、何度再会しても長所がろくに描かれないのにこの存在感とは。 エル・グレコへの作家の思い入れは初めて知りました。 |
| 【《主人公がいかにしてアシェンデンへと成長したのか》が興味のひとつだったのですが、ストーリーはボーア戦争のころで終わってしまい、ラストでコモ湖畔に颯爽と立って「マイ・ネーム・イズ……」とはなりませんでした。】 |
| 【小説は1957年刊ですが、(ウィキ情報によると)1955年6月にフレミングはインターポールの会議取材のためイスタンブールを訪れ、帰りにオリエント急行を利用しています。これが作品中に列車を登場させるアイデアになったそうです。ただし、よく見られるオリエント急行の路線図ではイスタンブール発車後ブルガリアのソフィア、ユーゴのベオグラードと進みますが、ボンドたちはブルガリアに入らず、トルコの国境で列車が二つに分割された後、南のギリシャ国内路線(アレクサンドルポリ、クサンシ、ドラマ、セレス、テサロニキ、イドメニ)を走っています。1950年にトルコとギリシャがNATO加盟し東西冷戦に入っていたため、迂回コースを取ったのでしょう。54年までは西側の人間はブルガリア路線が通過不可能だったようです。ま、イスタンブールではブルガリア人テロ集団に襲われていて(マリリン・モンローの看板の裏にひそんでいたあの人物です)、通りたくもないね、なんてボンド言ってるし。 かくして007はギリシャの鄙びた車窓の旅が初体験できたのですが(行きは一挙に飛行機で。途中アテネの空港で優雅にウーゾ酒を飲んだりしてる)、なんでずっと寝てたんだ、史跡を見そこねたぜと同僚ケリムにつっこまれてます。 ところで、フレミングは滞在中にイスタンブールで起きた大暴動(ギリシャ人街破壊)を取材し、『サンデータイムズ』紙にレポートを載せています。この大暴動こそ、ペトロス・マルカリスが傑作短編「三日間」で細やかに描ききった《九月事件》でした(エッセイ第2回)。】 |

