いただきもの報告です。
■台湾の要有光という出版社から出た燕返の『推理小説家的末日』(2023)
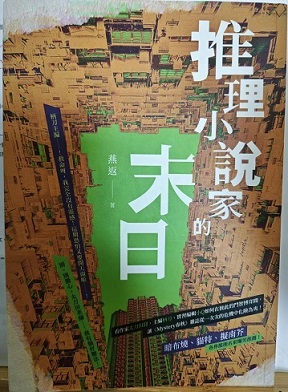
中国大陸で出る中国ミステリー小説はだいたい買うように心掛けているのですが、台湾や香港などで出る繁体字の本は購入するのが若干手間なので、このように恵贈されるとありがたいです。
本書は日本のミステリー小説業界を題材にしたユーモアミステリー短編集です。作者の燕返については、以前、「第79回:SARSと新型コロナをつなぐ17年越しの復讐『残像17』」でも紹介しました。『残像17』もまた台湾の要有光出版から出た繁体字の本で、新型コロナウイルス感染症を巡る院内ミステリー小説ですから、中国大陸で出版できなかったのも納得できる話なのですが、今回のユーモアミステリーまで要有光から出たのはどういうわけかとしばらく考えました。しかしこれは多分、政治的な理由とはほとんど関係ないと思われます。
本書『推理小説家的末日』は、登場人物が日本のミステリー業界で働く作家や編集者ばかりという、オール日本人小説です。要するに大陸の出版社は、中国が舞台でもなければ、中国人キャラクターが出るわけでもない中国ミステリーを、わざわざ出版したくはないと考えたのではないでしょうか。
島田荘司を崇拝する中国人ミステリー小説家・御手洗熊猫の怪長編『島田流殺人事件』が自費出版だった理由の一つは、登場人物が全員日本人だったからだ、とある雑誌社の編集者から聞いています。
ですから『推理小説家的末日』が大陸で簡体字版として出版できなかったのも、無理のない話です。しかしそれによって大勢いたはずの大陸の読者を失うことになりました。ただ、この物語は少なくとも中国では成立しない内容なので、舞台を中国に、登場人物を中国人に「ローカライズ」しても不自然きわまりないものになってしまいます。繁体字版で出せるだけでも、作者は本望かもしれません。
どの短編にも登場するのが、ミステリー小説家の太刀田囧と、雑誌『ミステリー春秋』の編集長の柄刀、それに新人編集者の小Qです。彼らは毎回ドタバタ劇を繰り広げて、ときには殺したり殺されたりすることもあるのですが、次のお話ではみんな復活しているという一話読み切り型の構造で、高橋葉介の『学校怪談』に似ています。
「推理小説家のトロフィー」という短編は、推理小説賞を受賞してこれから作家街道まっしぐらだと意気込んでいた太刀田囧が全くアイディアが出ず、バレないと思ってアルバニアのミステリー小説という超マイナーなところからトリックをパクったら、何故か一発で編集者に見抜かれるという話。
「推理小説家の大会」は、ミステリー春秋が主催する新人賞が、実は才能が枯渇したが新作を出せば必ず売れる太刀田囧に投稿作品のトリックを盗作させる場だったという話。
「推理小説家の追憶」にいたっては、ワガママな太刀田囧が編集部に無理を言って愛蔵版を出したものの、編集者から残酷な提案を強いられて逆に追い詰められるという話です。
もちろんこれらの短い概要が内容の全てではなく、ここから話が二転三転して、意外な人物まで巻き込まれることになるのですが。
インスピレーションが降りてこない、アイディアが出ない、読者が減ったなどは、中国のミステリー小説家にとってもあるあるネタでしょうが、大御所作家が編集部に無茶を言ったり、新人賞を私物化したり、わがままを言ったりという展開はあまり想像できません。そもそも中国にはミステリー関係の小説賞がほぼないし、ベテランと言えるミステリー小説家もほとんどいないし、何よりミステリー雑誌を発行している雑誌社なんか……という状況なので、こういう業界ネタができるのは、良くも悪くも日本のミステリー業界の強さかなと思ったりしました。
■那多『19年間謀殺小叙』(2018)
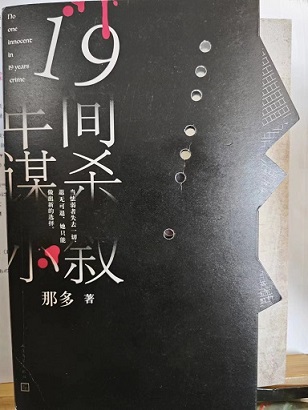
那多はもともとサスペンスホラー小説家という印象が強い作家でした。しかしいつからかサスペンスの方向にハンドルを切るようになって、私はてっきり、中国でホラー描写を書くのも難しくなったからサスペンスに「転んだんだな」と思い、それ以降彼の作品を読むことはありませんでした。しかし、サスペンスホラー小説家の蔡駿の作品が日本で次々と翻訳出版されているいま、サスペンス作家として有名な那多の作品も日本語訳が出る可能性は充分にあるので、最高傑作として評判の本書ぐらいは読んでおこうと思い、手に取ったしだいです。旧友の19年間越しの殺人のツケを、あまり関係のない女性が払うはめになるというダークサスペンスで、世界を敵に回しても約束を果たそうとする女性同士の友情を描いた物語でした。
|
医者を志す大学生の柳絮は、同室の文秀娟から、同じ研究室の何者かに毒を盛られて殺されるかもしれないという不安を打ち明けられる。考えすぎではないかと柳絮は思ったものの、たしかに文秀娟のまわりでおかしなことが起き、その結果、文秀娟は亡くなった。 |
普通の大学生が誰かに毒殺されると訴えたところで、被害妄想だと言われるのが関の山です。当時、本書と並行して春日武彦の『屋根裏に誰かいるんですよ。』を読んでいたので、文秀娟もてっきりその類かと思っていたら、本当に死んでしまったのでビックリしたのを覚えています。しかも犯人は彼女と同じ研究室の誰かで、それが警察にも捕まらず野放しになっていることも恐怖です。
柳絮にとって生前の文秀娟は謎に包まれた人物でした。調査で彼女の実家に向かうと、上海のお嬢様だと思っていた彼女は下町出身で、父親は娘が謎の死を遂げたというのに調査に非協力的。どうやら彼女は大学に来るまでに、人には言えない何かをやっていて、父親はなんとなくそれに感づいている、という空気が伝わってきます。そのうえ協力者の郭概が何者かに殺害され、9年前に文秀娟を殺した毒殺犯がまだ自分のそばにいるのではないかという不安が募ります。
物語が文秀娟の子ども時代に移ると、文秀娟の評価が百八十度変わる事実が次々と明かされます。どうしてあれほど毒殺を恐れたのか、どうして父親から死を悲しまれていないのか、どうして殺されるほど恨まれていたのかなど、数々の理由が分かるにつれ、文秀娟の死は必然だったとやるせなく思ってしまいます。
そして物語は柳絮のたった一人の戦いへと続きます。協力者の郭概は死に、自分の夫すら、文秀娟と同じ研究室にいたため毒殺犯の可能性もゼロではないという状況になっても、文秀娟の死の真相を調べようとします。いままでおとなしく生きていた女性が野心家だった死んだ友人のために命をかけて奮闘するさまは美しさすらあり、また身勝手にも感じました。
本書は映像化がすでに決定していますが、文秀娟と柳絮の時間を超えた友情と、柳絮から文秀娟への届くことのない一方的な感情がどう描かれるのか、いまから楽しみです。
| 阿井幸作(あい こうさく) |
|---|
|
・ブログ http://yominuku.blog.shinobi.jp/ |
●現代華文推理系列 第三集●
(藍霄「自殺する死体」、陳嘉振「血染めの傀儡」、江成「飄血祝融」の合本版)
●現代華文推理系列 第二集●
(冷言「風に吹かれた死体」、鶏丁「憎悪の鎚」、江離「愚者たちの盛宴」、陳浩基「見えないX」の合本版)
●現代華文推理系列 第一集●
(御手洗熊猫「人体博物館殺人事件」、水天一色「おれみたいな奴が」、林斯諺「バドミントンコートの亡霊」、寵物先生「犯罪の赤い糸」の合本版)
 中国ミステリ愛好家。北京在住。現地のミステリーを購読・研究し、日本へ紹介していく。
中国ミステリ愛好家。北京在住。現地のミステリーを購読・研究し、日本へ紹介していく。