この数カ月、諸々の理由で読書をする時間すらなかった反動で、6月~7月はかなりの積ん読を消費することができました。今回は、この1カ月で読んだ本の中から3作品の中国ミステリーを紹介します。
■王稼駿『女神』

王稼駿といえば、島田荘司推理小説賞に何度も応募しては一度も入賞できていなかったり、以前このコラムでも取り上げた『再見、安息島』(さよなら、安息島)のように、ミステリーの構成力が弱いという、よりによって推理小説家として致命的な欠点があったりと、不遇なイメージがつきまといます。そんな彼がなんと◯◯ミステリーに挑戦。(例えば歴史ミステリーならわざわざ「歴史」を伏せ字にする必要がないので、この処理は全く意味をなさないのかもしれない)。
実はこの作品、2021年の第7回金車・島田荘司推理小説賞の一次選考を通過しているんですが、その際、王稼駿は小鎮青年というペンネームを使っています。
| 会社が火の車で借金取りに追われている「わたし」こと丁捷は、一刻も早く両親の遺産を相続する必要があったが、そのためには長年音信不通の姉の丁敏から承諾を得なければいけなかった。姉が住んでいるという部屋に行くと、彼女と背格好がよく似た別人の女の死体があった。そしてさらに姉の所在を探すと、「雲端」というマルチ商法とカルト宗教が組み合わさったような怪しい組織にいることが分かる。なんでもそこには難病を治す奇跡を起こせる女神がいるらしい。「雲端」に潜入した「わたし」は、組織の幹部から向けられる疑惑の視線をかわしながら姉の行方を追う。 |
あらすじだけ書くと単なる潜入サスペンスものですが、悪質なマルチ組織の処方箋として読むだけでも楽しめます。事前に恋人と打ち合わせをして、自分が金を要求したら有無を言わさず振り込んでくれと頼み、組織内を短期間でのし上がっていくシーンなどは、実際の潜入捜査でも使っていそうな手口です。しかし最大の見所は、丁捷の正体が◯◯だったと明らかになるところです。それによって、丁捷がどうして恋人の夏陌の家族から邪険に扱われていたのかが分かりました。
「雲端」潜入前、丁捷は夏陌の家に招待されるのですが、彼女の親や親戚から全然歓迎されていません。このとき、借金のことは夏陌たちにバレていないので、てっきり性格や相性が合わないから疎まれているのだと思っていましたが、そりゃあ娘が連れてきたのが◯◯だったら、親としてはけっこう抵抗あるかなと納得。ただ、現代中国を舞台にした作品で、丁捷のような人間が果たして夏陌の家族に会いに行くかなと疑問に思い、このエピソードをミスリードとして使うのはちょっとアンフェアだと感じました。そして丁捷が◯◯だったことが読者へのサプライズになったのはともかく、作中でうまく活かされていないのももったいなかったです。
内容が内容だけにあまり多くを説明できない作品で、中国最大のレビューサイト「豆瓣」でもレビュー数が全然少ないのが本当に残念です。多作な王稼駿の代表作と言っても過言ではないので、評判を知って読者が増えることを祈っています。
■曹操『金宮案』

曹操という一度聞いたら忘れられない芸名で、中国で十数年間も活動しているアメリカ人俳優が書いたサスペンス小説『The Eunuch』の中国語訳版です。こういう中国語タイトルになったのは、金王朝の宮廷を舞台にしているからなのでしょうが、ロバート・ファン・ヒューリックのディー判事シリーズにある『中国黄金殺人事件』の中国語タイトル『黄金案』なので、それにもかかっているのかもしれません。
以前、イタリア人作家 Elsa Hart が中国の清代を舞台にしたミステリー『JADE DRAGON MOUNTAIN』を紹介したことがありますが、曹操はこれまで出演した時代劇で培った古代中国の知識を活かして本作を書いたのでしょう。
| 宮中で一人の側室が殺された。宮廷の外は門番が見張りをしていて、門は中から開けられないようになっているため、部外者の犯行とは思えない。事件の捜査を命じられた宦官の納謀魯取は証拠を集める中で、側室を殺したのは皇帝だという認識を強め、捜査で間違った選択をしたら自分の命も危ういと悟る。どうにかして皇帝の母親である皇太后を味方につけた彼は、権謀術数渦巻く宮廷で綱渡りの推理を展開しながら、事件の真犯人ではなく真相を探ることになる。 |
一般常識的に、殺人は犯罪であり、罪を犯した人間は官憲に捕まって司法に裁かれるのが望ましいです。探偵が事件を推理することと犯人を捕まえることはイコールではありませんが、真相を知り、明らかにすることこそ名探偵の習性であり、そのためになりふり構わないのは名探偵に必須のスキルです。しかし、他者の生殺与奪を自由にできて、法の枠外にいる人物と同じ空間で殺人事件の推理をする探偵って、いったいどういう気持ちなんでしょうか。
本作では序盤から、探偵役をはじめ宮中の重臣たちが殺人事件の真犯人を何となく察するのですが、相手が相手だけに誰もそのことを口にしません。納謀魯取たち宮中で働く人間は、お互い腹の中を探り合い、失言がないよう必要最低限のことしか喋ろうとしません。例えば——
「それは何だ?」
「それとは?」
「◯◯のことだ」
「☓☓です」
「☓☓とは何だ?」
こんな感じで、会話のキャッチボールが至近距離すぎて、読んでいてまだるっこしいわけですが、宮廷の閉塞した空気感をうまく表現できていたかなと思います。
納謀魯取がすることは、証拠集めではなくその動機を探ること。皇帝が真犯人だとしても、「犯人はお前だ」と指摘できる人物は国中一人もおらず、証拠固めをしても無意味だからです。一方、納謀魯取に事件の捜査を命じたのがその皇帝本人ですから、捜査を適当に済ませるわけにもいきません。
皇帝の側室殺しが事実だとしたら、その理由は何か? だって皇帝なら何かと理由をつけて側室一人を処刑することぐらい簡単でしょうに。すると中盤で、死んだ側室が残したとされる日記が怪文書のように宮廷に広がり、そこには「皇帝は不能」というとんでもないスキャンダルが書かれていました。関係者がどんどん処刑され、納謀魯取もいつ処分を下されるか分からない状況になり、しかも何者かから暗殺者まで差しむけられて、まさに薄氷を踏む思いで捜査を進めます。容疑者が司法の手の届かない人物だという理由で、捜査にここまで気を使う探偵もいないんじゃないでしょうか。
本作の最大の売りはやっぱり、中国では結構有名なアメリカ人俳優が書いた本(原文は英語)というところですが、物語の着目点は中国に長く住む外国人ならではだなと感じました。物語のキーマンである皇帝は暴君というほどではないですが、金王朝を支配する女真族のトップとして漢族を見下していて、殿試(科挙の最終試験。皇帝自らが出題する)でも、漢族の進士たちに暴言を吐く始末。著者の曹操は、国のトップが差別主義者だった不幸を書くことで民族融和というメッセージを打ち出しているように見え、その考えに至るのは中国に長くいる同じ外国人としてとても理解できました。
翻訳にかなり気合いが入っているため、文章がとても古風で、中国の時代小説を読み慣れていない者にはあまり頭に入ってこない作品でしたが、内容自体は「アメリカ人俳優曹操が書いた中国歴史ミステリー小説」というインパクトに負けないしっかりしたものだったので、日本人にも読まれてほしいですね。これ逆に英語の原文の方が読みやすかったりして……
■凌小霊『奇跡降臨之前』
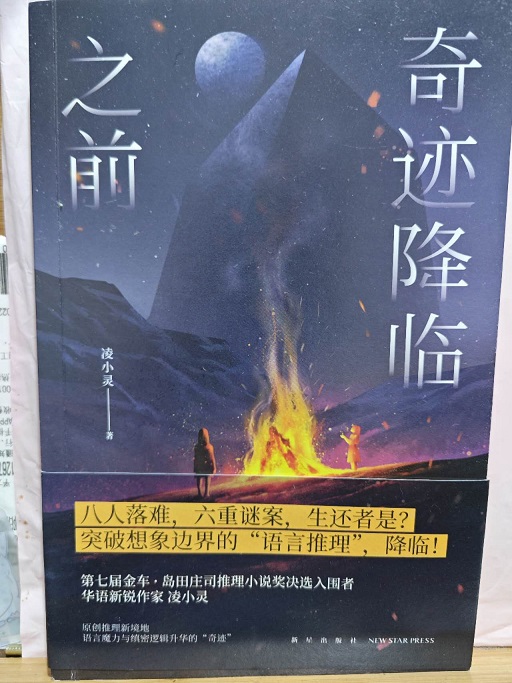
言語ミステリーという触れ込みで登場した話題作。作者の凌小霊は復旦大学の推理協会(ミス研)出身で、陸秋槎の後輩に当たります。『隨機死亡』が2021年の第7回金車・島田荘司推理小説賞の一次選考を通過し、短編の「星の悲劇」が風狂奇談倶楽部で犯人当て作品として選ばれて翻訳までされているので、日本にも知っている人がいるのではないでしょうか。
| 家出した妹の部屋に残されていた一枚の切符を頼りに、妹の行方を追う沈一心。彼女が利用したとされる旅行会社のバスに乗ったところ、そのバスが事故で谷底に落下。なんとそこには、既存の現生人類とは異なる進化をたどり、原始的な生活を送り、中国語とはまるっきり異なる独自の言語体系を持つ谷底人、そして妹の沈天問がいた。助かったと安堵するのもつかの間、同乗者が何者かに殺されてしまう。果たして犯人は谷底人か、それとも自分たちの中にいるのか……。同乗者の一人、占い師の凌暁月は谷底人たちの会話を分析することで、彼らが殺人事件にどう関わっているのか解き明かそうとする。 |
ここで出てくる谷底人は、未接触部族というわけではなく、我々人類とは全く別のルートで猿から進化した原始人で、会話で交流をするし、宗教も信じていますが、喋ってることは全く分からないし、信じているものも全然違うという人々。そんな彼らに対し、「対不起」(ごめんなさい)が口癖のコミュ障卑屈占い師の凌暁月が、聞いたことをほとんど覚えていられる脅威の記憶力と、どんな点と点をも結び付けられる推理力を使い、彼らの言葉を翻訳します。
谷底人が使用する谷底語は作者が一から創作した言語で、きちんとした法則性があるので、凌暁月の推理をちゃんと理解すれば読者もその言葉の意味が分かるようになっています。しかし実際問題、未知の言語を話す話者同士の会話を聞き、この言葉はこういうシーンでよく使われているからこういう意味だろと推理するだけで、言葉の意味を理解し、話者と交流をすることは可能なのでしょうか。多分無理だと思います。
一般的なミステリー小説では、犯人が一見実現も再現も不可能な犯罪をやってのけますが、本作では探偵が他者では絶対に不可能な推理をやっているわけです。未知の言語を短時間で理解するなんて、往年の名探偵でも無理でしょう。
谷底語を分析していくと、谷底人独特の文化も分かり、彼らにはこういうタブーがあるからこういうことはしない、こういう風習を持っているからこういうことはできない、と行動の枠を制限し、推理の範囲を狭められるようになります。そうやって谷底人全体を一括りにするのは早計じゃないかとも思うのですが、実は谷底人の最も奇妙な特徴が、昆虫みたいに個がなく、一つの集団として行動するところなので、谷底人一人がやらないことは、全員やらないのと同義なのです。
没個性的な登場人物はミステリー小説にたまに出てきますが、この作品では個を持った人間が一人もいないグループが主人公たちを遠巻きに見守るというなんとも不気味な光景が繰り広げられます。そして終盤、主人公たち部外者に触発されて、谷底人たちに変化が生じるのですが、それはまるで四足歩行から二足歩行への移行を見ているようで、存在が曖昧な群れの中から自立した個が生まれることで、谷底人ははじめて容疑者の一人となるのでした。
実はこの作品、他にもツッコミどころが多く、レビューサイトでもさまざまな指摘を受けていて、評価は賛否両論です。ただ、言語ミステリーに挑戦したという心意気は買われていて、私もたいへん面白い作品を読ませてもらったと感じ入りました。しかし、本書が紆余曲折を経て日本で出版されるということになれば、ぜひ加筆修正をしてから翻訳されてほしいと切実に思います。
今回も個性的な作品を紹介できたと思いますが、自分の家にはまだたくさんの中国ミステリー小説が積まれていて、読んだけれどレビューを書いていない本もあるので、そろそろ本格的に需要が追いつかなくなってきた感じです。その上、映画やドラマまで新作が出るので、まだまだコラムのネタは尽きないなと安心するやら骨が折れるやら。
| 阿井幸作(あい こうさく) |
|---|
|
・ブログ http://yominuku.blog.shinobi.jp/ |
●現代華文推理系列 第三集●
(藍霄「自殺する死体」、陳嘉振「血染めの傀儡」、江成「飄血祝融」の合本版)
●現代華文推理系列 第二集●
(冷言「風に吹かれた死体」、鶏丁「憎悪の鎚」、江離「愚者たちの盛宴」、陳浩基「見えないX」の合本版)
●現代華文推理系列 第一集●
(御手洗熊猫「人体博物館殺人事件」、水天一色「おれみたいな奴が」、林斯諺「バドミントンコートの亡霊」、寵物先生「犯罪の赤い糸」の合本版)
 中国ミステリ愛好家。北京在住。現地のミステリーを購読・研究し、日本へ紹介していく。
中国ミステリ愛好家。北京在住。現地のミステリーを購読・研究し、日本へ紹介していく。