「どくミス!2025」に熱い投票をいただきありがとうございました。第一位となったのは、M・W・クレイヴン『ボタニストの殺人』(東野さやか訳 ハヤカワ・ミステリ文庫)でした。おめでとうございます。
今回は一三〇名のみなさまに投票をいただき、六十六作品がリストに挙がりました。結果一覧および作品へのコメント一覧は読書会のサイトで配布しておりますので、そちらをぜひご確認ください。順位も楽しみではありますが、まだ知らない作品や作家との出会いもまた大きな楽しみです。これからの読書計画のお供にご活用ください。
また、五月二四日におこなった発表イベントも YouTube にて配信中です。観覧されたみなさんのチャットもお楽しみいただけますのでこちらもぜひ。
来年も同じ時期に「どくミス!2026」として開催する予定です。今年一年を通してまたたくさんの翻訳ミステリー小説が刊行されると思います。「どくミス!」のこともちょっとだけ頭の片隅に置きながら、読書をお楽しみいただければと思います。
ということで今回はカミラ・レックバリ、ヘンリック・フェキセウス『奇術師の幻影』(富山クラーソン陽子訳 文春文庫)をご紹介します。ストックホルム警察特捜班の刑事ミーナと凄腕のメンタリストであるヴィンセントが活躍するシリーズ第三弾にして完結編です。
上にも書いたように、主人公はストックホルム警察の刑事ミーナとメンタリストヴィンセントです。と書くとこのコンビが事件の謎を解く警察小説である、と考える方がほとんどでしょう。それは確かに間違ってはいないのですが、ちょっと説明が必要でしょう。
ミーナはビニール手袋なしではものにも触れられない、会議室に供されるペストリーの類いも「誰の手に触れたかわからない」といって食べられない、下着は毎日使い捨て、消毒液の使い過ぎで手は荒れ放題、肌が赤くなるほど熱いシャワーを一時間ほども浴びないとすまないなど、日常生活に支障が出るほどの潔癖症です。一方のヴィンセントも、テーブルの上にペットボトルが三本あれば、冷蔵庫から一本出してきて四本にしたり、かごに入ったクッキーの数が偶数になるよう食べて調整したり(誰かが食べたら自分も食べて偶数にする)など奇数をやたらと嫌う性質で、とにかく身の回りにある数字が気になって仕方がない。そしてそれが奇数だと自分の調子にまで影響するというこちらもまた奇妙な性癖の持ち主なわけです。このような特性が影響して、二人とも周囲とのコミュニケーションにはやや困難を抱えています。ミーナはチームのメンバーから奇異に見られているし、ヴィンセントは家族との関係があまりうまくいっていない。
そんな二人は、第一作『魔術師の匣』で奇術のトリックを模した殺人事件を解決するため、専門家の意見を乞うべくヴィンセントのもとをミーナが訪れたことがきっかけで出会うのですが、ヴィンセントはメンタリストとしての能力を発揮して、ミーナの特性をいち早く見抜きます。そして、ミーナもそのことに気づき、二人は会うたびに互いを意識していきます。けっして阿吽の呼吸とか以心伝心などといった言葉で表現できるコンビではない、どちらかというとぎこちなさがつきまとう二人なのですが、根底の部分では互いのことがよくわかっているという、ちょっと不思議なコンビなのです。
本作『奇術師の幻影』は、ミーナの前夫であるニクラスのもとに、差出人不明の封筒が届くところから始まります。なかには電話番号の書かれた名刺が一枚。その番号にかけてみると録音されたメッセージが流れてきました。
「お客様の命は、あと……十四日間……一時間……十二分です」
ニクラスはこのメッセージの意味するところに気づくのですが、そのことを娘のナタリーやミーナには伝えることができません。
一方、ストックホルムに張り巡らされている地下鉄のトンネルでは人骨の山が発見されます。骨折の跡や歯の治療歴などから、数ヶ月前に失踪した実業家であることが判明するのですが、そのあとも三体分の人骨が発見されることによって、事件は混迷の途をたどります。特捜班は、過去二回の事件をともに解決したヴィンセントの助けを得ながら真相を探っていくのですが、そのヴィンセントにもまた危機が迫っていました。人骨の謎、ニクラスの死へのカウントダウン、そしてヴィンセントに迫る謎の影。これらが渾然一体となって衝撃の結末へとなだれ込むのです。
と、ストーリーについて書けるのはこのくらいでしょうか。ひとつひとつの謎の魅力、そしてミーナやヴィンセントが如何にして真相にたどり着くのかという、ミステリーとしての骨格がとてもしっかりしているのはもちろんなのですが、このシリーズ全体の特色としては、ミーナやヴィンセントに限らず、特捜班の面々のプライベート描写に分量を割いているということが挙げられます。
たとえば班長のユーリア。一作目では妊活していた彼女もやがて子供が生まれ、育児の苦労のなかで夫との関係性が少しずつ変化していくさまが描かれます。一作目、二作目の登場人物紹介で好色漢とされたルーベンは、二作目で知った事実により気持ちに変化が生まれ、今作での紹介では「好色漢」の文字がなくなっています。班の最高齢、ベテラン刑事のクリステルは、昔ある事情で別れてしまった同性の友人と数十年ぶりに再会し、和解し、再びパートナーとなるまでが描かれます。一作目の事件で引き取ることになったレトリバーのボッセもクリステルの行動に大きな影響を与えます。
当サイトの人気連載「書評七福神」二〇二二年九月の記事において北上次郎さんが一作目『魔術師の匣』を評して、《つまり余分な要素だ。これらを切り落とすとこの物語はたぶん半分になる。無味乾燥のストーリーだけになる。ようするにこの余分な要素が物語に奥行きと臨場感とダイナミズムを与えているということだ。》と書かれているのですが、確かにそのとおりで、彼らの私生活を垣間見、読者が思い思いの感情を彼らに寄せることによって、一作ごとに深い感慨を与えていくのです。
それだけに、本作のラストはあまりにも意外過ぎる。帯にも文藝春秋のサイトにも「ドンデン返し」という言葉が使われているので、それなりの覚悟をして読むわけですが、それでも仰天してしまう。これを受け入れられないという読者もそれなりにいるのではないでしょうか。そのくらい衝撃的。そして、登場人物たちに感情移入すればするほど、この結末を知った読者のなかに切なさややるせなさという感情を呼び起こします。周到に準備されたドンデン返しだけではなく、読者の心情にまで訴えかけてくる効果までも最初から狙っていたのだとしたら、これはもう感服するしかありません。
できれば一作目から順に。どうしてもという方は三作目を読んでから一作目、二作目に戻るという読み方でもいいと思います。事件を追いつつも日々の暮らしのなかで右往左往する刑事たちの心情が魅力的に描かれた小説なので、どのように読んでも読者の胸を強く打つことは間違いありません。ひとつだけ忠告しておくと、本当に結末に驚きたいという方は今作の解説は必ずあとから読んでください。先に読んじゃうと勘のいい方なら気づいてしまうかもしれませんので。
| 大木雄一郎(おおき ゆういちろう) |
|---|
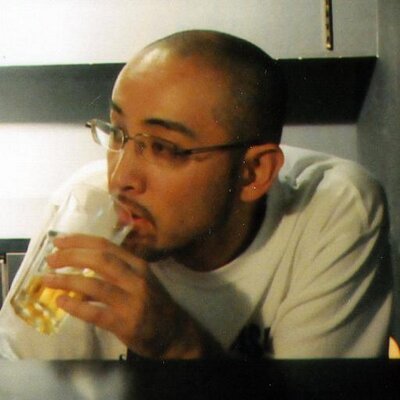 「どくミス!2025」への投票ありがとうございました。次回もみなさまに楽しんでいただけるようがんばります。翻訳ミステリーがもっともっと多くの人々に読まれますように! 「どくミス!2025」への投票ありがとうございました。次回もみなさまに楽しんでいただけるようがんばります。翻訳ミステリーがもっともっと多くの人々に読まれますように! |