みなさま、カリメーラ(こんにちは)!
ギリシャと深いつながりのある国、と言えばやっぱりお隣りのイタリアです。
古代からの結びつきは言うまでもありませんが、現代でもともにEU、NATO、地中海連合に属しており、政治、経済、文化面で緊密な関係にあります。ギリシャの貿易相手国としてイタリアは輸出入額ともドイツに次ぐ第二位。ギリシャ人学生の留学先としても英国に次いで第二位の人気があります。
関係の深さは言語面にも現われています。ギリシャ語に流れ込んだ外来語のうち、数がもっとも多いのもイタリア語です(次いでトルコ語)。古い調査ですが、ギリシャ語中の外来語のうちイタリア語は三割を占めているそうです。
ミステリ作品でよく見かける外来語の例をちょっとだけ挙げておくと、ギリシャの探偵に欠かせないτσιγάρο(ツィガロ)「タバコ」はイタリア語sigaro「葉巻」から来ています(一方、「葉巻」はギリシャ語ではπούρο(プーロ)と言い、スペイン語puro「純粋な(タバコ)」からです。「タバコ」「葉巻」のこの意味のずれはお隣のトルコ語やブルガリア語でも同じ)。マフィアのボスの身辺警護をする μπράβος(ブラヴォス)「用心棒」はもともとイタリア語bravo「すぐれた、勇敢な、(用心棒の意味もあり)」。麻薬をめぐって売る側と買う側は βαποράκι(ヴァポラキ)「麻薬の売人」と πρεζόνι(プレゾニ)「麻薬中毒者」ですが、いずれもイタリア語vapore「蒸気船」、presa「(薬の)一服」からです(前者の意味変化が奇妙ですが「調達する者」ということでしょうか)。最後に、γκόμενα(ゴメナ)「愛人、魅惑の美女」がgommina「小さなゴム栓、髪につけるジェル」から(この変化も不思議)と来れば、ちょっとしたノワールになりそうです。
しかし、こういった数字や例以上に、両国は同じ地中海の民、南欧人として、気質的に合うところがあるようです。以前知り合ったアテネのみやげ物屋のコスタスじいさんは、イタリア人観光客が来るたびに「わしらは
近代史の点から言うと、第二次大戦中にギリシャは独伊ブルガリアの枢軸国側に占領されていましたが、緒戦のアルバニア戦線で撃退した相手であり、大戦末期に降伏して連合国側についたイタリア軍に対するのと、抵抗した村落を徹底的に破壊した冷徹なドイツ軍とに対してでは、心情にかなりの差があるようです。
このへんは文学作品中での取り扱いの差にも現われています。
例えば、女性作家リリカ・ナークの短編集『子供たちの地獄』(1944年)は小学校の国語の教科書にも載っている作品です。抜粋部分では、占領下のアテネで物乞いをし、夜は洞窟で眠る子供たちが若いイタリア兵ジョヴァンニと知り合います。子供たちは親しみを感じ、敵方のはずのジョヴァンニもパンやチーズを分けてくれますが、しかし、その後イタリアが連合軍と和睦しドイツに敵対することになったため、ジョヴァンニたちはドイツ軍に引き立てられ、子供たちは不安な眼差しで見守ります。
 リリカ・ナーク『子供たちの地獄』 エスティア社、1944。 |
ストラティス・ミリヴィリスの短編「パングラティスが英雄になれなかった理由」(短編集『赤の本』1952年)は新兵パングラティスがマケドニア東部の町セレスでイタリア軍小隊の捕虜となり殴られ侮蔑されますが、なぜか途中で相手の態度が急変し、親しげに肩をたたいて、チョコやタバコをくれたりします。実はこの小隊はアルバニア戦線での劣勢に絶望し早々と投降を決めたのでした(その後ドイツ軍の侵攻でギリシャは占領されることになるのですが)。ミリヴィリスは代表作『墓の中の生』で塹壕戦の閉塞的な恐怖をリアルに描いていますが、この短編は辛辣なユーモアにあふれています。
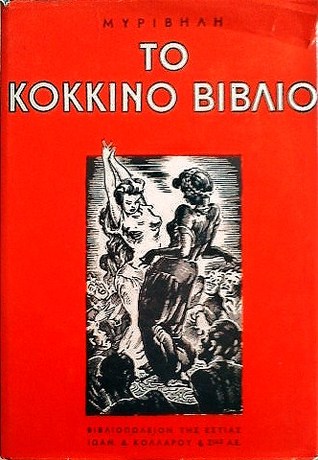 ストラティス・ミリヴィリス『赤の本』 エスティア社、1952。 【二つの大戦間に綺羅星のごとく現れた《三十年代派作家》のひとり。リレー小説『四人の物語』にも参加、主人公男女の反目と和解を骨太に描きました(エッセイ第10回)】 |
ミステリ小説にももちろん占領下を扱ったものがあります。ヤニス・マリスの(ベカス警部シリーズではない)戦争スリラー『虹作戦』(1966年)では主人公の青年フォティスが父親救出にラリサ市へ向かう途中、若いイタリア軍曹に遭遇し怪しまれますが、「父さん、逮捕……銃殺……」と片言のイタリア語で懇願すると、お情けで許されます。これに対して、フォティスがある任務を帯びて潜入したアテネで出会うドイツ軍人と言えば、高慢で冷酷な《少佐》だの、無表情で人を拷問にかける《機械男》だの絵に描いたような悪役たちです(この作品は次回のエッセイで取り上げる予定)。
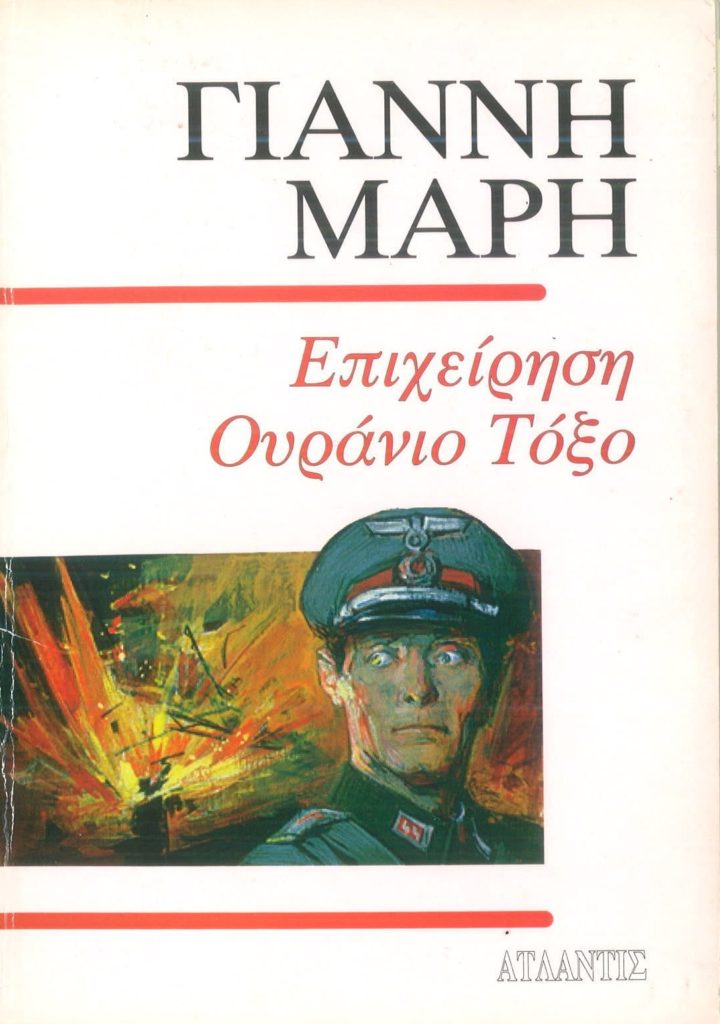 ヤニス・マリス『虹作戦』 アトランディス社、1966。 |
今回ご紹介するディミトリス・ママルカスはイタリア愛が嵩じて、かの地を舞台にしたミステリを描き続ける作家です。ギリシャ人はほとんど出てきません。ここまで入れ込む作家は他に見当たらないので、一匹狼の《イタリア派》と勝手に命名しておきます。
ママルカスは1968年アテネ生まれで、若いころからイタリアに惹かれていたのでしょう、南部のレッチェ大学に留学し学位を取っています。
デビュー作は1999年の『酒ある限り望みあり』なので、《六歌仙》の後を継ぐ第三世代「興隆期」に当たります。インタビューによると、この世代の作家はミステリ作品の舞台をアテネの街角から国外へ広げようとする傾向があるそうで、イタリア贔屓のママルカスはその最たるものでしょう。
続く『ヴォタニコスの大いなる死』(2003年)はアテネの西部地区で展開する犯罪ものですが、第三長編『出版者の誘拐』(2005年)は主人公のイタリア人作家が、自分を破滅させた女に対して、彼女の愛人である出版者をも巻き込みながら復讐に突き進む姿を描く、《イタリアもの》の嚆矢のようです。
続く『ディミトリオス・モストラスの失われた蔵書』(2007年)は、同年の《ギリシャ民族書籍センター(ΕΚΕΒΙ)》主催の「読者賞」にノミネートされており(ジャンルにかかわらず読者に支持された小説が対象)、なかなか評判よさそうなので読んでみました。
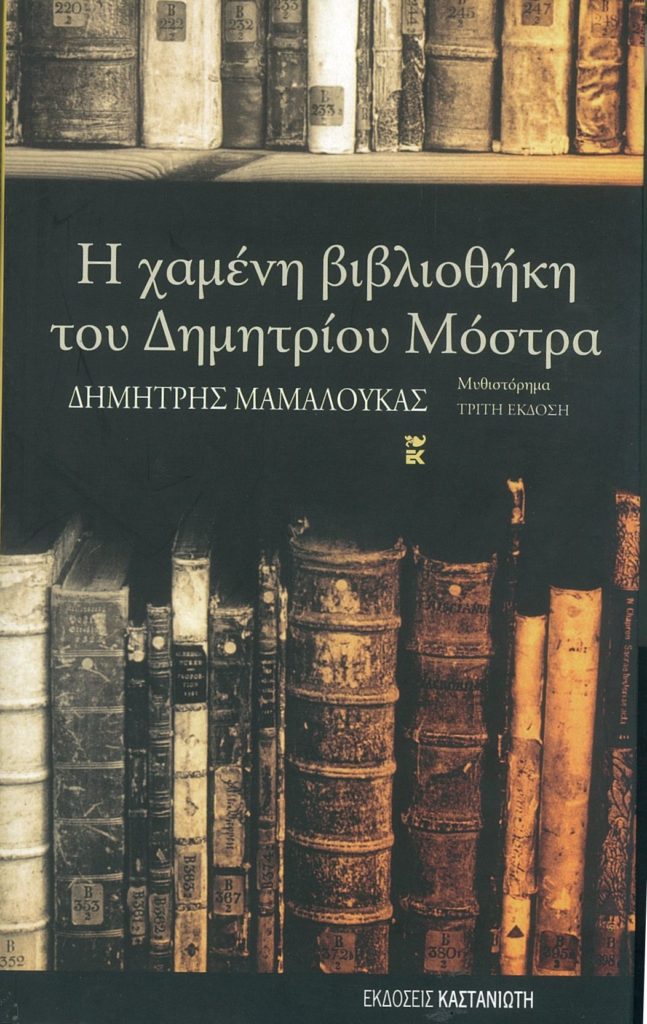 ディミトリス・ママルカス『ディミトリオス・モストラスの失われた蔵書』 カスタニオティス社、2007。 【このカバー、そそられます】 |
一人称の語り手ニコラ・ミラノはギリシャ人外交官の父とイタリア人女性との間に生れました。その後父もアテネの正妻も亡くなり、祖父の代から収集してきた六千冊もの蔵書を遺贈されます。定職は持たず、この貴重本を売ることで生計を立てている優雅な身分です。ギリシャ語については、辞書を引き引きなんとか書名くらいは読めますが、会話はほとんどできないらしい。恋人ダニエラは2000年にサラエヴォから逃れてきたといいますから、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の犠牲者でしょう。
相棒のガブリエーレ(ガービ)・アッビアーティは裏社会に通じた無免許の探偵です。ローマ中心のデッレ・ボッテーゲ・オスクレ通りの部屋は、古書、レコード、コミックに溢れています。犯罪事件があると勝手に現場へ入り込み調査やら撮影録音しては(警官とは懇意なのでお目こぼし)、資料をためて個人アーカイブを作っている犯罪捜査オタクです。
閑人の《わたし》ニコラはガービから探偵術の手ほどきを受けて助手役に納まっています。ギリシャ人作家によるイタリア人のホームズ&ワトスンですね。最初は二十代の若手コンビかと想像していた(私の脳内では初めからベネディクト・カンバーバッチの顔)のですが、ともに四十代だと明かされます。
探偵ガービのほうが主役なのでしょうが、ちょっと気になるのは、かつてミラノに在住し、1970年代にイタリアを騒がせた極左組織《赤い旅団》との関係が暗示されている点です。ただ、この作品の中で焦点があてられるのかどうかは分かりません。
ある日、《わたし》は古書マニアである車椅子のアルドと妻モニークの訪問を受けます。アルドはディミトリオス・モストラスなる人物の蔵書を探しているといいます。あるいはモストラスへの献辞入りの本でもいいのだが、と奇妙なこだわりを見せますが、しかし、公共図書館にならモストラス寄贈本がすでにあるのになぜ?と《わたし》は怪しみ始めます。
モストラスは18世紀から19世紀にかけて活躍した実在の人物です。アルタとナフパクトス主教イグナティオスの秘書官を務め、初代ギリシャ大統領カポディストリアスの知己でもありました。イタリアのピサに居を構え、一万二千冊という途方もない蔵書を収集。後にギリシャ西方のケルキラ島へ移り住みましたが、経済的苦境から蔵書を売り払ったといいます。
後日スクラスなる別のギリシャ人が、同じように稀覯本を高額で買い取りたいと《わたし》の前に現れます。馬のように嫌らしい笑い声(どんな?)、傍らには二メートル近い屈強なボディーガードを侍らせ、見るからに悪役の風体です。アルドとは古書取集の盟友だと漏らしますが、なにか因縁があるのでしょうか。いやそもそも、モストラスの蔵書にはどんな意味があるのか? なぜ二人が別々に狙っているのか?
中盤でモストラス蔵書の数奇な因縁話が語られ、読者をどんどん引き込んでいきます。古書ミステリの醍醐味ですね。
モストラスは将来独立した同胞民族(ギリシャ革命戦争の前の話です)へ、文化遺産として蔵書を遺贈するつもりでした。しかし、ケルキラ島に移住したとき、最も貴重な二千点は送らなかったそうです。ということは、桁違いの高値のつく稀覯本は今もイタリアに遺されているのか?
《わたし》&ガービのイタリアを縦断する宝探しの旅が始まります。献辞に隠された暗号の導きにしたがって二人はヴェネチアへ。同じ獲物を狙うアルドやスクラスの危険な影がちらつきます。
これと絡んでもう一つの大事件が進行中。こちらは現代に根がありそうです。
かつて凶悪な婦女暴行や幼児暴行で服役した元受刑者たちが殺害される奇怪な事件が頻発します。犯人グループは第一章から《アンチモストリ団》(つまり《反怪物団》)の名で登場します。《力》、《思考》、《忍耐》といったコードネームを持ち、闇の仕置き人というところです。
《わたし》の恋人ダニエラが、なぜかこのグループのスナイパーに狙われるところから、二つの事件が交錯していきます。当然、警察も《アンチモストリ団》の捜査に動きます。こうして消えた蔵書を探すグループ、闇の仕置きに突っ走る一団、これを阻止しようとする警察の三つ巴、四つ巴の抗争がイタリアの北と南で展開します。
《アンチモストリ団》事件では警察や《わたし》との駆け引きがストレートに展開し、アクションとスリル全開で読者を否応なく引っぱっていきます。
ただ、個人的には失われたモストラス蔵書の因縁話のほうに魅了されました。19世紀の実在の人物を絡めた歴史の謎も魅力満載だし、ヴェネチアの古屋敷での冒険も筆に力が入っています。作者はポオの「アモンティリャドの酒樽」や「陥穽と振り子」が好きなんだろうなと感じました。(インタビューでも、ミステリ好きの少年少女に薦める作品は?の質問に「黄金虫」と答えています。ミステリ作家もファンも、出発点はみんな一緒ですね。)
最後には、さる場所で失われた蔵書が威容を現し、その運命には読者も息をのむことになります。映像化されたらきっと映えることでしょう。
◆ 探偵コンビの復活
前作から何と九年を経て、ガービと《わたし》のコンビが帰ってきました。2016年発表の第五長編『赤い旅団の隠れた中核』です。
 ディミトリス・ママルカス『赤い旅団の隠れた中核』 ケドロス社、2016。 |
書名から想像されるように、(前作では描かれなかった)《赤い旅団》の活動が主要なモチーフのようです。1970年代から80年代にかけてイタリア北部でテロ活動を過激化させた極左グループで、1978年には元首相モーロの誘拐殺害事件まで起こしています(この事件のショックがママルカスの作品執筆のきっかけになったらしい)。しかし80年後半になるとメンバーの逮捕などから衰退し、その後壊滅したとされています。
今作は古書奇譚とはテイストの異なる政治ミステリになるのでしょうか。
1979年春。《赤い旅団》の分派《フランチェスコ・ロルーソ》がミラノで初めてのテロ活動を起こそうとしています。ある工場経営者を誘拐する作戦ですが、充分な下調べにもかかわらず、どこかで狂いが生じて警察と銃撃戦になってしまいます。グループのリーダーも、人質の経営者も射殺され、警官にも死傷者が出ます。
いきなりの大アクションで幕を開けた後、時間は跳んで2007年へ。
二人のアクの強い人物が登場します。
まずはフィレンツェ山間の別荘にこもるミステリ作家バッターリア。スランプ気味で ここ数年ヒット作がなく、酒浸りの毎日です。高利貸しに怯えて山中に身を隠しながらなんとか起死回生のヒット作を生み出そうとしています。
つづいてミラノの極右派上院議員ロンカート。次期市長の座を狙っており、日本武術の使い手と無表情の剛腕という姉弟をつねにボディーガードにひき連れています。
現在のこの二人と過去のテロ事件とのリンクとなるのが、相変わらずローマ在住のガービと《わたし》です。
過去のポップな雰囲気溢れるバー《コッコ・ビル》(50年代に現われたイタリア・コミックのキャラだそう)に入り浸るガービを、妖艶なキアラが訪ねてきます。かつてガービとは微妙な男女関係だったようです。その後キアラは結婚しフィレンツェ住まいですが、大学生の息子アレッサンドロが失踪してしまった様子。警察は「いい歳した大学生だろ」とまともに取り合ってくれず、馴染みの私立探偵を頼って来たのです。
ガービは失恋の痛手のせいか乗り気ではありませんが、助手役から探偵へとステージを上げたい《わたし》に尻を叩かれ、しぶしぶ引き受けることになります。コンビはアレッサンドロが大学生活を送っていたボローニャへ。
この町の中央駅は1980年極右グループの爆弾テロが起き、八十五名の死者、二百名以上の負傷者を出しました(日本人一名も犠牲者になっています)。ガービは駅の被害者慰霊碑の前で黙祷します。
手がかりがつかめない中、《わたし》はアレッサンドロのガールフレンド、エレナにもらったヒントから部屋で物騒なあるものを発見。さらに、アレッサンドロの卒論テーマがなんと《赤い旅団》だったと知ります。
その間、何があったものか、スランプの作家バッターリアが急に新作を発表。ところが、エレナは作中の一節が自分をあてこすっている、と主張します。たしかにアレッサンドロは作家とは知り合いで作品を偏愛していましたが、いったいどういうことなのか? 《わたし》とガービはバッターリアの山荘に向かいます。
この後ものすごい展開となり、それに輪をかけるように、例の危ない姉弟を連れた極右ロンカートや、さらにその後を追う謎のグループがフィレンツェを目指します。
各章の合間には極左中核メンバーのリストとアレッサンドロの調書が挿入されます。初めはメンバーの本名などかなりの欄が空白になっていますが、ストーリーとともに埋められて《隠れた》メンバーがあぶり出され、アレッサンドロの運命が明かされていく仕組みです。
最初は題名からして社会情勢、政治思想をテーマにした堅いミステリだろうと想像していました。
作家は1960年生まれですから、70年代のテロの世紀を実体験したわけではなく、五年間じっくり調査しながら準備していたといいます。中核メンバーたちがそれぞれどのような経路で極左グループに入り、過激化していったのか(思想先行型や困窮生活に追われて、など事情はさまざま)、さらに現在までどのように過去をひきずってきたのか、暗い内面がたっぷりと描かれます。一方で、彼らを偶像視して活動を開始した現代の「新赤い旅団」も出てきますが、表面的な模倣ばかり狙う薄っぺらさがチクリと風刺されています。
また、当時の雰囲気を再現するために、車、ワイン、ポップス、コミックなどの情報があちこちに散りばめられています。(ただ、残念ながら個人的によく知らない部分が多く、例えばランボルギーニだ、フェラーリだとか書かれても、そういや日本にも昔イタリアのスポーツカー・ブームがあったっけ――1980年ころ?――くらいしか感じませんが)。
しかし、ママルカスの魅力は(前作同様)、冒険と心理サスペンスの部分にあるように感じます。作家の筆がひたすら冴えわたるのは、例えば、山中に誘き出され底知れぬ洞穴に落ちた人物が脱出の試みを繰り返すシーン。思いつく脱出策は次々に封じ込められ、到底生還できそうにない修羅場を、ちょっと書くのが憚れる陰惨な方法で克服しようとするのですが……拡大版「陥穽と振り子」といったところ。
あるいは、追い詰められ憔悴していく人物たちの心理描写も作家の得意な部分です。善玉悪玉関係ありません。アリバイ工作する悪役が駅周辺の目立たない安ホテルを探して彷徨するシーンなど(こちらが肩入れするわけでもないのに)息もつかせぬ緊迫感に溢れています。
全547ページの厚い作品を読み終えると満腹度はたっぷり。楽しませてもらいました。渾身の作でしょう。ただ、気になったところが二点ほどありました。
ひとつは語りの人称に関わることです。
『モストラスの失われた蔵書』でも採られていたのですが、一人称語りと三人称語りが混在しています。過去のテロ事件は当然三人称語りですが、現在の失踪事件はニコラがずっと《わたし》として語るわけではなくて、《わたし》のあずかり知らぬ場所で起きる出来事、例えば、作家や上院議員、「新赤い旅団」の動きなどは三人称になります。
ある書評家は、読者がしろうと探偵《わたし》以上の知識をもらえるので、一歩先んじた探偵捜査を楽しめると指摘しています。
たしかに視線が揺れ動く面白さはありますが、ただ、このせいで説明が煩瑣になってしまうのは否めません。読者にはすでに周知のことなのに、《わたし》は知らないので周囲にあれこれ聞き込みを続けた、となってしまうからです。
全部三人称で語ればよさそうなものですが(視点を任意の登場人物に置き、自由に移動させられるのは作者の特権なのですから)、できるだけ自分(の分身)も事件の渦中に参加したいという作者の強い思いの現われなのでしょうか。
もうひとつ、これは明らかに作者が狙ってますが、《わたし》のアクの強さが紳士ワトスン風の記述者の域を超えてどんどん前面に出てきています。もともと及び腰だった主役ガービを尻目に、失踪した大学生の調査を勇躍引き受けるのは、依頼者キララの美貌のため(「最初彼女を見た時から強い思いを感じた」)。ガービの首に縄をつけるようにして訪れたボローニャでは、別の魅力を持つエレナに出会い「最初に会った時から心を奪われた」。二人ともわがものにしようと、失踪事件の手がかりがあると出まかせを口にしたり、女の寝室に滑り込めるように宿泊部屋を勝手に割り当てたり、あれこれ姑息な手を使います。ましてや噓の証言で、気に入らない人物の罪を重くしようと企むのはさすがにやり過ぎ……
ネロ・ウルフの助手アーチーも女好きで口八丁手八丁のうぬぼれ屋でしたが、そのはるか上を行くワトスンの暴走です。これを制御すべきウルフ役ガービは過去の恋の痛手からか、なんだかお座なりの言動で、《わたし》はやりたい放題。キアラやエレニに対しては恋愛感情なぞではなく単なる情欲だ、とあっけらかんと記し、ある人物に対して「こいつは生まれながらにして相手をいらだたせるやつだな」なんて言っていますが、そりゃあんたもだよと読者はツッコミたくもなります。
《わたし》の強烈なキャラ性が印象に残るのは間違いありません。この点作者の企みは成功しています。が、雄大な謎とサスペンスに満ちた事件の合間に、ことあるごとに《わたし》がドヤ顔で出てきてあらぬ方向に暴走するのは計算通りなんでしょうか?
上で、前作が《ギリシャ民族書籍センター》「読者賞」にノミネートと書きましたが、この作品も雑誌『
「ミステリ作家たちの励ましになった」とママルカス本人や書評家はエッセイで語っています。1950年代のマリス時代以降ギリシャにおけるミステリ文学の評価は劇的に向上してきたはずですが、今なおこんな風に言わざるを得ないというのは、ミステリが市民権を得るまでの道がそれほど険しかったということなのでしょう。
 ヴァシリス・ダネリス『列車の男』 カスタニオティス社、2016。 |
 ディミトリス・カペタナキス『われら落つるべし』 エスティア社、2016。 |
ママルカスの本領が冒険のスリルと心理サスペンスにあるのは短編を読めばよくわかります。
『ベカス警部の帰還』(2012年)は《ギリシャ・ミステリの父》ヤニス・マリスが創造した(今や伝説的な)警部を主役に、十五人の現役作家が腕を競ったオマージュ短編集です(エッセイ第6回)。ママルカスは「ヴェネチアの霧」で戦争犯罪人の元ナチス将校を逮捕させるべく、ベカス警部をイタリアへ出張させています。一番やりたかったのは三月の霧が立ち込めるヴェネチアでの大銃撃戦でしょう。
ただし、イタリア人とドイツ人に対してギリシャ人が抱く心情の差はこの短編でも鮮明に現われています。
ヴェネチアでベカスの協力者となる憲兵隊アメリオ准尉は第一次大戦中レフカダ島の地元ギリシャ人たちに匿ってもらった恩義を忘れず、警部に旧友のような好感を持ちます。これに対して、元ナチス将校は占領下で村人を虐殺し、終戦とともに証拠隠滅して逃亡、現在はスイス人富豪に変装して安穏に暮らしているという、どうしようもない悪役に設定されています。
 アシナ・カクリ&コスタス・カルフォプロス編『ベカス警部の帰還』 カスタニオティス社、2012。 【15人のミステリ作家による大先輩マリスとベカス警部へのオマージュ作品集。「ヴァネチアの霧」でベカス警部、初のイタリア出張】 |
サスペンス色がよく出ているのは、『最後の旅』(2009年)所収の「最後の旅程」です。
《わたし》は傲慢な共同経営者に恨みを抱き、殺害して知人に罪をかぶせようとしますが、計画が漏れており、狡猾な知人もその企みを逆利用しようとして、計画全体がぐちゃぐちゃに歪んでいきます。いったい誰が最後に笑うことやら。人物がもがき焦燥するという点ではノワールでしょうが、誰も彼も欲望に満ちた悪党で、どうなろうと自業自得だという感じです。
この作品でも、最初《わたし》は綿密な計画を得意げに語っていますが、途中から三人称語りが時折挿入され、《わたし》のバレバレで間の抜けた様(長距離バス中でのとんでもない殺害方法)が外面から描かれることで、嘲笑というか失笑というか、ヤレヤレという気にさせられます。
長編で見られる語りの人称転換はママルカスのお気に入りのようで、この短編では非常に効果的に使われています。
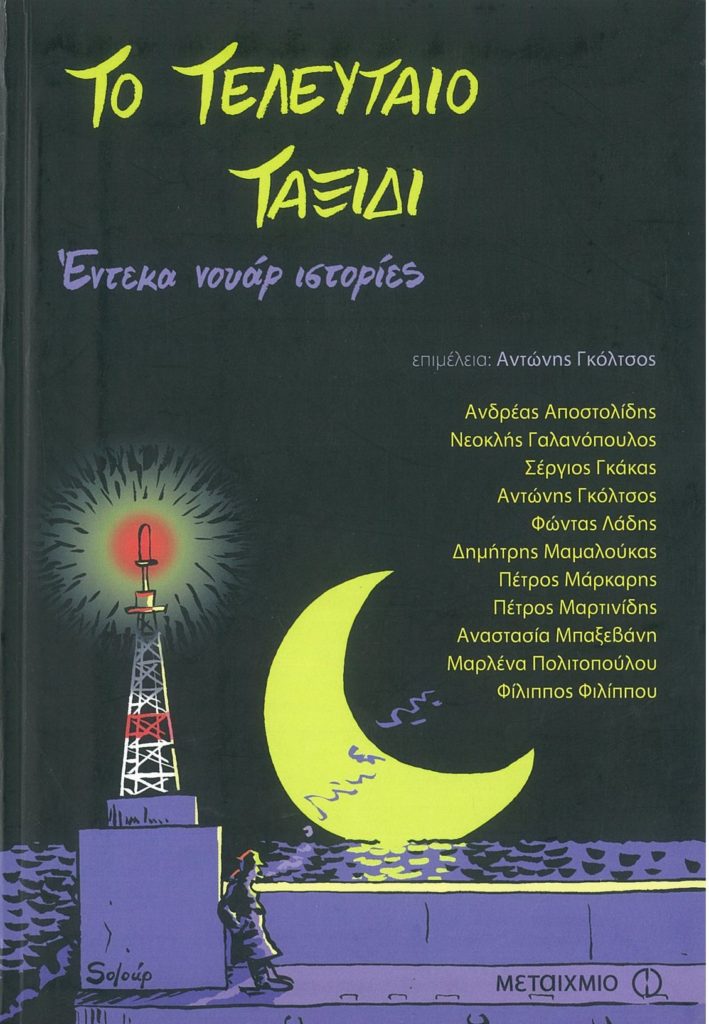 アンドレアス・アポストリディス他『最後の旅』 エスティア社、2009。 【「最後の旅程」所収。バス内でのおバカな殺害方法が出てきます】 |
『ギリシャの犯罪』第一巻(2007年)の「第四の人物」は題名が暗示するように、男女の爛れた四角関係が殺人に繋がっていきます。犯罪の跡を消そうと焦る主人公の脳裏に一瞬、母親の思い出がよぎるのがいやにリアルで、作家の実体験だろうか(それはないでしょうが)と思ってしまいました。
私が初めて読んだママルカス作品はこれだったので、男女の愛憎・欲望関係が犯罪へと転がっていくフィリポス・フィリプ(エッセイ第3回)風の作家だと思っていたのですが、長編『モストラスの失われた蔵書』や『赤い旅団の隠れた中核』では、古書奇譚と宝探しの冒険、社会を震撼させた極左テロを題材として取り込み、基本路線を新たな方向へと広げています。
 アンドレアス・アポストリディス他『ギリシャの犯罪』 カスタニオティス社、2007。 【「第四の人物」所収】 |
なお、ママルカスは二つのジュブナイル・ミステリのシリーズ《時の子供たち》(2011年以降)と《四人の比類なき探偵》(2016年以降)も手掛けており、合わせて8作発表しています(エッセイ第5回)。
なぜ子供向きの可愛らしい本も書くのかというインタビュー質問には、謎を解く子供たちの物語を構想し執筆することは、社会の暗い局面に向き合っているミステリ作家の精神にとって「癒し」なんだよ、と答えています。
 ディミトリス・ママルカス『現金輸送大強盗』 ケドロス社、2016。 【《四人の比類なき探偵》シリーズ第一作】 |
◆◆欧米ミステリ中のギリシャ人(12)――アン・ズルーディのギリシャ人(1)――
アガサ・クリスティーが新婚旅行のコースに組み込むほどギリシャびいきで、作品中にもギリシャ人をたびたび登場させていることは以前書きました。
ところで、それを遥かに超えてギリシャに惚れ込み、当地を舞台にギリシャ人ばかりが登場するミステリを発表し続ける人がいます。英国人作家アン・ズルーディです。ありがたいことに、デビュー作『アテネからの使者』(2007年)が和訳されています。
今回はこの作品についてお話ししたいと思います。
この作品の魅力はまず何といっても不思議な主役探偵でしょう。
ニュースキャスターのような歯切れのいい発音。恰幅のよい身体に高級スーツ、ラコステのポロシャツ、イタリア製のベルト、流行遅れの派手な眼鏡。とりわけ目を引く白いテニスシューズは絶えずクリームで手入れに余念なし。冗談なのか、《翼のあるサンダル》と自ら呼んでいます。作中で《太った男》と言及され、おしゃれなポワロと巨漢のフェル博士が混じったような風采ですが、とにかく素性が謎です。
「緑がかった青のワイシャツを着こんで、上からスーツをはおった。そのとたん、なんとも変わった光沢の灰色の服地がラベンダー色から緑がかった青に変化したように見えた」と、これはちょっとハーリ・クィン氏のイメージも入ってますね。
男の名はヘルメス・ディアクトロス。アテネの調査員と名乗るだけで、どのような機関に属しているのか正体不明。ベカス警部やハリトス警部の勤務するアテネ市アレクサンドラ通りのリアルな警察本部とはまったく無関係のようです。まさかゼウスの寵児?
でも、冒頭には「ヘルメスはかがみこんで美しいサンダルを履こうと紐を結び、はるか彼方に横たわる島に向って、低く波間を飛んだ」と、「オデュセウス」の一節が引用されているし……
ヘルメス本人も、「ディアクトロス」はホメロスに出てくる古いことばで「ゼウスの使者」を指し、ユーモアある古典学者の父親はこれに合わせてヘルメスと名付けたんですよ、と解説してくれます。
舞台となるのはエーゲ海のティミノス島。トルコの山々が見渡せる、とあるのでロドス島のあるドデカニサ諸島のひとつでしょうか。かつてマロリー大尉一行が攻略した要塞の聳えるナヴァロン島に近いようです(ティミノスもナヴァロンも架空の島ですが)。
冒頭で島の若妻イリニの遺体が海から引き揚げられます。イリニは三年前
北欧ミステリのように凶悪な事件が連続するというわけではありませんが、この一件の死をめぐって、一見のどかで平穏な島の底に渦巻くどろどろの愛憎関係やある人物たちの悪辣な過去が炙り出されていきます。
例えば、傲岸で無礼極まりない警察署長。腰巾着の巡査部長。ロマ人に偏見を抱き、娘の恋人を毛嫌いする母親。窮屈な島の慣習に不満の若者。アフリカの投資で一発当てた成金男。過去の傷から暴力と酒に落ちこんでいく漁師、カフェニオにしけこんで噂話に耽る男たち(「島の男たちは怠けものだ。ドイツ人や日本人と全く違う」などと周囲から後ろ指)。
こうした、どこでも見られそうな(セント・メアリー・ミードでも瀬戸内海の獄門島でも同じでしょう)狭く旧弊な村落の人間関係がじわじわと描きこまれ、そこからイリニの死の真相が浮かび上がります。
事件を追う《太った男》ヘルメスは「忠告しておこう。わたしをみくびってはいけない。みくびられると、わたしはかなり汚い手を使うよ」と自ら脅しをかける通り、怒らせると実意に怖い相手。警察よりずっと上の権限で仕事をし、裁きを下すと言います。やっぱりゼウスの使者でしょうね。ただし、「裁き」というのは罪を罰するだけではなくて、不当に貶められた相手には逆に慈しみを施します。そこで、結末では傲慢な罪人への「報い」と同時に、人知れず苦しむ者たちには「癒し」が与えられ、読者は暖かい気持ちにしてもらえます。(謎の解明だけではなく、各人物に応じた癒しまで行ってくれる、というのはなんだか京極夏彦ミステリのようです)。
島でカフェを開いているニコス老は、若いころ南米を回った経験を持ち、島民とは一味違う宗教観を披瀝します(外国人である作者自身のユニークな視点が反映されているかのよう)。老人曰く、この国のキリスト教は見せかけだ。古代の神々がいなくなったなんてとんでもない。神々はいまだに人間にいたずらをしかけるんじゃよ、目立たないように、しかし狡賢く……。
そんなふうに控えめに活動しながら裁きを下すのがヘルメス・ディアクトロス探偵なのでしょう。
細かなところまで描かれる小島の暮らしぶりも魅惑的です。作者は本当にギリシャ好きなんでしょうね。
例えば、若い大工夫婦の結婚式ではお馴染みのブズキが奏でられる中、ふたりが被るオレンジの花冠の絹リボンが結びつけられ(死が二人を分かつまで、ということですね)、参列者は砂糖をまぶしたアーモンドを投げて祝福する、といった場面が出てきます。祝宴では茹でタコ、ラム肉ステーキ、ローストチキン、揚げズッキーニのガーリックソース和え(スコルダレアと呼ばれるこのソース、魚などにも合います)、(やっぱり出てくる)ナスのシチュー、小さな巻き貝などが並び、ギリシャ産ブランデーのメタクサと赤ワインが添えられます。馴染みの漁師は精がつくように、と新婚夫妻にウニを差し入れ。
もっと質素な場合なら四旬節(復活祭前四十日の断食日)。漁師アンドレアス一家はピクニックに出かけ、オリーブ、ニンジン、カリフラワーなど菜食をつまみ、デザートにバニラ味のハルヴァ(チョコレートソースかけ)を食べています。
  【ハルヴァ。左はレストランのサービス品。右は以前自分で作ってみたもの。セモリナ粉(黄色く粒の粗いデュラム小麦の粉)を焦がしてから、シロップ(砂糖、レモンの皮、シナモンスティック、丁子)を加えて冷まし固めます。粒が口に残る独特の触感。】 |
食の情報に読む側はやっぱり反応してしまいます。
「ギリシャの主食は何?」という質問に、パンではなく「豆じゃろ」と例のみやげ物屋のコスタスじいさんは答えてくれましたが、このティミノス島でも主婦が日々の食事にレンズ豆やヒヨコ豆を茹でています。
他には、パスタにこってりしたミートソースとチーズを散らしてオーブンで焼くパスティツォやキャベツの詰め物(ラハノドルマデスという名のロールキャベツ)。どちらもジョージ・ぺレケーノス作品中でワシントンD.C.のギリシャ系探偵たちが舌鼓を打っていました(エッセイ第15回)。
あともう一つ、粉砂糖とシナモンをまぶしたカスタードパイをヘルメス探偵がかじっていますが、街角で売られているブガッツァという名のあまいお菓子です。
  【ブガッツァ。粉砂糖をまぶし、中にはカスタードクリーム。左のような袋入りで売られています。】 |
『アテネからの使者』は2008年の《ITV3クライム・スリラー賞》や《デズモンド・エリオット賞》にノミネートされました。
続く『ミダスの汚れた手』(2008年)以下、第9作『十二月の悪魔たち』(2018年、ただし短編)まで出ており、このうち五作が和訳されています。今後ヘルメス氏の正体がどう明かされていくのか気になります(このまま謎の存在でいてほしいけど)。
次回エッセイでも彼女の作品を読み続けてみようと思います。
| 橘 孝司(たちばな たかし) |
|---|
|
台湾在住のギリシャ・ミステリ愛好家。この分野をもっと紹介するのがライフワーク。現代ギリシャの幻想文学・一般小説も好きです。 「砂男」や「黄金の壷」で知られる「お化けのホフマン」の書いたミステリ『マドモワゼル・ド・スキュデリ』。「モルグ街の殺人」より二十年も前の作品で、論理的な謎解きではなく、パリの奇怪な連続殺人にルイ十四世愛顧の詩人が挑む話。犯人の悪魔的な執念が読みどころです。 |
| 【ホームズ&ワトスン役のイメージを完全に覆した、探偵ウルフ&助手アーチーのデビュー作。ちゃんとした謎解きミステリですが、濃いキャラ同士の掛け合いが魅力。ウルフが騒々しい少年キャディーたちを相手に証言の矛盾を自ら悟らせるよう、粘っこく導いていくシーンは最高です】 |
| 【ヘルメス・ディアクトロスも今後、ハーリ・クィン氏のようにあちらの世界の人になっていくのでしょうか】 |